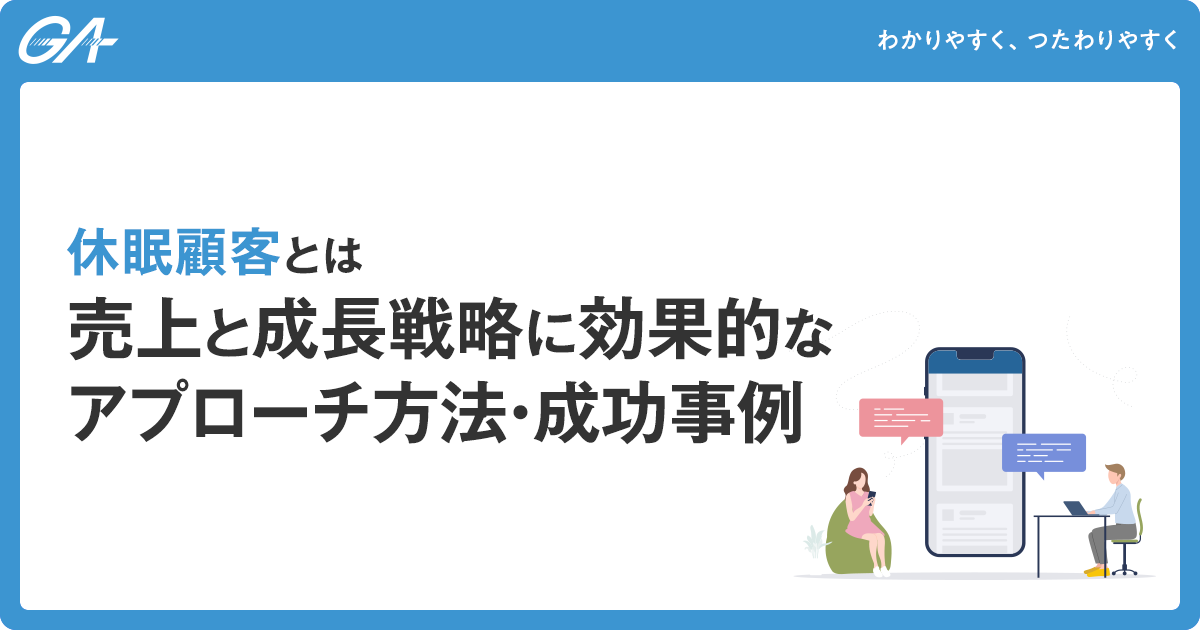BtoBビジネス担当者やEC事業者にとって、顧客獲得競争は悩みの種です。そんな中、多くの企業が実施しているのが「休眠顧客の掘り起こし」です。
一度は自社の製品やサービスを購入・契約したものの、その後、取引が途絶えてしまった顧客は、企業にとって「見過ごせない資産」です。 休眠顧客との再取引は、新規顧客の獲得に比べて、少ない労力で高い成果につながる可能性を秘めています。
この記事では、休眠顧客の基本的な定義から、具体的な掘り起こし施策、そして効果を最大化するための測定方法までを解説します。休眠顧客との関係を再構築し、ビジネスの成長につなげましょう。
休眠顧客とは?
休眠顧客とは、過去に自社の商品やサービスを購入・利用したことがあるにも関わらず、一定期間以上取引や接触が途絶えている顧客を指します。例えば、初回購入以降に継続購入のない顧客や、定期購入を解約した顧客がそれに当たります。
※ただし、「一定期間」は企業や商材によって定義が異なります。
重要なのは、休眠顧客が完全に失われた顧客ではなく、適切なアプローチによって再活性化が期待できる「潜在的な資産」であるという点です。過去の購買履歴やサービス利用歴があるため、ゼロからの関係構築が必要な新規顧客とは大きく異なる特徴を持っています。
なぜ注目されているのか
休眠顧客への注目が高まっている背景には、現代のビジネス環境における複数の要因があります。
1.新規顧客獲得コストの高騰
デジタル広告の競争激化により、リスティング広告やSNS広告のクリック単価は年々上昇しており、従来と同じ予算では十分な新規顧客を獲得することが困難になっています。
2.顧客データの蓄積と活用技術の向上
CRMシステムやマーケティングオートメーション(MA)ツールの普及により、過去の顧客データを効率的に分析し、セグメント化したアプローチができます。
3.LTV(顧客生涯価値)重視
単発的な売上よりも、長期的な顧客関係の構築を重視する企業が増え、既存顧客の価値最大化が経営の重要テーマとなっています。
これらの要因から、休眠顧客の掘り起こしは「効率的な売上向上策」として多くの企業で実践されているのです。
休眠顧客が増える理由
現代の市場環境は急速に変化しており、顧客が一時的に離れてしまう「休眠顧客」が増加しています。その主な理由として、以下の2点が挙げられます。
1. 市場環境の変化
現代では、顧客が商品を買うまでに時間がかかる傾向にあります。
BtoB分野:競合との比較検討に時間がかかることや、意思決定者が複数のため決済に時間がかかることから、その間に顧客の購買意欲が低下し、次の購入タイミングを逃してしまうことがあります。
EC分野:新しいサービスや商品の選択肢が増えたことで、顧客が特定のブランドに固執しなくなり、しばらく利用がないまま忘れられてしまうケースが増えています。
また、経済状況、災害、パンデミックといった外部環境の影響や、業界再編、M&Aによる取引関係の変化も、休眠顧客が増える一因となります。
2. 消費者行動の多様化と情報過多
インターネットの普及により、消費者の購買行動は劇的に変化しました。
いつでも情報収集が可能:顧客は好きなタイミングで簡単に他社の商品やサービスと比較検討できます。これにより、企業が顧客を囲い込むことが難しくなり、顧客との接点が徐々に失われがちです。
メッセージが埋もれる:毎日膨大な情報が発信されるため、自社からのメッセージが顧客に届きにくくなっています。
これらの変化により、休眠顧客が増加しやすい状況が生まれています。
休眠顧客が企業に与える影響

休眠顧客の増加は、売上とコストの両面から企業に深刻なダメージを与えます。
売上利益への影響
休眠顧客の増加は、企業にとって大きな売上機会の損失を意味します。既存顧客が製品やサービスを定期的に購入しなくなるため、売上目標を達成するのが難しくなります。新規顧客獲得に力を入れても、それ以上に顧客が離脱していけば、事業は停滞します。
これは、まるでバケツに開いた穴のような状態です。どれだけ水を注いでも、底から漏れ続けてしまうのと同じで、新規顧客を獲得する努力が水の泡になってしまうのです。
顧客生涯価値(LTV)の低下
LTVとは、一人の顧客が取引を開始してから終了するまでの間に、企業にもたらす利益の総額を指します。休眠顧客は、このLTVが極めて低い状態です。なぜなら、顧客として価値を生み出す期間が途中で終わってしまうからです。休眠顧客が増えることは、企業全体の平均LTVを下げ、長期的な収益性や安定性を損なうことにつながります。
マーケティングコストの増加
休眠顧客が増えると、企業は失われた売上を補うために、新規顧客の獲得にさらに多くのリソースを投入せざるを得なくなります。一般的に、新規顧客を獲得するコストは、既存顧客の維持コストの5倍(※)に達するといわれています。つまり、休眠顧客が増えるたびに、企業はより高価な「新規顧客獲得」という手段に頼らざるを得なくなり、結果としてマーケティング費用が膨れ上がってしまうのです。
このコスト増は、たとえ売上を維持できたとしても、利益率を圧迫します。売上は上がったように見えても、その裏で多額の費用がかかっているため、手元に残るお金が減ってしまうのです。
休眠顧客の存在は、単なる売上の減少だけでなく、企業のリソースを非効率的にしてしまう要因にもなり得ます。
※「1:5の法則」:コンサルティング会社Bain & Company社の名誉ディレクターを務めた、フレデリック・F・ライクヘルド氏による、新規顧客に販売するコストは、既存顧客へ販売するコストの5倍かかる」とされる法則。『ロイヤルティ戦略論』より
休眠顧客への効果的なアプローチ方法

ここでは、メールマーケティング、ダイレクトメール、リターゲティング広告という3つの主要なチャネルを使った具体的な施策をご紹介します。さらには、複数のチャネルを組み合わせることで、顧客の心に響く再活性化を図ります。
メールマーケティング
メールマーケティングはコスト効率が良く、パーソナライズされたアプローチが可能な休眠顧客施策の王道です。まず、顧客の最終購入日やWebサイトの閲覧履歴から休眠度合いをセグメント分けします。休眠期間が短い顧客には、限定クーポンや新商品情報を盛り込んだ「特別なお知らせ」を送信します。
期間が長い顧客には「お久しぶりです」といった挨拶から始め、製品・サービスの改善点やお客様の声を紹介することで、ブランドへの関心を再燃させます。ただし、開封してもらうためには、メールの件名を工夫し、魅力的な文言を盛り込むことが重要です。
また、メールが迷惑メールフォルダに入らないよう、適切な配信システムを利用し、配信停止手続きも分かりやすく記載することで、顧客との健全な関係を維持できます。
ダイレクトメール(DM)
デジタルチャネルが主流の今、ダイレクトメール(DM)は、あえてアナログな手法で顧客に特別な印象を与えます。特に、高額商品や顧客との関係性を重視するビジネスで有効です。DMは、ただのチラシではなく、手書き風のメッセージや、高級感のあるカタログ、サンプル品などを同封することで、受け取った顧客に「自分だけへの特別なメッセージだ」と感じさせることができます。
これにより、ブランドへの信頼感や愛着を再構築するきっかけになります。また、デジタルチャネルでは届きにくい高齢層や、インターネットを利用しない顧客にも直接アプローチできるメリットがあります。印刷や郵送のコストはかかりますが、高い開封率と特別感で、休眠顧客の心に深く響く可能性を秘めています。
リターゲティング広告
リターゲティング広告は、Webサイトやアプリの訪問履歴、メールリストの顧客情報をもとに、SNSやWebサイトの広告枠にパーソナライズされた広告を配信する手法です。休眠顧客が普段利用しているSNSのタイムラインや、ニュースサイトの広告スペースに、過去に興味を示した商品や、特別キャンペーンの広告を表示することで、自然な形で商品の存在を思い出させます。
例えば、過去に閲覧した商品の「在庫が残りわずかです」といった緊急性のあるメッセージや、「あなただけに、50%OFFのクーポン!」といったお得な情報を提示することで、再び商品に興味を持ってもらいます。また、他のチャネルと連携することでさらに効果が高まることが期待できます。メール送信後の反応がない顧客にリターゲティング広告で追いかける、といった施策は非常に有効です。
あわせて読みたい!EC休眠顧客の掘り起こし方|RFM分析×MA活用の実践手法
ゼネラルアサヒが担当した「休眠顧客掘り起こし施策」
私たちは、お客様が抱える課題を深く理解し、クリエイティブの表現力だけでなく、戦略的な企画提案や施策の実行まで、総合的なソリューションをご提供します。以下、当社の事例をご紹介します。
食品メーカー通販会社 A社様
- 休眠顧客を対象にしたDM作成のご相談案件
背景と課題
従来、冷凍食品は複数商品をまとめたセット販売のみを展開。しかし、休眠顧客の購買再開を促進するにあたり、「セットの中に苦手な商品が含まれている場合、顧客は購入を見送る」という課題仮説を立てた。要は久々に購入を検討する休眠顧客にとって、好みに合わない商品が含まれるセット購入は、再購入への心理的ハードルを高める要因になっていると考えた。
施策内容
この仮説を検証するため、休眠顧客を対象に、自由に商品を選択できる「よりどり購入」の仕組みを導入することを提案し、実施。お客様が「購入するカタチ」を選べるようにすることで、再購入のハードルを下げ、購入機会の幅を広げることを狙いとした。
結果と考察
キャンペーン実施後の購買データを分析したところ、単品商品を複数個購入する休眠顧客が一定数確認された。これは、セット内容に制約されずに好みの商品だけを選びたいというニーズが休眠顧客層にも存在することを示しており、当初の仮説が正しかったことが実証された。
購入形態の選択肢を見直すことで、久々の購入における心理的ハードルが下がり、休眠顧客の購買再開を促す重要な要因となったと考えられる。
今後の方針
この結果を受けて、よりどりキャンペーン施策は休眠顧客の活性化施策として継続的に展開していくことが決定した。
休眠顧客施策の成果を高める3つの改善フロー
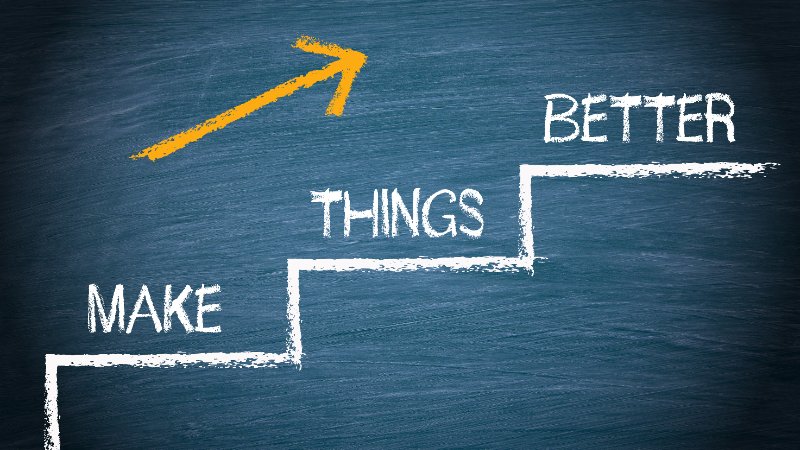
一度きりの施策で終わらせず、継続的に効果を最大化するためには、正しい効果測定と改善の仕組みが欠かせません。ここでは、休眠顧客の掘り起こしを成功させるための具体的なステップを3つご紹介します。
ステップ1. 成果を測るためのKPIを設定する
施策の成果を正確に把握するためには、適切な目標(KPI)を定めることが不可欠です。
◎ECサイトの場合:
再購買率: 施策実施後、再度購入してくれた顧客の割合。
反応率: メールやDMを開封・クリックしてくれた顧客の割合。
LTV(顧客生涯価値)増加額: 再活性化した顧客が、その後どれだけの利益をもたらしてくれたかを見ます。
◎BtoBビジネスの場合:
再受注件数や問い合わせ数、商談化率など。
これらの数字を定期的に追うことで、どの施策が有効だったかを客観的に評価できます。
ステップ2. ABテストで最適なアプローチを見つける
同じ施策でも、アプローチ方法を変えるだけで効果は大きく変わります。そこで役立つのがABテストです。
◎配信タイミング:「午前中にメールを送る」パターンと「夕方に送る」パターンで開封率やクリック率を比較。
◎メッセージ:「価格の安さ」を強調するパターンと、「商品を使うことで得られるメリット」を強調するパターンで反応を比較。
このような地道な検証を繰り返すことで、最も効果的な配信タイミングや訴求方法を見つけ出すことができます。
ステップ3. 顧客層ごとにアプローチを変える
すべての休眠顧客が同じ理由で離脱したわけではありません。顧客の属性ごとに、反応しやすい施策は異なります。
◎分析のポイント:BtoBの場合: 担当者の役職や所属部署、会社の規模。
◎ECの場合:過去の購入商品や最終購入日。
これらのデータをもとに顧客をグループ分け(セグメント化)し、それぞれのグループに最適なメッセージを送ることで、より高い成果を目指せます。CRMツール(顧客管理ツール)を活用すれば、こうした分析とアプローチを効率的に行うことができます。
これらのステップを計画(Plan)→実行(Do)→検証(Check)→改善(Action)のPDCAサイクルとして繰り返すことで、休眠顧客施策の精度はどんどん高まり、長期的なLTVの最大化につながります。
よくある質問(FAQ)

Q.休眠顧客への接触頻度の目安は?
休眠顧客へのアプローチ頻度は業界や商材によって異なりますが、一般的には以下のような基準が用いられています。
BtoB企業:6ヶ月〜1年間の非接点
EC・小売業:3ヶ月〜6ヶ月間の非購入
サブスクリプションサービス:解約後1ヶ月〜3ヶ月
高額商材(自動車・不動産等):1年〜3年間の非接点
BtoBでは決裁サイクルやニーズが長期的なため、半年に一度“状況ヒアリング”を兼ねた接点を設けるケースもあります。頻度が高すぎると逆効果になることもあるため、顧客ごとの適度な間隔や接点設計が重要です。
Q.効果が出やすい施策の特徴は?
効果が出やすい施策の共通点は、「パーソナライズ」と「タイミング」の最適化です。過去の購買履歴や問い合わせ内容を踏まえた個別対応、顧客ごとの休眠期間に合わせた“ベストなタイミング”でのリマインドが高い反応率を生みます。また、限定オファーや無料体験、成功事例の共有も復活の後押しに効果的です。
Q.BtoB/BtoCで最も効果的なアプローチ方法の違いは?
BtoBの場合は、複数担当者との関係づくりや個別提案が重視されます。過去の取引内容や担当者情報を活用してダイレクトメールや電話でのフォローが効果的です。一方、BtoCやECでは、メールキャンペーンやリターゲティング広告など、「デジタル接点」をパーソナライズして活用する手法が成果につながりやすくなります。
Q.法令(特商法/個人情報保護)に注意するポイントは?
休眠顧客への施策を実施する際は、特定商取引法や個人情報保護法の遵守が必須です。無断での営業メール配信や、意図しない個人情報の利用はコンプライアンス違反となる恐れがあります。事前に顧客の同意を得ているか、配信の解除が容易になっているかを必ず確認しましょう。
Q.顧客管理ツール(CRM・MA)はなぜ必要?
顧客管理ツール(CRM・MA)の導入により、顧客情報の一元管理やアプローチ履歴の可視化、効果測定が飛躍的に効率化します。データにもとづいたセグメント抽出や、最適タイミングでのアプローチ設計も容易にできるため、限られたリソースで最大限の成果を生み出せます。中長期的なLTV向上のためにも早期導入が推奨されます。
まとめ
本記事では、休眠顧客の企業への影響を理解し、効果的な掘り起こし施策や施策の測定・改善フローにつなげる内容をご紹介しました。BtoB企業やEC事業者にとって、休眠顧客の掘り起こしは「高い費用対効果」と「既存の信頼関係を活用できる」大きな武器です。施策を着実に積み上げ、PDCAを回すことでLTV向上と収益の安定化が期待できます。もし「自社の休眠顧客対策を強化したい」「休眠顧客対策の具体的な施策に悩んでいる」といった課題があれば、さまざまなご提案も可能です。ぜひお気軽にご相談ください。