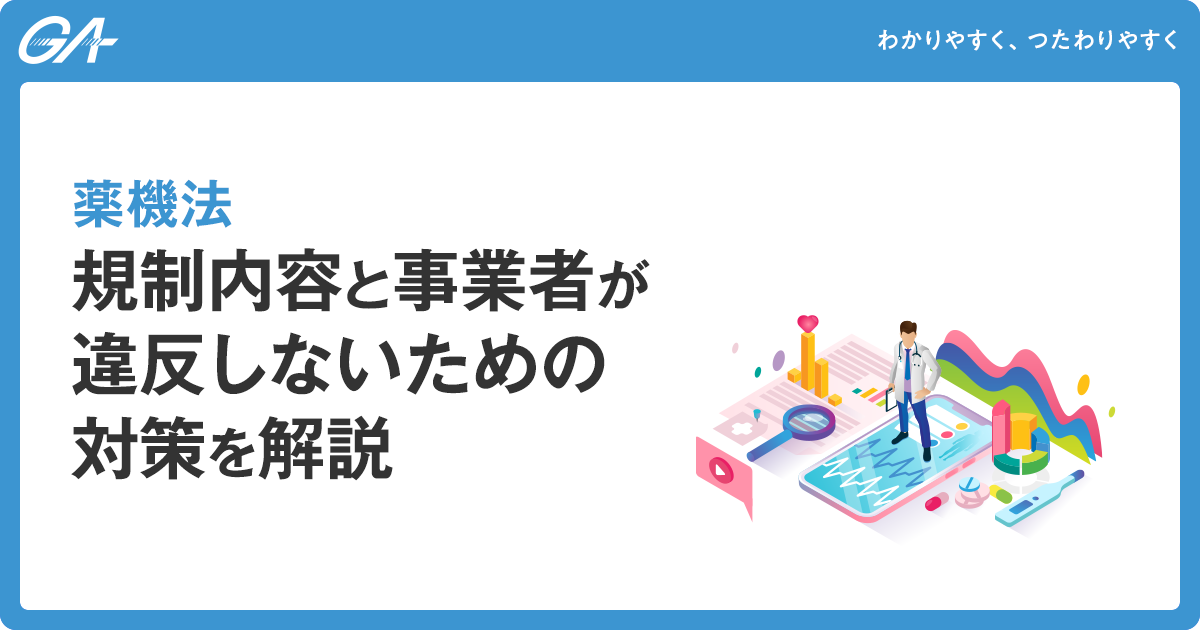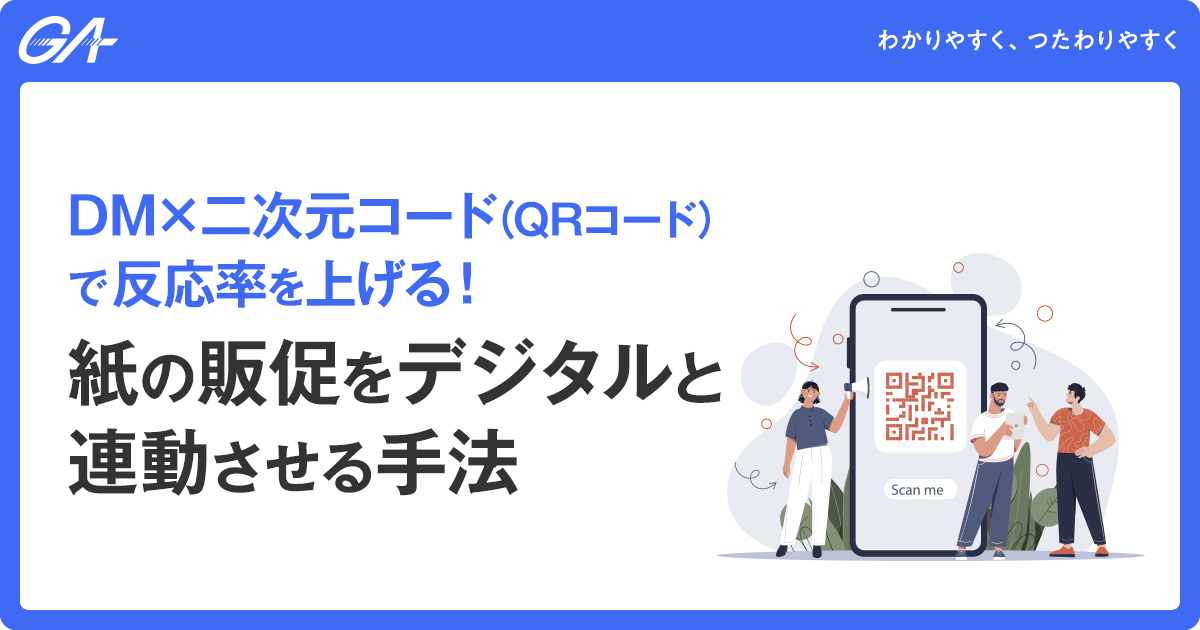化粧品や医薬品、健康食品の広告は、多くの人々の健康や美容への関心を反映し、日々街頭やメディアで目にする機会が非常に多いものです。しかし、これらの製品を販売する際に避けて通れないのが「薬機法」への対応です。
「薬機法って聞いたことはあるけれど、具体的に何を規制しているのかわからない」「広告やWebサイトで使える表現と使えない表現の境界線がわからず不安」といった声を、多くのEC担当者の方からお聞きします。
薬機法は複雑で専門性が高く、違反すると重い罰則が科される可能性があるため、正しい知識を身につけることが不可欠です。本記事では、EC事業者が最低限知っておくべき薬機法の基礎知識から、違反を避けるための対策まで、わかりやすく解説します。
薬機法とは?

薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品などの「ヒトの健康や生命に直接関わる製品」に関して、製造・流通・販売から広告表現に至るまでを定めた日本の法律です。
かつては「薬事法」と呼ばれていましたが、2014年の法改正により「薬機法(やっきほう)」に名称が変わり、規制対象が広がりました。薬機法の大きな目的は、国民の健康と安全を守ることにあります。私たち消費者が安全で効果のある製品を安心して選べるよう、厳しい基準で規制しています。
なぜ薬機法の知識が必要か?
薬機法の知識が必要な理由は、主に以下の4つが挙げられます。
1. 法的責任の回避
薬機法違反は刑事罰の対象となり、懲役や罰金が科される可能性があります。また、企業の社会的信用失墜や売上への深刻な影響も避けられません。正しい知識を持つことで、これらのリスクを未然に防ぐことができます。
2. 消費者の安全確保
薬機法は消費者を誤解や健康被害から守るための法律です。適切な表現を使用することで、消費者に正確な情報を提供し、安全な商品選択をサポートできます。
3. 競合他社との差別化
薬機法を遵守した適切な広告制作は、消費者からの信頼獲得につながります。信頼性の高いブランドイメージを構築することで、競合他社との差別化が可能になります。
4. 事業の継続性確保
薬機法違反により行政処分を受けると、販売停止や営業許可取り消しなど、事業継続に関わる重大な処分を受ける可能性があります。継続的な事業運営のためには、薬機法への対応が不可欠です。
薬機法直近2-3年の改正ポイント(2022年~2024年)
| 改正時期 | 改正項目 | 主な内容 |
| 2022年 | オンライン服薬指導の恒久化 | • コロナ特例措置から恒久制度へ移行• 処方箋医薬品のオンライン服薬指導が正式解禁• 初回対面原則など一定条件下で実施可能 |
| 2022年 | 薬局機能の明確化・強化 | • 地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の認定制度本格運用• かかりつけ薬剤師・薬局機能の法的位置づけ強化 |
| 2023年 | 添付文書の電子化完全義務化 | • 医薬品・医療機器等の添付文書が完全電子化• 紙媒体から電子媒体(二次元コード等)での提供へ移行• 患者・医療従事者への情報提供方法が大幅変更 |
| 2023年 | 医薬品等の安定供給体制強化 | • 製造販売業者に安定供給計画の策定・報告義務• 供給不安情報の国への報告義務化• 流通記録の保持義務とトレーサビリティ強化 |
| 2023年 | 行政処分情報の公示範囲拡大 | • 薬機法違反企業の処分情報をより詳細に公開• 消費者の適切な選択を支援する透明性向上 |
| 2024年 | AI・デジタル技術活用の制度整備 | • AI診断支援システム等の承認審査体制整備• デジタル療法(DTx)の薬事承認ルール明確化 |
| 2024年 | 個人輸入・越境EC規制の強化 | • 海外からの医薬品個人輸入に対する監視強化• 違法な健康食品・未承認医薬品の取締り厳格化 |
| 2024年 | サプリメント・健康食品監視体制の強化 | • 機能性表示食品の事後チェック体制強化• SNS・インフルエンサーマーケティングの薬機法適用厳格化 |
2025年薬機法改正の概要はこちら
薬機法が規制対象|主な5つの製品
薬機法の規制対象となる主な製品カテゴリは、以下の5つです。それぞれ定義と特徴を押さえておきましょう。
1.医薬品
医薬品の定義は、以下の通りです。(薬機法2条1項)
(定義)
第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一 日本薬局方に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
引用元:e-gov法令検索|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
「医薬品」とは、人または動物の疾病の診断・治療・予防を目的とし、日本薬局方に収められているもの、またはこれらに準じる製品です。
市販薬や処方薬、漢方薬などが該当します。
最も厳しい規制を受け、販売や広告には許可や厳格な基準があります。
2.医薬部外品
医薬部外品の定義は、以下の通りです。(薬機法2条2項)
2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であって人体に対する作用が緩和なものをいう。
一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的にために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの
引用元:e-gov法令検索|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
医薬部外品は、医薬品と化粧品の中間に位置する製品です。有効成分が配合されており、一定の効果効能を表示することが認められていますが、医薬品ほど強い作用はありません。
例)薬用化粧品、デオドラント、栄養ドリンク、育毛剤などがあります。
医薬部外品を宣伝する際は、厚生労働省が許可した効能・効果の範囲内で表現しなければいけません。それ以外の、あたかも薬のような効果があると思わせる表現や、許可されていない効果を謳うことはできません。
3.化粧品
化粧品の定義は、以下のとおりです(薬機法2条3項)
3 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
引用元:e-gov法令検索|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
「人体を清潔にし、美化し、魅力を増し、皮膚もしくは毛髪を健やかに保つ」ことを主な目的としています。
例えば、スキンケア用品・メイクアップ用品・シャンプーコンディショナーなどがそれにあたります。効能表現や広告には細かいガイドラインがあります。
4.医療機器
医療機器の定義は、以下のとおりです(薬機法2条4項)
4 この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
引用元:e-gov法令検索|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
「人や動物の疾病の診断、治療または予防に使用する」器具や装置のことです。
体温計や血圧計から高度医療機器(CTや人工関節など)まで幅広く対象となり、製品ごとにクラス分類や承認・認証・届出などが必要です。広告にも独自のルールがあります。
5.再生医療等製品
再生医療等製品の定義は、以下のとおりです(薬機法2条9項)
9 この法律で「再生医療等製品」とは、次に掲げる物(医薬部外品及び化粧品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
一 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの
イ 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成
ロ 人又は動物の疾病の治療又は予防
ニ 人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの
引用元:e-gov法令検索|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
細胞・組織等を用いた医療(再生医療、細胞治療、遺伝子治療など)などが該当します。従来の医薬品・医療機器と異なる基準や手続きが設けられており、最先端医療分野での事業者は特に厳しく情報管理が求められます。
薬機法で規制されていること
薬機法は、大きく3つの柱で規制を行っています。EC担当者や広告制作者は、どこにリスクや留意点があるのか、正確に理解しておく必要があります。
1.医薬品等の製造・販売の規制
医薬品等を製造または販売するには、厚生労働大臣あるいは都道府県知事からの許可・登録が必要です。無許可での製造販売は違法で、罰則の対象となります。
医薬品等の製造販売業の許可(12条1項)
【製造販売業の許可】
第十二条 次の表の上欄に掲げる医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をしてはならない。
| 許可制の対象となる行為 |
| 薬局の開設 |
| 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造・販売 |
| 医療機器又は体外診断用医薬品の製造・販売 |
| 再生医療等製品の製造 |
| 医薬品の販売 |
| 高度管理医療機器等の販売・貸与 |
| 医療機器の修理 |
| 再生医療等製品の販売 |
| 登録制の対象となる行為 |
| 医療機器又は体外診断用医薬品の製造 |
2.広告表現の規制
消費者を誤導する広告を防ぐために、医薬品などの効果効能について厳しい規制が設けられています。
| 虚偽・誇大広告の禁止 |
| 事実と異なる内容の広告 |
| 効果や安全性を過度に強調する表現 |
| 医学的根拠のない効果の標榜 |
| 未承認の効能効果の標榜禁止 |
| 承認を受けていない効能効果を謳うこと |
| 医薬品的な効果を暗示する表現 |
| 特殊疾病用医薬品等の広告の制限 |
| 医療関係者以外の一般人対象の広告は禁止 |
医薬品については広告可能な情報・表現も細かく定められており、健康食品やサプリメントでも「医薬品的効能効果の暗示」などが厳重に監視されています。
- 広告規制対象
広告代理店、SNS、インフルエンサー投稿、LP、ECサイト内の商品説明、SEO記事など、すべてが「広告」とみなされる点にも注意が必要です。
また、広告代理店、インフルエンサー、アフィリエイター、ライターなどに関わる人も同様です。課徴金や刑事罰の対象となる可能性があるため、広告制作時には細心の注意を払いましょう。
3.品質・安全性の確保
薬機法は、製品の品質・安全性を保証するため、厳格な製造管理・品質管理体制(GMP、GQP、GVP等)の構築を義務付けています。万一、問題や副作用が発生した場合の対応や、トレーサビリティ確保も企業の責任です。
消費者が安心して製品を選べるために、最も重要です。
| 処方箋医薬品の販売規制 |
| 処方箋を持たない者に対して、原則処方箋医薬品を販売できない |
| 容器・被包上の表示に関する規制 |
| 容器・被包上の表示や記載内容は、薬機法のルールに従う必要がある |
| 薬機法違反の医薬品の販売禁止 |
| 薬機法に違反している医薬品等の販売は禁止されている |
| 記載が禁止される事項 |
| 未承認の効能・効果・性能、および保健衛生上危険がある用法・用量・使用期間を記載しない |
薬機法違反を犯した場合の罰則
薬機法に違反した場合、以下のような段階的な罰則が科されます。違反の内容や程度により、複数の処分が同時に適用される場合もあります。
刑事罰
最も重い罰則が「刑事罰」です。不正な製造販売や重大な広告違反などの場合、懲役刑や1億円を超える罰金刑が科せられる例もあります。違反行為の重大さによっては、社会的信用を根本から失墜させる結果となり、再起が困難になることも十分考えられます。
行政指導
違反の軽重にかかわらず、監督官庁から「指導」「警告」などの行政指導が入るケースもあります。改善報告書の提出や再発防止策の徹底など、営業活動やマーケティング活動に大きな制約がかかります。
措置命令
薬機法違反に該当する製品や広告などには「措置命令(回収命令や販売停止)」が出されることもあります。ECサイトや流通で既に販売済みの場合でも、全商品の即時回収や返金対応が求められるケースもあり、深刻な経済的打撃につながります。
課徴金納付命令
薬機法改正により、著しい違反行為や不正表示の場合には「課徴金納付命令」が科されるようになりました。売上高の一定割合を国に納付しなければならず、多大な経済的損失につながります。
事業者が薬機法違反をしないための7つの対策

では、企業やEC担当者はどのような点に注意し、どんな対策を取ればよいのでしょうか。主な7つのポイントを解説します。
1.社内での薬機法教育・セミナー受講
薬機法の基本知識から最新の改正情報まで、定期的な社内教育と外部セミナーへの参加を強く推奨します。特にマーケティング部門、商品企画、コンテンツ制作に関わる全スタッフへの教育は必須です。新入社員研修での薬機法講習はもちろん、外部パートナーや制作会社との契約時にも薬機法遵守の確認を徹底しましょう。年1回以上の定期研修と、法改正時の随時アップデートにより、組織全体の薬機法リテラシー向上を図ることが重要です。
2.広告・記事制作時のチェック体制強化
Webサイト、ランディングページ、SEO記事、SNS投稿、メルマガ、チラシなど、あらゆる媒体・表現物が薬機法チェックの対象となります。必ず薬機法の専門知識を持った責任者による確認・校正プロセスをルール化してください。特に「効果効能」「安全性」「体験談」の表現は厳格な審査が必要です。複数名による段階的チェック体制を構築し、公開前の最終確認を怠らないことで、違反リスクを大幅に削減できます。
3.許認可・表示ルールの再点検
取扱う商品ごとに必須となる許可や届出、成分名や効能・効果などの表示ガイドラインを定期的に見直してください。法改正や新たな通知公表時には、迅速に自社商品への影響を分析し、必要であればリニューアルや修正も徹底しましょう。
4.第三者機関や専門家の監修を活用
業界に精通した薬機法専門家、弁護士、行政書士、薬機法管理者などの外部専門家を活用し、広告表現の監修や事前確認を行うことを強く推奨します。社内の判断だけに頼らず、客観的な視点での法的リスク評価を受けることで、見落としがちな違反要素を事前に発見・修正できます。継続的な顧問契約により、迅速な相談体制を整備することも効果的な対策の一つです。
5.景表法や健康増進法とのクロスチェック
薬機法の遵守だけでは不十分です。「景品表示法」による誇大広告規制、「健康増進法」による健康保持増進効果の表示規制など、関連法令との複合的なチェックが必要です。これらの法律は重複する部分も多く、一つの表現が複数の法律に違反するケースも珍しくありません。各法律の要求事項を統合的に理解し、より厳格な基準での広告制作を行うことで、包括的なコンプライアンス体制を構築できます。
6.違反しないライティングや広告デザイン会社の選定
薬機法に精通し、豊富な実績と専門ノウハウを持つ制作会社への外部委託は、自社リソースの負担軽減と違反リスクの大幅削減を両立する有効な手段です。制作会社選定時は、薬機法対応の実績、専門資格保有者の在籍状況、チェック体制の充実度を重点的に評価しましょう。また、制作後の修正対応や法改正時のアップデート対応まで含めた包括的なサービス提供が可能な会社を選ぶことが重要です。
7.万が一に備えた危機管理・法務体制の整備
薬機法違反の疑いが生じた場合の早期対応フロー、証拠保全、関係機関への報告、社内外への適切な情報共有など、包括的な危機管理体制の整備が不可欠です。特に行政指導や立入検査を受けた際の対応マニュアル作成、外部弁護士との連携強化、メディア対応の準備なども重要な要素です。平時からのシミュレーションと定期的な体制見直しにより、有事の際も迅速かつ適切な対応が可能となり、企業ダメージの最小化を図ることができます。
あわせて読みたい!ペット用品ECの薬機法違反を防ぐ!知っておくべき規制とNG表現
まとめ
薬機法は、EC事業者にとって避けて通れない重要な法律です。特に健康食品、化粧品、医療機器などを扱う事業者は、製品の製造・販売から広告表現まで、幅広い領域で薬機法の規制を受けます。
違反した場合の罰則は年々厳格化されており、刑事罰、行政処分、課徴金など多様な制裁措置が用意されています。これらのリスクを回避するためには、正確な知識の習得と適切な対策の実施が不可欠です。
しかし、薬機法は非常に複雑で専門性が高く、事業者が独力で完全に対応することは困難です。安全で効果的な広告制作を行うためには、薬機法に精通した専門家との連携が重要になります。