ECサイトの構築方法にはいくつかの種類があります。「フルスクラッチ開発」は既存のパッケージやモール型サービスとは異なり、ゼロから独自にシステムを設計・開発します。この手法は、高度な自由度や業務との高い親和性が魅力です。しかし、その一方で、開発にかかるコストや社内リソース、運用体制へのハードルも小さくありません。
本記事では、フルスクラッチ開発のメリットとデメリット、よくある失敗例、そして導入判断のチェックポイントまでを網羅的に解説します。自社に本当に必要なのかを見極める判断材料としてご活用ください。
フルスクラッチ開発とは?|意味と他の構築方法との違い

そもそも「フルスクラッチ」とは何か?
「フルスクラッチ開発」とは、その名の通り“ゼロから作る”ECサイト構築の方法です。一般的なECサイト構築には、ShopifyやMakeShopといったSaaS型のプラットフォームや、あらかじめ用意されたECパッケージを使うケースが多いですが、フルスクラッチはこれらとまったく異なります。
SaaSやパッケージでは「既存の機能を組み合わせて構築する」イメージに対し、フルスクラッチは必要な機能も画面設計も、すべて一から設計・開発するアプローチです。
そのため、自由度は圧倒的に高く、「自社の業務フローやマーケティング施策に完璧にフィットしたECサイト」を実現することができます。
ただし、裏を返せば、デザインやシステム構成、セキュリティ、データベース設計などもすべて自社または開発パートナーと相談しながら決めていく必要があるため、それなりのIT知識や体制、そして予算が求められます。
具体的に、以下のような違いがあります。
| 比較項目 | フルスクラッチ | SaaS(例:Shopify) | ECパッケージ(例:ecbeing) |
| 開発自由度 | ◎(制限なし) | △(提供機能内で制限あり) | ◯(ある程度のカスタマイズ可) |
| 初期コスト | 高い(数百〜数千万円) | 低い(数千〜数万円) | 中程度(数万円〜) |
| 開発期間 | 長い(半年〜1年以上) | 短い(最短数日〜数週間) | 中程度(2〜6カ月) |
| 機能拡張の柔軟性 | ◎ | △ | ◯ |
| 技術リソース必要 | 多い(エンジニア常駐前提) | 少ない(ノーコード対応) | 中程度 |
どんな企業に選ばれているのか?
フルスクラッチは、誰にでもおすすめできる開発手法ではありません。特に「初めてECを立ち上げる」といった小規模なスタートアップや個人事業主には、SaaSやパッケージのほうが圧倒的に導入しやすく、コストメリットもあります。
一方で、フルスクラッチが選ばれるのは、次のような企業に多く見られます。
大手・中堅の小売業・メーカー・専門店
例:ファッションブランド、スポーツ用品メーカー、食品加工業など
こうした企業は、販売チャネルや倉庫管理、POSシステムなどとの複雑な業務連携が求められるため、既存のASPやSaaSでは対応しきれないことが多くなります。
業界特化型の商習慣がある事業者
例:BtoB EC(掛売、見積、取引先別価格など)、定期購入型サービス、予約販売など
標準的なEC機能では不十分なケースが多く、商流・フローに最適化したシステム構築が必要とされます。
すでに基幹システムや独自業務システムを持っている企業
例:独自の在庫管理、受注管理、CRMなど
これらのシステムとスムーズに連携させたい場合、既製システムではAPI連携やデータ構造の制限が壁になります。その点、フルスクラッチであれば、社内仕様に合わせた柔軟なシステム構成が可能になります。
メリットとデメリットを徹底比較
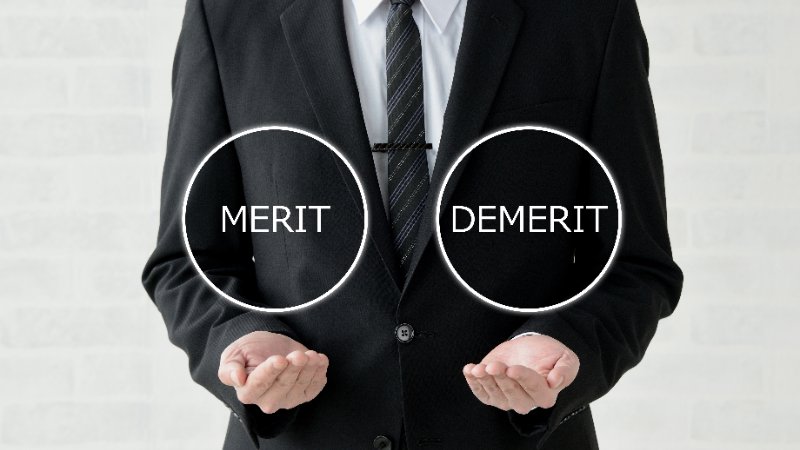
フルスクラッチ開発は、すべてをゼロから構築するため、自由度が非常に高い一方で、コストや時間といった大きなハードルも存在します。ここでは、フルスクラッチの「メリット」「デメリット」に加え、導入後によくある「後悔・失敗パターン」もあわせて整理します。
フルスクラッチのメリット
業種やビジネスモデルに最適化できる
フルスクラッチ最大の魅力は、自社の業種・業態にぴったり合わせたシステム設計ができることです。法人向けのBtoB ECや、受注生産・定期便といった特殊な販売モデルに対応したい場合、パッケージ型やASPでは限界があります。フルスクラッチなら、そうした要件にも柔軟に対応可能です。
社内業務に合わせた運用設計ができる
基幹システムや在庫・物流システムといった既存の業務インフラと、ECサイトをスムーズに連携できるのもフルスクラッチならでは。「営業の受注処理と連動したECシステムがほしい」といった場合も、運用現場の流れに合わせて設計できます。
デザインやSEOの自由度が高い
テンプレートに縛られないため、ブランディングに特化した独自デザインや、SEO施策に最適化された構造設計も可能です。URL構造、メタ情報の最適化、AMP対応など、パッケージ型では制限されるような細かなカスタマイズにも対応しやすく、マーケティング視点でも有利に働くケースがあります。
フルスクラッチのデメリット
初期コストが非常に高い
最大のデメリットはやはり開発費用の高さです。小規模でも数百万円規模、中〜大規模になると1,000万〜2,000万円以上かかるケースも珍しくありません。加えて、保守・運用費用も継続的に発生するため、長期的な投資としての覚悟が求められます。
開発期間が長く、スピード感に欠ける
一般的な開発期間は6カ月〜1年超と長く、競合に先駆けてスピーディにEC事業を立ち上げたい場合には不向きです。また、仕様確定〜設計〜実装〜テストといった工程を段階的に進める必要があり、社内の意思決定のスピードも求められます。
ベンダー選定と信頼関係構築が必要
自社のビジネス理解が深く、長期間にわたり協力関係を築ける開発ベンダーの選定が極めて重要です。特に運用開始後も、改修や機能追加のたびに依頼が発生するため、パートナーとしての信頼性や対応力が大きく影響します。
よくある失敗パターン
要件定義が不十分なまま進行
フルスクラッチでは、開発前の要件定義の精度が成果を左右します。「とりあえず始めて、あとで調整すればいい」と考えてスタートすると、後から大幅な手戻りや追加費用が発生するリスクが高まります。
社内に十分な運用体制がなかった
フルスクラッチで構築したECサイトは、日々の更新・改善・トラブル対応を自社で回していく体制が必要です。ところが、運用担当者のスキルやリソースが不足していたり、部門間の連携が取れていなかったりすると、期待通りのパフォーマンスが出せません。
開発・運用コストを甘く見積もった
「最初の見積もりでは◯百万円だったはずが、結局は倍近くかかった」といった声も少なくありません。これは、要件追加や仕様変更に伴う追加工数の積み重ねや、保守費用を見落としていたことが主な原因です。費用面では常に「バッファ(予備予算)」を設けておくことが重要です。
このように、フルスクラッチ開発には大きな自由度と引き換えに、相応のリスクと責任が伴います。成功の鍵は、「なぜフルスクラッチにするのか」を明確にし、その目的に沿った要件定義と体制づくりを行えるかにかかっています。
自社ECにフルスクラッチは必要?判断ポイントチェック
フルスクラッチ開発は、確かに柔軟性や拡張性に優れていますが、すべての企業に適しているとは限りません。以下のフローチャートに答えて、フルスクラッチを検討する必要があるか参考にしてみましょう。
フルスクラッチ開発の進め方とプロセス
フルスクラッチでECサイトを構築する場合、開発の自由度は高まりますが、その分、工程や体制の整備も重要になります。この章では、一般的なEC構築の流れと、実際に開発を進めるうえでのポイントについて解説します。
ECサイト構築の一般的な工程とは?
フルスクラッチに限らず、ECサイト構築は以下のようなステップで進められます。
1. 要件定義:
まず、どのようなECサイトを作るのか、その目的や機能要件、予算、納期などを明確にします。例えば「会員制サイトにしたい」「在庫管理システムと連携したい」「多言語・多通貨に対応したい」など、必要な要件を洗い出し、関係者間で共通認識を持つことが重要です。
2. 設計:
要件に基づいて、画面の構成や機能仕様を決めていきます。UI/UX設計やシステムアーキテクチャの設計など、ユーザー体験とシステムの構造を設計図としてまとめます。
3. 開発:
設計フェーズで定義した仕様に沿って、実際にコードを書いてシステムを構築します。フロントエンド、バックエンド、データベース、API連携など、多岐にわたる技術領域を網羅的に対応する必要があります。
4. テスト:
完成したシステムに対して、動作確認やバグのチェックを行います。機能テストや負荷テスト、セキュリティテストなどを行い、リリースに向けての品質を担保します。
5. リリース:
公開準備が整えば、実際のサーバー環境に反映してリリースします。その後も、運用監視・改善・保守といったフェーズが継続していきます。
外注と内製の違い
開発体制をどう組むかも大きなポイントです。
- 内製(自社開発):
社内に開発チームがある場合、要件定義〜保守まで自社で一貫して進めることが可能です。自社のビジネス理解が深い分、コミュニケーションロスが少なく、柔軟な対応がしやすい点が強みです。 - 外注(開発/制作会社に委託):
一方で、社内にエンジニアがいない・不足している場合は、開発を外部に依頼するケースが一般的です。経験豊富な制作会社を選べば、技術力やプロジェクトマネジメント力を活かした進行が可能になります。ただし、発注側としての要件整理力やディレクション力が求められます。
ゼネラルアサヒのお問い合わせはこちら
気になる費用と期間|フルスクラッチはなぜ高い?

フルスクラッチ開発は、既存のパッケージやASPを使わず、ゼロからECサイトを構築する方法です。そのため「高額になる」「時間がかかる」といったイメージを持たれがちですが、実際にはどのくらいの費用と期間を見込む必要があるのでしょうか。ここでは、開発規模別の費用感や、機能単位でのコスト、開発にかかる期間の目安を具体的に紹介します。
初期費用の目安|
フルスクラッチ開発では、サイトの規模と要件に応じて費用が大きく変動します。以下はあくまで目安ですが、実際の開発費をイメージする際の参考になります。
- 小規模なECサイト:500万円〜
基本的な商品登録・カート機能・会員機能などを備えたシンプルな構成。UI/UXのカスタマイズは最小限に抑えられます。 - 中規模なECサイト:800万〜1,200万円
多カテゴリの商品管理や複雑な在庫管理、キャンペーン機能など、ビジネスモデルに合わせたカスタマイズが求められるケースです。 - 大規模なECサイト:2,000万円以上
ポイントシステム、定期購入、外部システム連携、多言語対応などが必要になると、大幅な工数が発生します。
特に、独自性の高い設計や外部連携の多さは費用増加の要因となります。「500万円以内で作りたい」と考えている場合は、機能を絞り込み、開発または制作会社とよく相談することが重要です。
まとめ
この記事では、フルスクラッチ開発の特徴やメリット・デメリット、適したプロジェクトのタイプなどについて詳しく解説しました。フルスクラッチとは、既存のシステムやパッケージに頼らず、ゼロから完全に自社仕様でシステムを構築する方法です。自由度の高さや独自性の実現が大きな魅力ですが、その一方で、開発コストや期間、保守負担の大きさといったリスクも伴います。
特に、社内でソースコードを管理し、全社的にEC化を進めたい大企業にとっては、フルスクラッチは有力な選択肢となるでしょう。一方で、導入コストやスピードを重視したい場合は、ASPやクラウドEC、ECモールといった他の手法も含めて検討することが重要です。
市場や技術トレンドの変化が激しいEC業界では、柔軟な対応力と将来を見据えた判断が求められます。自社のビジネスニーズやリソース、成長戦略を踏まえたうえで、最適な構築方法を選ぶことが成功への第一歩となるでしょう。





