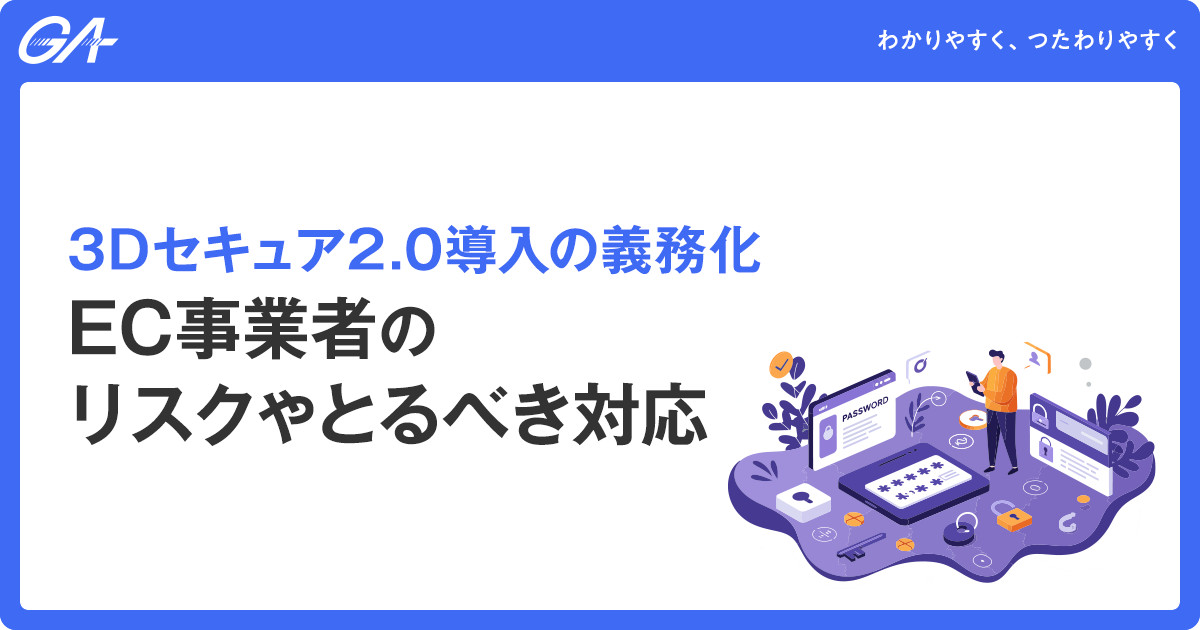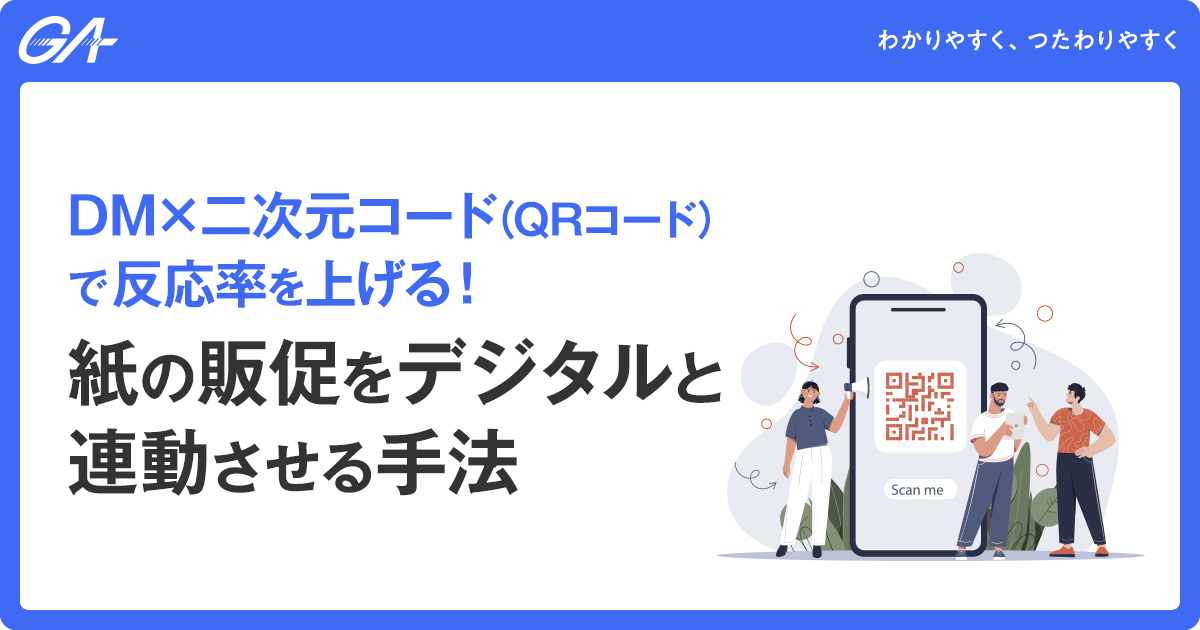2025年3月末より、すべてのECサイトに「3Dセキュア2.0(EMV 3Dセキュア)」の導入が義務化されました。これはクレジットカードの不正利用が急増している現状を受け、経済産業省やカード業界が推進する安全対策の一環です。しかし「何から始めればいいのか」「導入すると本当に売上に影響はないのか」と不安に感じるEC運用担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、3Dセキュアとは何か、2.0への進化のポイント、義務化の背景やリスク、企業がとるべき対策までわかりやすく丁寧に解説します。
3Dセキュア2.0(EMV 3Dセキュア)とは
3Dセキュア2.0(EMV 3Dセキュア)は、オンライン決済におけるセキュリティを強化するための本人認証技術です。
従来の「3Dセキュア1.0」を進化させた形で、より安全かつスムーズな購買体験を実現することを目的に、国際ブランド(VISA、Mastercardなど)が中心となって設立した団体「EMVCo(イーエムブイコ)」によって策定されました。
この3Dセキュア2.0では、カード情報に加えて、利用者の端末情報や行動履歴など、さまざまな情報を組み合わせたリスクベース認証が採用されています。その結果、以前のように購入時に毎回パスワードを求められることなく、よりスムーズな購入体験が可能になりました。
3Dセキュア1.0と2.0の違い
ここで、3Dセキュア1.0と2.0の違いを分かりやすく表にまとめました。
| 項目 | 3Dセキュア1.0 | 3Dセキュア2.0 |
| 認証方法 | 事前登録したパスワードや静的情報で本人認証 | リスクベース認証(RBA)+必要に応じてワンタイムパスワードや多要素認証 |
| ユーザー体験 | パスワード入力が必要で、入力忘れや誤入力による決済離脱が発生しやすい | 条件に応じてパスワード入力不要の「フリクションレス認証」が可能。リスクが高い場合のみワンタイムパスワードなどを要求 |
| 対応デバイス | 主にPC想定 | PC・スマホ・アプリなどマルチデバイス対応 |
| セキュリティ | 静的な認証情報に依存 | リスクベース認証(RBA)+多要素認証で強化。取引リスクに応じた柔軟な認証が可能 |
| フレームワーク | HTMLベース | Web API/モバイルSDKで柔軟に実装可能 |
主な違いとその意味
1. パスワードが不要に
3Dセキュア1.0では「本人認証用のパスワード」を事前に登録する必要がありましたが、忘れてしまうと決済ができないという課題がありました。
3Dセキュア2.0は、パスワード入力は原則不要です。端末情報、購入履歴、IPアドレス、行動パターンなどを組み合わせて不正を検知します。
2. 認証方式の柔軟化
3Dセキュア2.0では、本人の信頼度が高い場合は、認証画面が表示されない「フリクションレス(非介入)認証」が可能です。逆に、リスクが高いと判断された取引では、SMSやアプリ通知などでワンタイムパスワード(OTP)などを使った認証が求められます。
3. スマホ・アプリ時代に対応
現代の購買体験はPCだけでなく、スマホやアプリからのアクセスが主流です。3Dセキュア2.0はモバイルSDKにも対応しており、マルチデバイスで安全な認証を実現します。
導入の背景
ECサイトにおける不正利用の現況
近年、オンラインショッピングの普及に伴い、クレジットカード情報を悪用した「不正利用被害」が急増しています。特に新型コロナウイルス感染症以降、非対面決済の需要が拡大したことで、ECサイトを狙った不正アクセスやカード情報の漏えい事件が相次いでいます。
日本クレジット協会の調査によると、2024年のクレジットカード不正利用被害額は 550億円を超え、過去最高を更新しました。そのうち約9割が「番号盗用」などの非対面取引(ECサイトでの決済)によるものと報告されています。つまり、実店舗ではICチップ対応などのセキュリティ強化が進む一方で、ECサイトのセキュリティは依然として脆弱な部分が多いのが現状です。
不正利用の手口は年々巧妙化しており、主に以下のようなパターンが見られます。
| 主な不正利用手口 | 内容 |
| フィッシング詐欺 | 偽サイトやメールでカード情報を盗み取る手口 |
| スキミング | カード情報を不正に読み取って複製する |
| クレデンシャル・スタッフィング | 流出したID・パスワード情報を使って不正ログインする |
| ボット攻撃 | 自動化ツールで大量の不正決済を試みる |
こうした攻撃は、単なる「技術的な不備」だけでなく、「本人認証の仕組みが弱い」ことを突くものです。従来の3Dセキュア1.0では、本人認証の際にパスワード入力を求める方式でしたが、ユーザーの入力ミスや煩雑さによる離脱、またはパスワード漏えいによる不正突破など、運用上の課題が多くありました。
「3Dセキュア2.0(EMV 3Dセキュア)」は、より高度な本人認証と快適な購入体験を両立できる、オンライン取引上の安全を確保するための仕組みといえます。
ECサイトに3Dセキュア2.0を導入するメリット
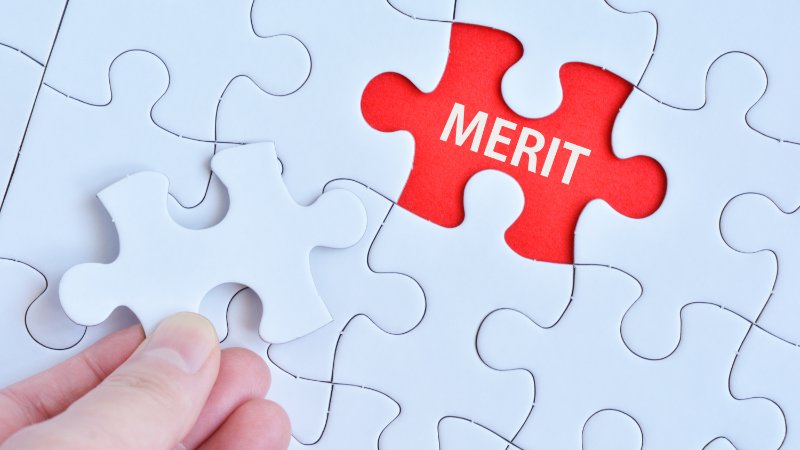
ECサイトに3Dセキュア2.0を導入するメリットは、主に2つあります。
メリット1.チャージバックのリスクの回避
3Dセキュア2.0では、決済時に顧客の本人確認を厳格に行うため、不正利用のリスクを大幅に低減します。万が一、不正利用が発生した場合でも、適切に認証プロセスを経ていれば、カード会社が損失を負担することになります。これにより、ECサイト事業者は高額な返金や補償のリスクから解放され、経営的な安定性を確保できます。
メリット2.セキュリティ性能の向上
3Dセキュア2.0は、従来のバージョンに比べて、より高度な本人認証技術を採用しています。顧客の端末情報、行動分析、リスクスコアリングなどの多様な情報を活用し、不正利用を高精度で検知できます。そのことは、顧客のクレジットカード情報を安全に保護し、顧客にとって、より安全な決済環境を提供することになります。また、サイトに対する信頼と安心感にもつながります。
3Dセキュア2.0義務化を無視した際のリスク
【原文】
– 割賦販売法35条の17の8第2項および第4項
– 同法施行規則133条の9第1号および第4号
これらの法令により、決済代行会社は、加盟店が不正利用防止措置を取っていない場合:
– 新規契約の申し込みを拒絶
– 既存加盟店に対し、合理的期間内での是正を指導
– 加盟店が指導に従わない場合、カード決済契約を解除する義務があります。
クレジットカード・セキュリティガイドライン【5.0版】(2024年3月改訂)
クレジットカード・セキュリティガイドライン【6.0版】(2025年3月改訂)
2024年3月に改訂された「クレジットカード・セキュリティガイドライン(5.0版)」では、2025年3月末までに、原則すべてのEC事業者が、クレジットカード決済において「3Dセキュア2.0(EMV 3Dセキュア)」を導入することが推奨されています。また、2025年3月に改訂された6.0版では、導入の有無を定期的に調査し、未対応加盟店には是正指導や契約解除などの措置を行うことが明記されています。
そのため、2025年4月以降は、決済代行会社やカード会社から「3Dセキュア2.0(EMV 3Dセキュア)」対応可否について確認されることになります。
もし3Dセキュア2.0を導入していない場合、次のようなリスクが発生します。
決済ができない
国際ブランドおよび主要カード会社は、3Dセキュア2.0非対応のECサイトに対して、カード取引の承認を制限または拒否する方針を示しています。そのため、ECサイト側では「決済エラーが発生する」「カード決済が急に利用不可になる」といった問題が起きる可能性があります。購入手続きが完了できなくなり、顧客のカゴ落ち率や機会損失が増加します。
不正利用の際、補償負担が発生する
3Dセキュア2.0を未導入の場合、不正利用が発生した際の損害補償はEC事業者(加盟店)が負担するケースが増えます。導入済みであれば、認証済み取引について原則としてカード会社側が補償する「チャージバックの責任のシフト」が適用されます。未対応取引は補償の対象外となり、自社で不正利用分の損害を負担することになります。また、返金対応や顧客サポートなど追加コストも発生し、経営リスクが高まります。
カード会社・決済代行会社との契約が停止される
上記にある割賦販売法により、セキュリティ基準を満たさない加盟店との契約については、決済代行会社が契約停止や解除を行う義務があります。主要代行会社では、不正利用リスクの高い未対応事業者とは契約更新を拒否する場合もあります。結果として、主要カードブランドによる決済ができなくなり、ECサイトの信頼性の低下につながります。
顧客離れによる売上減少
決済エラーや不正利用被害が報じられることで、消費者の不安が高まり、「このサイトは安全か」「カード情報を入力しても大丈夫か」という心理的なハードルが上がります。その結果、顧客離れが発生し、売上の低下につながります。一度失った信頼を回復するには時間がかかるため、セキュリティ対応を怠ることは長期的なブランドのダメージを招きます。
3Dセキュア2.0の導入の流れととるべき対策

3Dセキュア2.0の導入には、システム面だけでなく、運用や顧客体験の観点からも慎重な準備が必要です。
以下のステップに沿って進めることで、スムーズな導入・運用が可能になります。
1. 決済代行会社の仕様を確認する
まず、自社で利用している決済代行会社(PSP)がどのブランド・仕様に対応しているかを確認します。
多くの代行会社では、3Dセキュア2.0対応が進んでいますが、ブランドによっては実装状況や対応バージョンが異なる場合があります。
既存契約の内容を見直し、必要に応じてプラン変更やシステム更新を検討しましょう。
2.3Dセキュア2.0対応の決済代行会社の選定
もし現在利用している決済代行会社が未対応の場合は、対応済みのサービスへ切り替えることを検討します。
選定時には、以下の観点で比較するとよいでしょう。
- 対応ブランド(Visa、Mastercard、JCBなど)の範囲
- リスクベース認証(RBA)への対応有無
- システム連携の容易さ(API仕様・開発ドキュメントの整備状況)
- サポート体制とセキュリティポリシー
3.APIの実装と設定
3Dセキュア2.0では、従来よりも**複雑な通信フロー(トランザクション処理)**が必要となるため、API連携を通じて本人認証データを送受信します。
そのため、エンジニアやシステム担当者がAPIの仕様を理解し、認証フローの実装・設定を正確に行うことが重要です。
また、サーバー側だけでなく、フロントエンド(ユーザー画面)との整合性にも注意が必要です。
4.UI・UX対応を行う
本人認証時のユーザー体験(UX)は、離脱率に直結します。
3Dセキュア2.0では、スマートフォンでの生体認証やワンタイムパスコード入力など、認証画面をいかにスムーズに見せるかが重要になります。
そのため、導入時には次のような対応が求められます。
- モバイル端末でのレスポンシブ表示最適化
- 認証画面の導線・説明文の工夫
- ローディング時間の短縮
- 認証エラー時のリカバリーガイドの明示
セキュリティ強化だけでなく、顧客体験を損なわないUI設計が重要です。
5.テスト環境で動作を確認、本番環境での運用
すべての設定が完了したら、まずはテスト環境(Sandbox)で取引テストを行います。
テストでは、正常系・異常系の両パターン(例:認証成功/失敗、通信エラーなど)を検証し、ログの取得・エラー処理を確認します。
問題がなければ本番環境へ移行し、運用を開始します。
導入後も、定期的なログ分析やセキュリティ監視を行い、不正検知精度の向上とUX最適化の両立を目指すことが重要です。
EC事業者からのFAQ

ここでは、実際に多くのEC事業者から寄せられる質問に基づき、3Dセキュア2.0の導入や運用に関する疑問点を整理します。
Q. 個人情報保護法の観点から3Dセキュア2.0における必要な同意はどのように取ればいい?
3Dセキュア2.0を導入することで、ユーザーの端末情報や取引履歴などが、本人認証のためにカード会社や認証サーバーに送信される場合があります。
そのため、「個人情報保護法第18条(利用目的の特定)および第23条(第三者提供)」に基づき、利用規約やプライバシーポリシー内に以下のような内容を明記しておくことが推奨されます。
- 本人認証の目的でクレジットカード会社等に情報を提供すること
- 送信される情報の範囲(例:端末情報・取引情報)
- 情報の保管・利用範囲についての説明
また、ECサイト上で決済前に「利用規約に同意する」チェックボックスを設けることで、適法な同意取得を明確化できます。
クレジット取引セキュリティ対策協議会の資料はこちら
Q. 登録済みのカード情報は、遡って3Dセキュア2.0認証をしなくてはならない?
既に登録されているカード情報について、過去分を遡って認証し直す必要はありません。
ただし、2025年3月以降に行われる新規決済や再決済時には、3Dセキュア2.0による認証フローを経る必要があります。
つまり、「カード情報の再登録」ではなく、「決済時点で本人認証を行う」運用へと移行する形です。
一方で、継続課金・サブスクリプション型サービスなどの場合は、決済代行会社の仕様により初回のみ認証が必要なケースや定期的な再認証を求められるケースもあります。利用中の決済事業者に確認しておくと安心です。
Q. アメリカ向け販売事業者への特別な注意が必要(越境ECの場合のみ)
越境ECでアメリカの顧客を対象に販売する場合、3Dセキュアの適用範囲や強制力が国によって異なる点に注意が必要です。
米国では、3Dセキュア2.0の導入率は欧州・日本に比べてまだ限定的であり、利用者によっては「本人認証画面が表示されること自体に不安を感じる」ケースもあります。
そのため、以下のような運用上の工夫が求められます。
- 購入画面に「安全な決済手続き(3Dセキュア対応)」であることを明記する
- 英語版サイトのFAQに認証プロセスを説明する
- リスクベース認証を活用し、低リスク取引はスムーズに通す設定にする
国際ブランドの仕様を遵守しつつ、現地の顧客体験を考慮した柔軟な設定が理想です。
まとめ
3Dセキュア2.0の導入は、単なる技術的対応にとどまらず、「安全な購買体験を提供するための企業姿勢」を示す取り組みです。義務化対応を怠ることは、決済リスクやブランド毀損だけでなく、顧客の信頼を失う最大の要因にもなりかねません。
今後、カード会社や決済代行会社の基準はさらに厳格化が進む見込みです。
早めの導入検討・実装を進め、安心して買い物ができるEC環境を整備していくことが、企業の事業継続にも重要です。