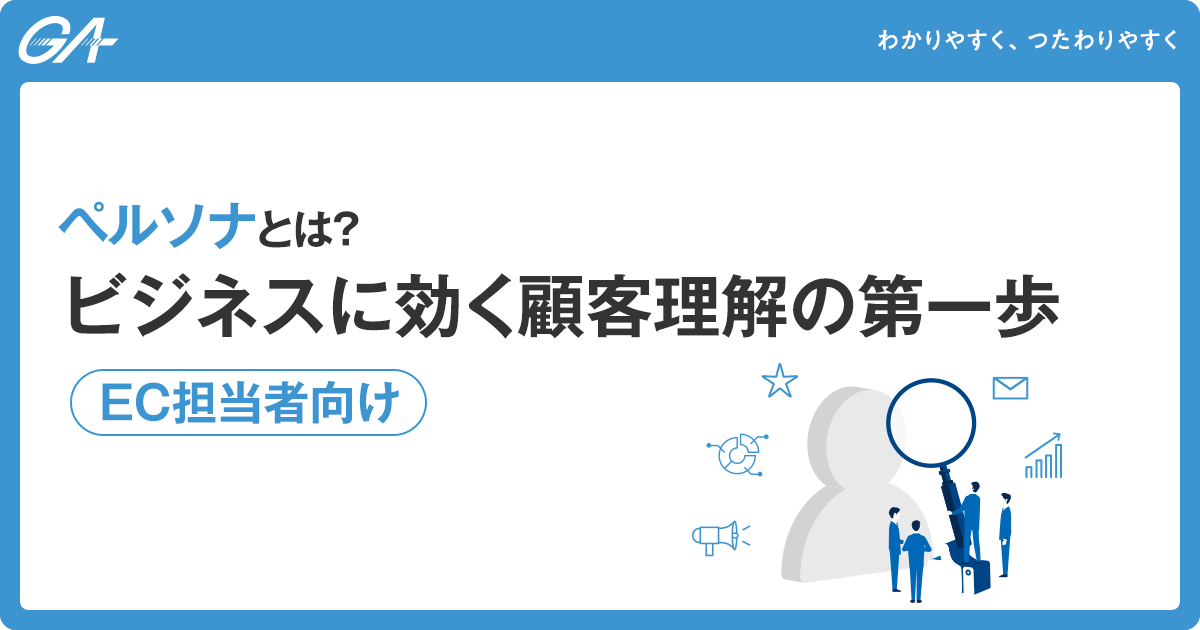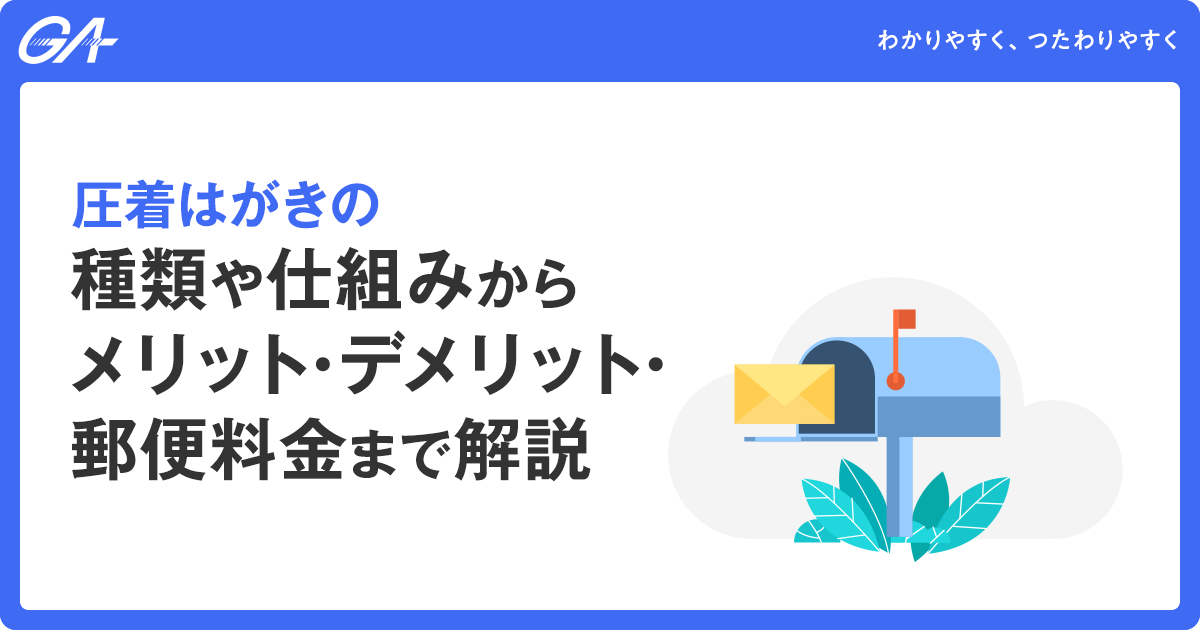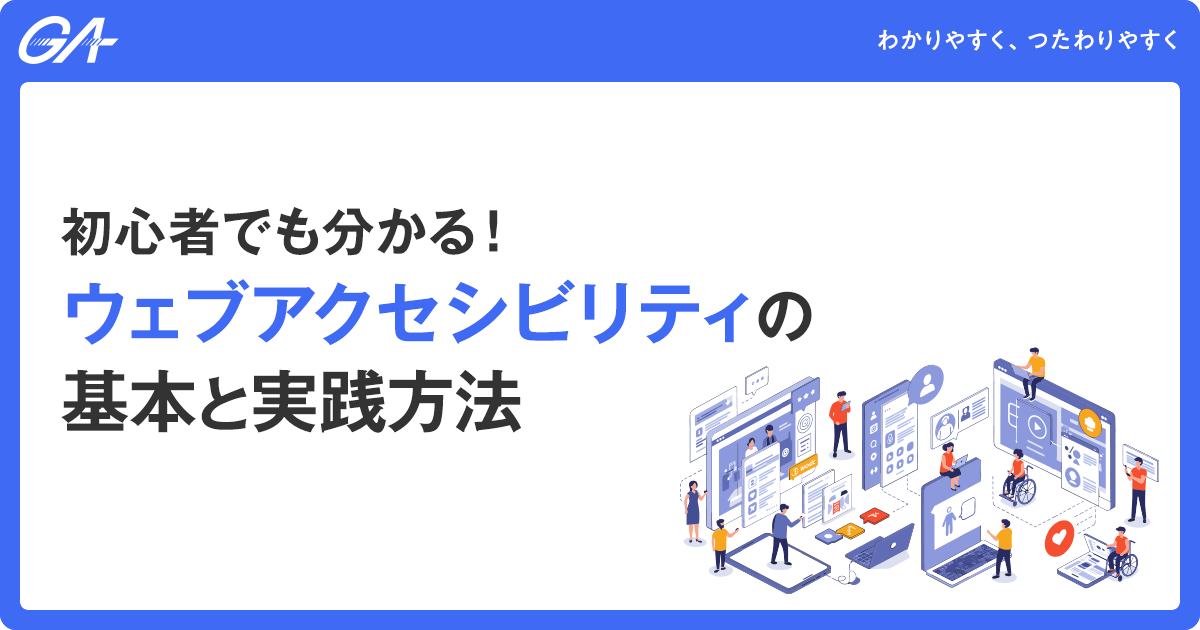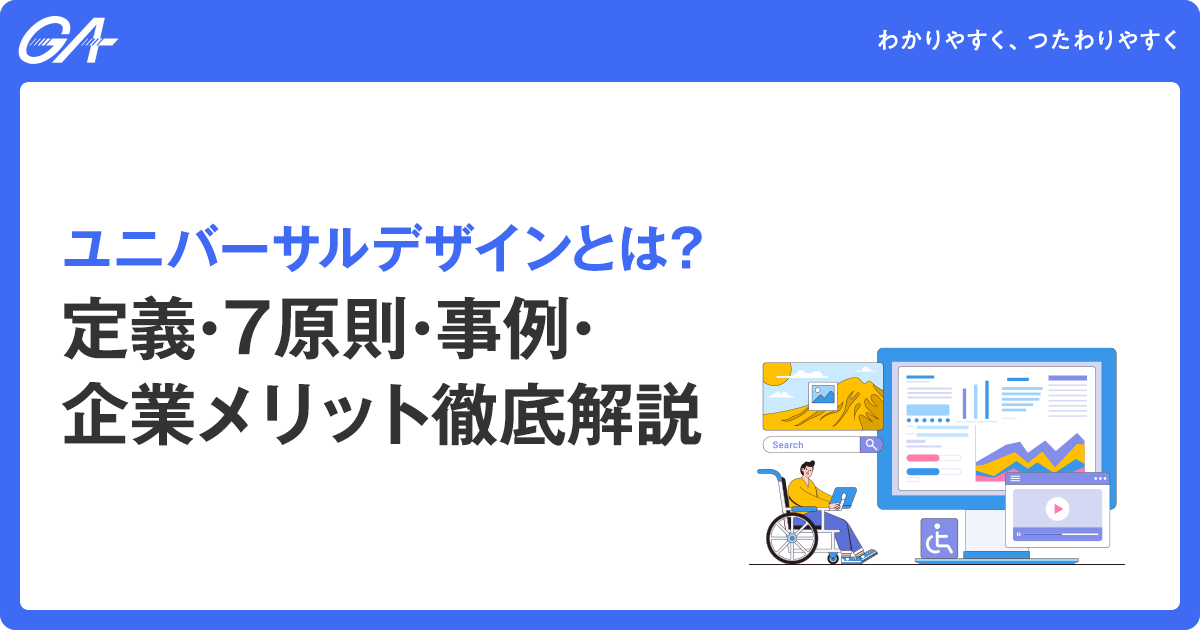デジタルマーケティングにおいて「ペルソナ」という言葉は、もはや聞き慣れた存在かもしれません。しかし、「ターゲットとの違いがよくわからない」「設定してみたけれど活用できていない」という声もよく耳にします。
ECサイトの運営において、誰に、どのように商品やサービスを届けるかを決めるのは、マーケティングの根幹です。その意思決定に軸を与えるのが「ペルソナ設定」です。
本コラムでは、ペルソナの定義から、EC・WEBマーケティングにおける必要性、メリット、設定方法までをわかりやすく解説。ペルソナを「形だけ」で終わらせず、成果につなげる実践的な活用法をお届けします。
ビジネスでのペルソナとは?

「ペルソナ(persona)」とは、本来ラテン語で「仮面」や「役割」を意味する言葉です。ビジネスでは、商品やサービスの“理想的な顧客像”を具体的に描いたモデルを指します。
例えば、「30代後半の女性で、都内在住、共働き、仕事と家事を両立しながら、週末は家族との時間を大切にしている」――といった具合に、年齢、性別、居住地、職業、ライフスタイル、価値観、課題などを細かく定義します。
このようにリアルな人物像として設計することで、マーケティング施策や商品開発の“判断基準”となり、よりユーザー目線の施策を打てるようになります。
ターゲットとの違い
「ターゲット」は、ある程度広い層を指すのに対して、「ペルソナ」はたった一人の具体的な人物像にまで落とし込む点が異なります。
| 指標 | ターゲット | ペルソナ |
| 特徴 | 属性をグループで捉える | 実在しそうな1人の人物像 |
| 例 | 20〜30代の女性 | 28歳・神奈川在住・広告代理店勤務の独身女性・ZARA好き |
| 活用シーン | 市場分析・広告配信 | コンテンツ設計・商品企画 |
ペルソナはターゲットよりも深く、顧客理解を高めるための「思考の補助ツール」です。言い換えると、ターゲットは「誰に売るか」、ペルソナは「どんな人が、なぜそれを買うのか」を明確にします。
ペルソナの重要性

WEBマーケティングにおけるペルソナ設定の意味
Webマーケティングにおいて、「誰に何を伝えるか」は最も基本かつ重要な要素です。その「誰に」を具体的にするのが、ペルソナ設定の役割です。ターゲット層を「30代女性・主婦」といった曖昧なイメージで捉えるのではなく、「35歳・東京都在住・2人の子を育てる共働き主婦・ネット通販で時短グッズを探している」といったように、実在する人物のように描くことで、ユーザーの課題や行動に寄り添ったマーケティングが可能になります。
このように具体的なペルソナがあることで、SEO対策や広告運用、SNS発信、コンテンツ企画などすべての施策において一貫したメッセージ設計が実現します。また、ユーザー視点を明確にすることで、無駄な施策を省き、限られたリソースで高い成果を得ることができます。
さらに、社内で共通の顧客像を共有することで、マーケティング部門だけでなく、商品開発やカスタマーサポートとの連携もスムーズになり、顧客体験全体の質向上につながります。
ペルソナとは、ただのマーケティングの資料ではなく、ビジネスを顧客視点で進化させるための基盤なのです。
ペルソナ設定のメリットとは?
メリット1:チーム内で顧客像の共通認識ができる
ペルソナは、チーム全体で「誰のために何をするか」の共通言語になります。部署間の意見対立や認識のズレを防ぎ、スムーズな意思決定を促します。
例えば、デザイナーがUI設計をする際も、営業が提案資料を作るときも、「●●さんならこの表現がいいだろう」と具体的に想像できるため、ブレない一貫性が生まれます。
メリット2:ユーザーニーズを明確にできる
ペルソナを定めると、顧客が抱える「課題」や「欲求」に自然と焦点が当たります。
単に「30代女性」という属性だけでは見えなかった、
- 時短に価値を感じる
- 子育てと仕事を両立したい
- トレンド感よりも実用性重視
といったニーズが明確になり、より解像度の高いマーケティング戦略を構築できます。
メリット3:訴求力の強化
広告やLP、メルマガ、SNS投稿などにおいても、ペルソナが明確であることで、「誰に・どんな言葉で届けるか」が明瞭になります。
結果として、反応率が高まり、LTV(顧客生涯価値)を意識したコミュニケーションが可能になります。
メリット4:精度の高いマーケティングにつながる
Google広告、SNS広告、CRM設計などにおいても、ペルソナ設定は活きてきます。ユーザーセグメントやオーディエンス設計の土台になるため、無駄な広告配信を減らし、費用対効果を改善する一助となります。
ペルソナ設定のコツや注意点

思い込みや理想だけで判断しない
多くの企業がやりがちなのは、「こうであってほしい」という理想の姿をペルソナとして設定してしまうことです。しかし、実際には存在しない理想の顧客像をもとにすると、現実とのズレが生じ、マーケティング施策が的外れになるリスクがあります。企業がペルソナ設定を行う際、このようなズレがよく見受けられます。
ペルソナは想像ではなく、実際の顧客をしっかりと理解したうえで作るべきものです。
根拠ある情報で定義する
情報収集の方法として
・自社ECサイトの購入データ・SNS分析・ユーザーインタビュー・口コミサイトやSNSでのコメント・カスタマーサポートへの問合せ内容・Googleアナリティクスなど
できる限り定量・定性の両面から「根拠のある情報」をベースに設計することが大切です。
定期的に見直す
市場環境やターゲットのニーズは変化します。3年前に作ったペルソナが今も通用するとは限りません。
定期的に見直し・更新を行うことで、常にユーザー目線のマーケティングが保てます。
ペルソナの作り方:3STEP
それでは、実際にペルソナを作ってみましょう。
STEP1. 顧客について調査・分析をする
まずは、前述した根拠ある情報である既存顧客データやアクセス解析、SNSのコメントなどから、
- 年齢・性別・職業などの基本属性
- 行動パターン(利用デバイス、閲覧時間帯)
- 購買に至る動機・課題
などを洗い出します。
インタビューやアンケートが取れる場合は、定性的な「声」も非常に貴重です。
STEP2. 生成AIに投げてみる
最近では、ChatGPTなどの生成AIを活用することで、ペルソナの叩き台を作成することが可能です。
例えば、
「30代女性・ECサイトでスキンケア商品を購入する人のペルソナを具体的に作って」
と依頼するだけで、ある程度リアルなペルソナが生成されます。もちろんこれは“出発点”にすぎませんが、アイデアを広げるには有効です。
さらに、STEP1で集めた調査・分析したデータをまとめて生成AIを活用すると、より理想的なペルソナの作成ができるでしょう。
STEP3. 改善は人力で修正する
AIで生成したペルソナに対して、社内の知見や現場のリアルな顧客像を照らし合わせながら、情報を肉付け・調整していきましょう。
「自分たちの顧客は実際どうなのか?」という視点で、ライフスタイルや趣味、言葉のトーンや行動背景、価値観まで精緻に設計すると、活用度の高いペルソナに仕上がります。
FAQ
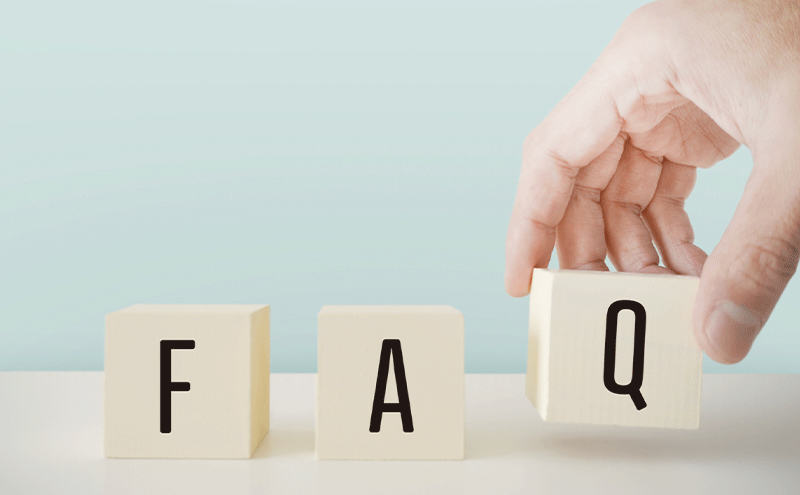
ペルソナの作り方についてご紹介しましたが、実際に作成する過程で「こんなときはどうすればいいの?」など具体的な疑問があるという方も多いのではないでしょうか。そこで、ペルソナ設定に関して寄せられることの多い質問と、その回答をまとめました。
ぜひ参考にしてください。
Q:小規模事業者でもペルソナは作るべきか?
A:はい、むしろ小規模事業者こそペルソナを明確にすべきです。限られた予算・リソースの中で効果的な施策を打つためには、「誰に」「何を」届けるかの的確な判断が必要です。
売上の8割は、特定の2割の顧客層が担っているといった「パレートの法則」からも、主要顧客の深掘りが成果に直結することがわかります。
Q:何人分くらい作ればいいの?
A:基本的には「1~2人」で十分です。多すぎると軸がブレて活用しにくくなります。まずは最も重要なメイン顧客のペルソナを一人作成し、必要に応じてサブのペルソナを追加する流れが現実的です。
まとめ:ペルソナは「考える力」の土台になる
ペルソナとは単なるマーケティング用語ではなく、「顧客理解」を深め、施策の精度を高めるための思考ツールです。
特にECサイトの運営やWEBマーケティングでは、「何となく」の感覚に頼らず、データや実感をもとに設計されたペルソナが、成果に直結する意思決定を支えます。
最初は難しく感じるかもしれませんが、1人の人物像を丁寧に描くことから始めてみましょう。そこから、貴社のビジネス全体において「誰のために」がより明確になり、本質的な戦略が見えてくるはずです。