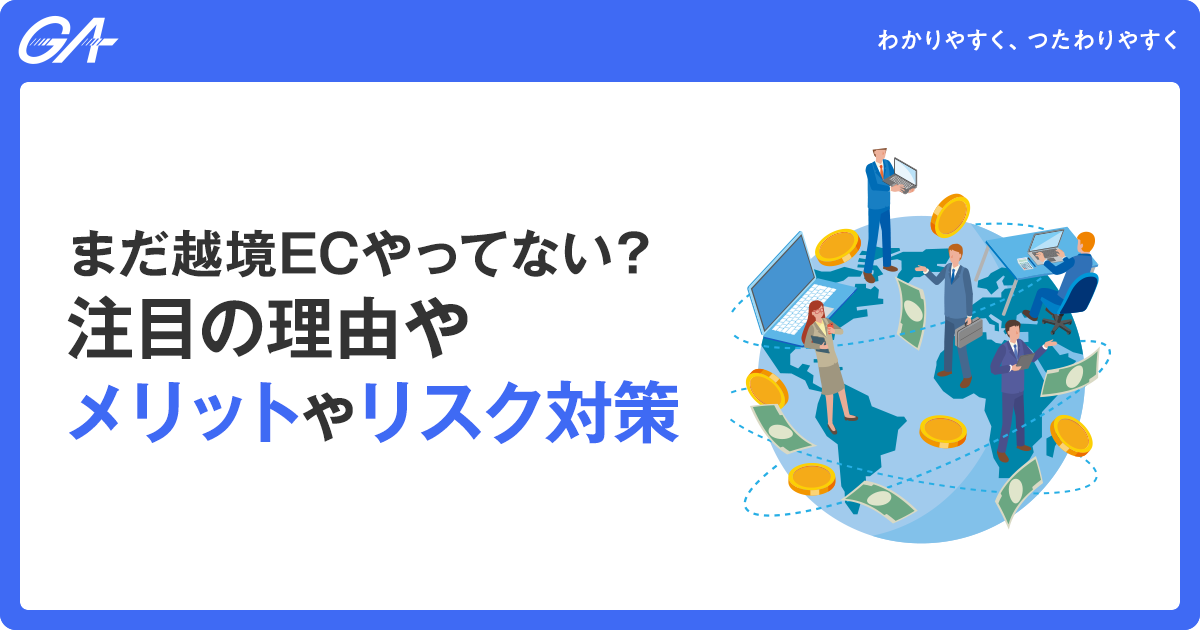日本国内ではインターネットを活用した「EC(電子商取引)」が広く普及し、消費者にとっても事業者にとっても重要な販売チャネルとなっています。その中で、高い注目を集めているのが「越境EC」です。聞き慣れない言葉かもしれませんが、海外への販路拡大を図る企業にとっては無視できないビジネス領域となっています。
この記事では、越境ECの定義や特徴、そして国内ECとの違いを具体的に見ていきましょう。
そもそも越境ECとは?

越境EC(Cross-Border E-Commerce)とは、日本の事業者がインターネットを通じて、海外の消費者や法人に対して商品やサービスを販売するビジネスモデルを指します。例えば、日本の化粧品メーカーが自社のECサイトを通じて中国の顧客に直接商品を販売したり、Amazonなどの国際的なモールを通じてアメリカや欧州に出品したりする形態が該当します。
つまり、「商圏が国境を越えている」ことが越境ECの最大の特徴です。物流・決済・通関などのインフラが整ってきたことで、以前よりも中小企業や個人事業者でも参入しやすくなってきています。
ポイントは、「海外販売=現地法人を設立する」ではないということ。あくまで日本国内に拠点を置いたまま、海外の顧客に向けて商品を届ける手段として、越境ECが注目されているのです。
国内ECとの決定的な違いとは(ユーザー・言語・商習慣・法制度)
越境ECは、国内ECと基本的な構造こそ似ていますが、運用面ではまったく異なる「難しさ」や「工夫」が求められます。その代表的な違いを見ていきましょう。
ユーザー属性の違い
- 国内ECの顧客は当然ながら日本人が中心です。一方、越境ECでは国ごとに購買傾向や文化背景が異なる多様なユーザーが対象になります。同じ化粧品でもアジアと欧米では成分のニーズや肌質の傾向が異なります。さらに、信頼性の判断軸やレビュー文化も違うため、単純な「日本でのヒット商品=海外でも売れる」という図式は成り立ちません。
言語の違い
商品説明やカスタマーサポートを現地の言語で対応することは、信頼性と購買率を大きく左右します。特に、翻訳の精度や文化的な文脈を踏まえたローカライズができていないと、「意味が通じない」「不安を感じる」といった離脱要因になりかねません。加えて、英語対応だけでなく、販売ターゲットに応じた中国語・韓国語・スペイン語など多言語対応が求められます。
商習慣の違い
日本では「送料無料」「即日配送」などが定番ですが、海外では配送期間が数週間に及ぶことも一般的であり、返品ルールや支払い方法も国によって大きく異なります。例えば、欧州ではクレジットカードよりもPayPalや銀行振込が好まれたり、中華圏ではWeChat PayやAlipayが必須であったりと、支払い手段の整備も重要な対応課題になります。
法制度・規制の違い
もっとも注意が必要なのが各国の法制度・通関ルールです。関税の有無、輸出入の禁止品目、原産地表示義務、消費税の取り扱いなど、法的な要件が国によって大きく異なります。対応を誤るとトラブルや返品、最悪の場合には法的責任を問われるリスクもあります。最新の情報収集と、信頼できる物流・通関パートナーの選定が不可欠です。
越境ECは「ネットさえあれば海外にも売れる」という簡単な話ではなく、言語・文化・商習慣・法制度の違いを前提にした入念な設計と運用が求められます。とはいえ、こうした違いを正しく理解し、現地にフィットした戦略を立てることで、越境ECは大きなビジネスチャンスへと変わるのです。
越境ECが注目されている理由
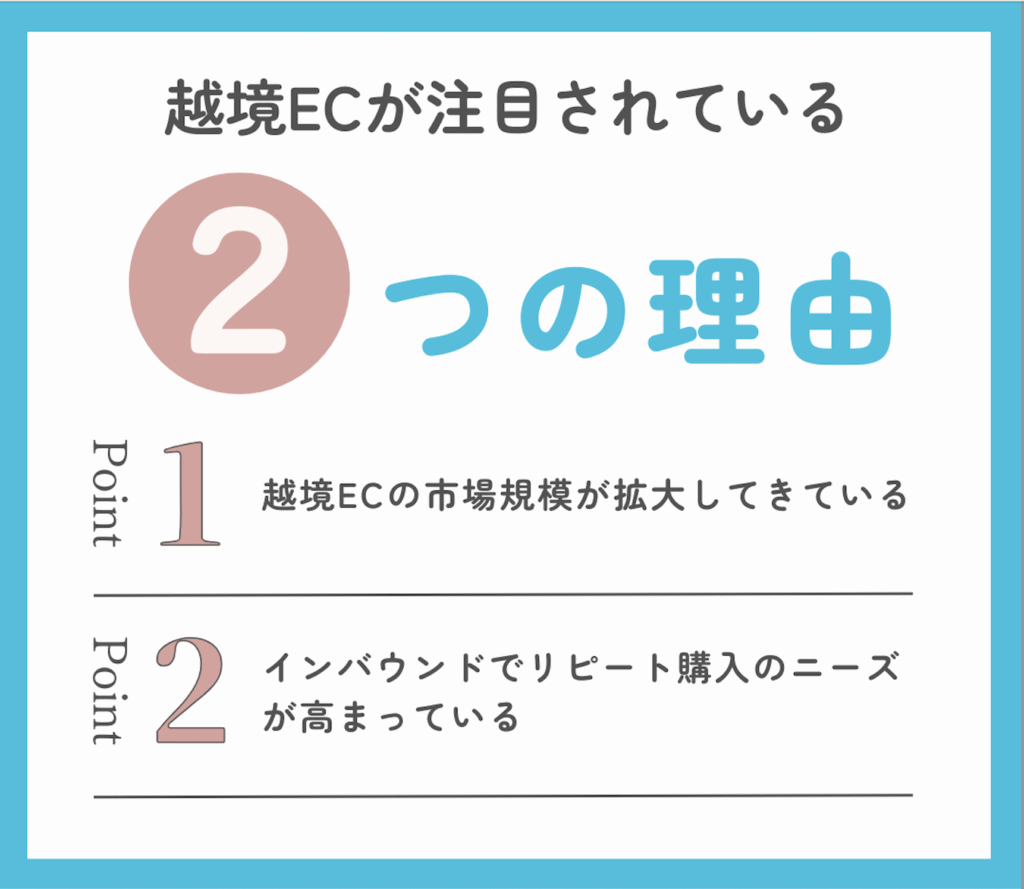
越境ECの市場規模が拡大してきている
近年、世界的に越境ECの市場規模は急速に拡大しています。国境を越えたオンラインショッピングの需要が高まり、各国の消費者が海外商品にアクセスしやすくなったことで、日本企業にとっても大きなビジネスチャンスとなっています。特にアジア圏では日本製品への信頼感が強く、「品質の高さ」「安心・安全」といったイメージが支持されており、日本発ブランドの人気は年々高まっています。中国やアメリカに向けた日本の越境EC市場は年々成長を続けており、今後もこの流れは加速すると見込まれています。
経済産業省のデータによると、米国の越境BtoC-EC(日本・中国)の総市場規模は2兆5,300億円となった。このうち、日本経由の市場規模は1兆4,798億円、中国経由の市場規模は1兆502億円であった。 中国の越境BtoC-EC(日本・米国)の総市場規模は5兆3,911億円となった。このうち、日本経由の市場規模は2兆4,301億円、米国経由の市場規模は2兆9,610億円であった。
経済産業省:令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書
インバウンドでリピート購入のニーズが高まっている
訪日外国人観光客による“インバウンド消費”も、越境EC注目の大きな要因です。観光時に購入した日本の商品を帰国後に再度購入したいというニーズが高く、それを実現する手段として越境ECが選ばれています。たとえば化粧品や健康食品、アニメグッズなどは「お土産で買ってよかったからもう一度欲しい」といったリピーター需要が多く、越境ECを通じてそのニーズに応えることで継続的な顧客獲得が可能です。コロナ禍を経て旅行が再開されたことで、今後さらにこの流れは活発になると予測されます。
日本企業の越境ECの具体例
多くの日本企業が、越境ECを新たな販路として積極的に活用しています。以下は代表的な事例です。
- 資生堂(SHISEIDO)
中国の「天猫国際」などのモール型ECに出店し、現地ニーズに合わせたスキンケア商品を展開。現地のSNSやインフルエンサーを活用したマーケティング戦略で大きな成功を収めています。 - 無印良品
越境ECサイトを通じてアジア・欧米市場に商品を販売。日本国内と同様に“シンプルで機能的”なブランドイメージが世界中で評価されています。 - 任天堂
ゲーム機やソフトの人気は世界的であり、公式ECやAmazonなどを通じて各国に製品を提供。アニメ・キャラクターグッズの関連商品も、越境ECを通じて多くの国で流通しています。 - 中小企業の例(例:地域特産品)
地方の中小企業も、地域の特産品や伝統工芸品を海外に向けて販売する事例が増えています。例を挙げると、和菓子や日本茶、漆器などが海外の富裕層や日本文化愛好者に支持され、越境ECを通じて新たな販路を開拓しています。
越境ECを始めることで得られる4つのメリット

日本国内だけでなく、海外市場に向けて商品を販売できる「越境EC」には、さまざまなメリットがあります。ここでは、越境ECを導入することで得られる4つの代表的な利点について解説します。
1.圧倒的な商圏拡大と需要
最大の魅力は、商圏が一気に世界へと広がることです。国内のEC市場が1億人の消費者に向けて展開されるのに対し、海外市場を含めれば数十億人規模の消費者にアプローチできます。
特にアジア諸国や欧米では、日本製品への関心が高く、需要のあるカテゴリー(アパレル、化粧品、日用品など)においては、現地の人々が積極的に日本ブランドを探し求めています。国内市場が成熟し、成長が鈍化する中で、海外市場の潜在力は非常に大きな魅力です。
2.「メイド・イン・ジャパン」ブランドの強み
日本製品は、品質の高さ・安全性・デザイン性などにおいて世界的に信頼されています。「メイド・イン・ジャパン」の表示そのものが、一種のブランドとして通用し、海外消費者の購入動機になります。
特に、中国・台湾・東南アジア圏の中間層や富裕層の間では、日本製の化粧品やベビー用品・健康食品に対する支持が厚く、他国製品よりも高価格でも選ばれるケースが多いのです。
ブランドを確立するには長年の努力が必要ですが、日本の中小企業でも、その「日本製」であるというだけで一定の信頼を得られるのは、越境ECの大きな利点です。
3.国内ECに比べて競合が少ない市場も
意外かもしれませんが、一部の海外市場では、まだ日本企業が本格参入していない領域も多く、国内ECと比べて競合が少ないケースもあります。たとえばASEAN諸国では、現地プレイヤーや中国ブランドの影響力はあるものの、日本の商品やサービスに特化したECサイトやマーケットプレイスの数は限られています。
このような市場では、ニッチな商品であっても競合がいないため、現地ユーザーにとって魅力的な選択肢となる可能性が高くなります。市場調査をしっかり行えば、国内では埋もれてしまった商品が、海外で高評価を得ることも十分あり得るのです。
4.出店のハードルが下がっている今がチャンス
かつて越境ECは、言語対応・決済手段・物流・関税などのハードルが高く、参入には相応のコストと知識が求められました。しかし、近年ではAmazon GlobalやShopee・Lazada〈ラザダ〉・天猫〈テンマオ〉(Tmall Global)など、海外向け販売を支援するプラットフォームが整備され、導入のハードルは大きく下がっています。
また、越境EC専門の物流サービスや翻訳ツール・カスタマーサポート代行なども充実しており、小規模事業者でも無理なくスタートできる環境が整ってきました。まさに今が、越境ECを始める「チャンス」と言えるタイミングなのです。
越境ECのリスクと対応策

越境ECには多くのチャンスがある一方で、国内ECとは異なるリスクも存在します。これらの課題にどう対応していくかが、ビジネスの成功を左右する重要なポイントです。以下では、主なリスクとその対応策について解説します。
言語、通貨、文化の壁と翻訳ツール、AIの活用
越境ECにおいてまず直面するのが、「言語の壁」です。サイト表示や商品説明はもちろん、カスタマーサポートも多言語対応が求められます。また、通貨の違いや文化的背景も、購入意欲に大きく影響します。
この課題に対しては、AI翻訳ツールや多言語対応のECプラットフォームの活用が有効です。たとえば「Wix」や「Shopify」などでは多言語翻訳アプリが利用可能で、商品説明を自動翻訳したり、通貨換算をリアルタイムで表示したりすることができます。文化面についても、現地の人気商品や消費習慣を事前にリサーチし、ローカライズ対応することでトラブルを回避できます。
物流、返品、関税のリアルな問題
越境ECでは、物流の遅延や送料の高騰、返品対応の煩雑さなど、国内配送とは比べものにならない課題が発生します。また、関税や輸入規制により、商品が相手国で受け取れないというケースもあります。
対応策としては、国際物流に強いフルフィルメントサービスを活用する方法が有効です。例えば、Amazon FBA(フルフィルメント by Amazon)やヤマトグローバルエクスプレス、Ship&coなどが、海外配送・関税手続き・追跡番号の発行までを一元化してくれます。また、返品ポリシーはあらかじめ多言語で明示し、トラブルの発生を未然に防ぎましょう。
各国の法制度・規制リスク
越境ECでは、出店先の国や地域の消費者保護法、知的財産権、食品・化粧品の輸出規制など、法制度への理解と対応が欠かせません。日本では合法な表現が、海外では違法とされる場合もあるため、注意が必要です。
このリスクには、JETRO(日本貿易振興機構)や各国の商工会議所、現地コンサルタントと連携することで情報を正確に把握することが肝要です。また、現地パートナー企業と提携することで、法制度面のサポートを得ながら、安全にビジネスを展開することが可能になります。
為替リスクと決済の多通貨対応
海外の顧客との取引では、為替変動による収益の目減りや損失も発生します。また、現地通貨での決済を求められるケースが多いため、多通貨決済対応も欠かせません。
こうした為替リスクには、決済プラットフォーム(例:PayPal・Stripe・Adyenなど)を通じてレートを固定したり、自動換算機能を活用したりすることで対応が可能です。加えて、売上金を外貨のまま保持し、為替の有利なタイミングで円に両替するなどのリスク分散策も有効です。
このように、越境ECにはさまざまな課題があるものの、テクノロジーや外部リソースをうまく活用することで、十分に乗り越えることができます。リスクを正しく理解し、現実的な対策を講じることで、グローバル市場への挑戦はより堅実で成果あるものになるでしょう。
チャネル選び(モール出店 vs 自社越境EC)
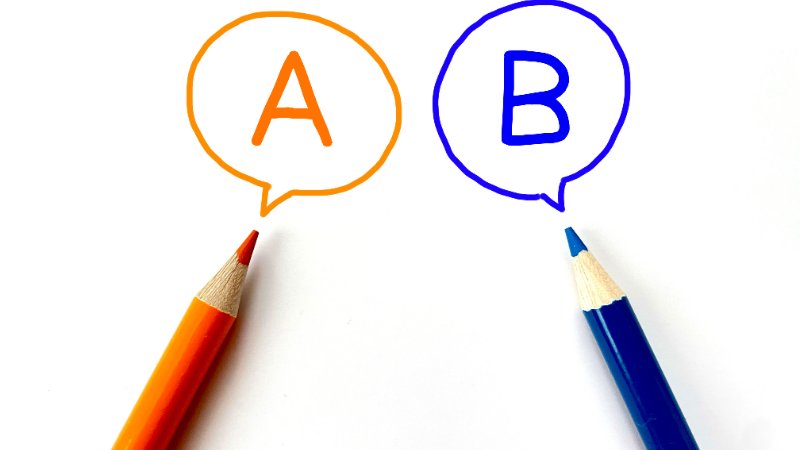
越境ECには大きく2つのチャネル選択肢があります。「モール出店」と「自社ECサイト運営」です。それぞれにメリットとデメリットがあります。
| 項目 | モール出店型越境EC | 自社越境ECサイト |
| 代表例 | Shopee(東南アジア)Tmall Global(中国)Amazon Global(北米) | 自社ドメインの多言語ECサイト 例:Shopify、Magento〈マジェント〉など |
| メリット | ・集客力が高く、すぐに販売開始可能 ・現地向け物流・決済が整備されている | ・ブランディングや顧客管理の自由度が高い ・リピーター戦略やCRMが可能 |
| デメリット | ・出店審査や手数料がかかる ・ブランドの表現自由度が低い | ・集客を自力で行う必要がある ・多言語 ・多通貨 ・法制度などに自社対応が必要 |
越境ECの初期フェーズでは、モールを利用して市場反応を見た上で、自社ECを強化する「ハイブリッド戦略」が有効です。
最低限必要な翻訳、通貨、物流体制
越境ECでは、「翻訳」「通貨」「物流」の3つが基礎インフラです。これらが整っていないと、ユーザー体験を損ねてしまい、購入に至らないケースが多発します。
- 翻訳:単なる自動翻訳ではなく、現地文化や表現に合わせた「ローカライズ翻訳」が理想です。AI翻訳+ネイティブチェックの併用が現実的です。
- 通貨:現地通貨での表示・決済は、ユーザーにとっての信頼性に直結します。PayPalやStripe、WorldFirstなど、多通貨決済に対応したサービスの導入が必須です。
- 物流:配送スピード・送料・追跡可能性は、海外ユーザーの購入判断に大きく影響します。現地倉庫の活用や、EMS・DHLなど実績のある越境配送サービスの利用が有効です。
SNS、インフルエンサーを活用した現地マーケ戦略
言語や文化の壁がある中で、「どのように現地ユーザーに認知してもらうか」は大きな課題です。ここで効果を発揮するのが、SNSとインフルエンサーを使ったマーケティングです。
- 現地SNSの選定
- 中国:WeChat・小紅書〈シャオホンシュー〉(RED)
- 東南アジア:Instagram・Facebook・TikTok
- 中国:WeChat・小紅書〈シャオホンシュー〉(RED)
- インフルエンサー起用
- 現地のマイクロインフルエンサーを活用することで、口コミ感覚で信頼を醸成できます。
- 案件は、海外向けインフルエンサーマーケット(例:AnyTag、Kolsquare(旧 Woomio))などを活用するとスムーズです。
- 現地のマイクロインフルエンサーを活用することで、口コミ感覚で信頼を醸成できます。
また、言語の壁はAIによって徐々に解消しつつあります。YouTubeやTikTok動画に自動翻訳字幕をつけたり、生成AIを活用して多言語対応のクリエイティブを制作するなど、新たなアプローチが可能です。
このように、越境ECはしっかりと段階を踏んだ準備があれば、スモールスタートでも成果を出すことができます。次の章では、実際に導入した企業の成功事例と活用ポイントをご紹介します。
主要な越境ECプラットフォームの比較

越境ECに取り組む際には、どのプラットフォームを選ぶかが非常に重要です。販売する商品やターゲット市場、ブランドの立ち位置によって、適したチャネルは異なります。ここでは、日本企業がよく利用する主要な越境ECプラットフォームと、それぞれの特徴を解説します。
| プラットフォーム名 | 対応エリア・市場 | 主な特徴 | 向いている企業 |
| Shopify | 世界175ヵ国以上 | 多言語・多通貨対応、デザイン・機能の自由度が高い。SNS連携・アプリ拡張が豊富。 | ブランド世界観を重視するD2C企業、中長期で育てたい企業 |
| Amazon Global | グローバル(特に北米・欧州) | 集客力が非常に高く、決済・物流インフラが整備済み。初心者でも始めやすい。 | 初めて越境ECに挑戦する企業、商品に競争力がある企業 |
| Tmall Global (天猫国際) | 中国本土 | 中国向け越境EC最大級。日本製品に信頼性あり。化粧品や健康食品が人気。 | 実績ある中堅〜大手企業、知名度の高いブランド |
| Shopee | 東南アジア・台湾 | モバイルユーザー中心。出店の手軽さとマーケティング支援が魅力。 | 小規模・スタートアップ、ASEAN進出を目指す企業 |
中小企業・D2Cブランドにおすすめの構成
中小企業やD2Cブランドが越境ECに取り組む場合、初期投資を抑えつつ、段階的に成長させていく戦略が有効です。まずはShopeeやAmazon Globalといった既存モールを活用して、販路とユーザーインサイトを獲得しましょう。これにより、現地での需要や競合状況を把握することができます。
その後、ブランド力が育ってきた段階で、Shopifyで自社越境ECサイトを構築し、ファンベースとの直接的な関係構築に移行するのが理想的です。モール出店と自社ECのハイブリッド運用を行うことで、チャネルリスクを分散しながら、ブランドの世界展開を持続的に進めていくことが可能になります。
FAQ

Q1:越境ECを始めるには、どこから手をつけるのが最もリスクが少ないですか?
A:まずはモール型の越境ECプラットフォームへの出店がおすすめです。
ShopifyやAmazon Global、Shopeeなどの既存プラットフォームは、集客力が高く、物流・決済のインフラも整っているため、初期費用や運用コストを抑えつつ越境ECをスタートできます。さらに、既存商品の中で「海外ニーズの高そうなもの」を選び、テスト販売することで、大きなリスクを取らずに市場の反応を確かめられます。
Q2:越境ECを始める際に、公的機関の支援は受けられますか?
A:はい、JETROや中小企業基盤整備機構などがさまざまな支援制度を用意しています。
例えば、JETROでは「海外展開支援」や「越境ECプラットフォーム利用補助」などを提供しており、実務支援・マッチング・補助金などを通じて、越境ECの立ち上げをサポートしてくれます。これらを活用することで、情報収集から実践までの負担を大きく軽減することができます。詳細は公式サイトで最新の支援メニューを確認しましょう。
(参考)
https://www.jetro.go.jp/jetro/activities/support/
https://www.jetro.go.jp/theme/export/js-links/40.html
まとめ
越境ECは、グローバル市場を相手にビジネスを拡大できる大きなチャンスです。特に中国やアメリカ、東南アジア市場は今後も拡大が見込まれ、参入のタイミングとしては今がチャンスといえるでしょう。モール出店と自社越境ECはそれぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の目的やリソースに合わせて適切な手法を選ぶことが重要です。
また、JETROなど公的支援も活用すれば、初期のハードルを下げながら取り組みを進めることができます。市場調査・戦略立案・販路開拓まで一貫して取り組み、継続的に改善を図ることで、越境ECの成功率は大きく高まります。