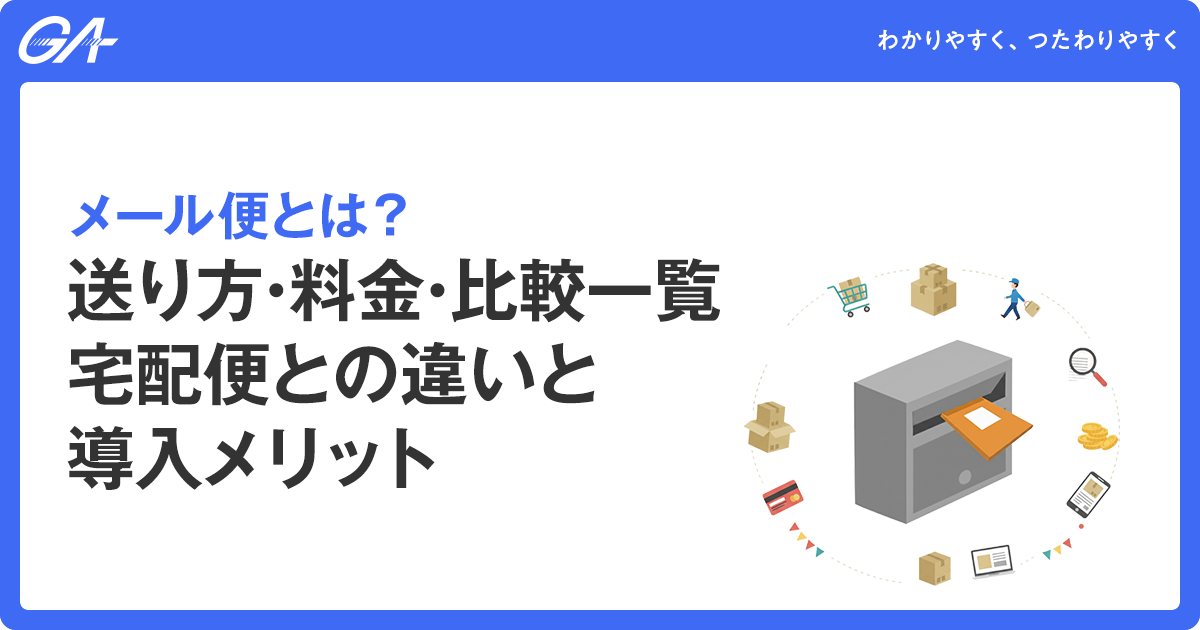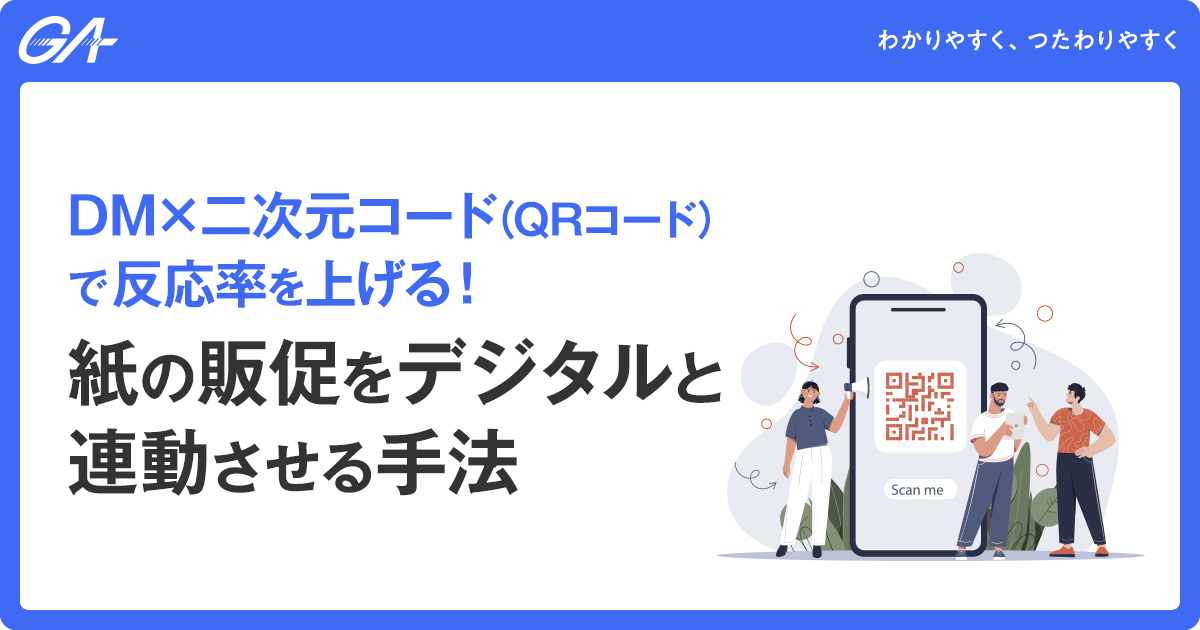EC事業者にとって配送コストは利益を左右する重要な要素です。メール便を適切に活用すれば、宅配便よりも安価に全国配送が可能になります。
本記事では、各社サービスの違いから選定方法、運用時の注意点まで実践的に解説します。
メール便とは

メール便とは、郵便物や小型の荷物を安価に全国へ配送できるサービスです。主にネットショップやEC事業者、個人の方が利用しています。薄くて軽い商品や書類、パンフレットなどの発送に適しており、ポストへの投函で受け取れます。そのため不在時でも受け取れ、配送コストが抑えられるのが魅力です。
サービスによって規格や利用条件に違いがありますが、いずれも「宅配便より低コスト」「コンパクトな荷物に特化」「一部のサービスは追跡も可能」といった特徴があります。EC運営や通販のコスト削減、顧客満足度アップに欠かせない選択肢です。
メール便と宅配便との違い
メール便と宅配便は「送れるもの」と「届け方」が大きく異なります。
メール便:ポスト投函を前提とした小型・薄型向けの低コスト配送
宅配便:対面受け渡しを基本に大きさや温度管理が必要な荷物まで幅広く対応する配送
また、到着までの時間と料金構造も違います。宅配便は地域やサービスによりますが、最短で翌日配送や午前指定など時間指定が可能で、速達性と確実性が高い分、料金は距離やサイズで変動し、メール便より高めになります。メール便は全国一律に近い低価格(概ね100〜600円程度)で送れる反面、配達に数日かかることがあり、時間指定ができません。
追跡や補償の面では宅配便が優位です。追跡の精度や補償制度、受領証の取得など証跡を残す仕組みが整っているため、紛失・破損時の対応がしやすく、クレーム対応負荷も小さくなります。メール便はサービスによって追跡や補償の有無が分かれるため、高額品や壊れやすいものには向きません。
メール便のメリット・デメリット
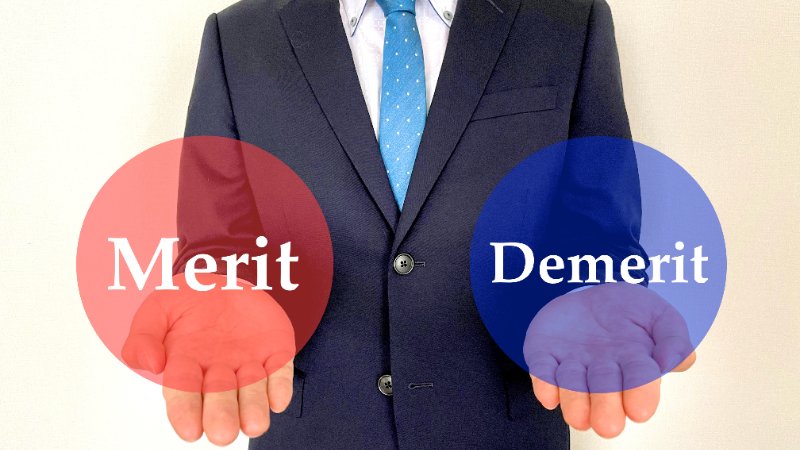
メリット
メール便を選ぶ最大の利点はやはりコストと利便性です。小型・薄型の商品であれば送料を大幅に抑えられるため、商品の価格競争力を維持しやすく、送料を一律にすることで購入のハードルを下げられます。さらにポスト投函を基本とするため、不在による再配達コストや受け取りの手間が減り、顧客満足度(CS)の向上にもつながります。
EC側の業務面でも、梱包が簡略化できることや専用ラベルやCSV一括印字による自動化が進めやすいことは大きな利点です。小ロットでの発送頻度が高い場合や、顧客が受取を簡便に済ませたい商品群には特に効果が出やすく、トータルの配送コスト最適化に貢献します。
デメリット
一方でメール便には制約もあります。まず補償が限定的、もしくは無いサービスが多く、破損や紛失が発生した際の対応コストやクレーム対応が発生しやすい点は事前に運用ルールを整備する必要があります。
サイズや厚さの制限が厳しいため、梱包方法で送れなくなるケースもあり、信書や高額品の送付が禁止されている場合が多いため注意が必要です。さらに配達日時の指定が原則できないなど、納期にシビアな顧客層には不向きです。
これらのデメリットは、補償の要・不要で商品を振り分ける、梱包基準を厳格にする、顧客向けに到着目安を明確に表示する、といった運用でかなり軽減できますが、事前の設計と社内ルール化が不可欠です。
メール便サービスの料金を比較
| サービス名 | 最大サイズ・厚さの目安 | 最大重量目安 | 料金目安(税込) | 追跡 | 補償 | 配達日数目安 | 土日配送(目安) | 主な用途 |
| クリックポスト | 34×25×3cm以内 | 1kg以内 | 185円 | ○ | × | 1〜3日程度 | 365 日配送 | 衣料品・サプリメント・CD/DVD・雑誌・スマホケース |
| ゆうパケット | 3辺合計60cm以内(長辺34cm以内、厚さ3cm以内)・厚さ3タイプあり | 1kg以内 | 厚さ1cm以内/250円、2cm以内/310円、3cm以内/360円 | ○ | × | 翌日〜翌々日 | 365日配送 | 衣料品・サプリメント・CD/DVD・雑誌・スマホケース |
| レターパック | 規定封筒サイズ(A4相当) | 4kg以内 | ライト430円/プラス600円 | ○ | ×(延着・紛失問合せ可) | 1〜3日程度 | 365日配送 | 信書もOK 書類・重めの小物 |
| ゆうメール | 縦34cm・横25cm・高さ3cm以内 | 1㎏以内 | 150g/180円、250g/215円、500g/310円、1kg/360円 | △バーコード | × | 1〜6日程度 | × | 雑誌・カタログ・CD/DVD・カレンダー |
| ネコポス | 三辺:60cm以内、長辺:34cm以内 (下限:縦23.0㎝以上 横11.5㎝以上) 厚さ3cmまで | 1kg以内 | 全国一律※条件に応じて設定 | ○ | ○ (3000円税込まで) | 翌日〜3日程度 | 365日配送 | 雑誌・カタログ |
| クロネコゆうパケット | 三辺:60cm以内、長辺:34cm以内 (下限:縦14㎝以上 横9㎝以上) 厚さ3cmまで | 1kg以内 | 厚みに応じた全国一律※条件に応じて設定 | △ | ○ (3000円税込まで) | 3〜1週間程度 | 365日配送 | 雑誌・カタログ・衣類・CD/DVD |
| 飛脚メール便 | 三辺合計70cm以内 | 1kg以内 | 300g以内/168円、600g以内/220円、1kg以内/325円 | × | × | 法人へのお届け:3〜4日程度 | 土曜は一部可能/日曜は地域差 | 雑誌・カタログ |
| 飛脚ゆうメール便 | 縦34cm・横25cm・高さ3cm以内 | 3kg以内 | 200g以内/115円、500g以内/168円、1kg以内/299円、2kg以内/330円、3kg以内/456円 | × | × | 法人へのお届け:3〜4日程度(一部地域除き)個人は5日程度 | 土曜は一部可能/日曜は地域差 | 雑誌・カタログ・CD/DVD |
※「追跡」「補償」「土日配送」はサービスごと・地域ごとに違いがあり、上表は一般的な傾向です。補償の有無はECでのクレーム対応に直結するため、特に重要です。補償が無い場合は梱包や代替対応(返金・再送)方針を事前に決めておきましょう。
日本郵便
日本郵便は個人・法人利用ともに対応するサービスが多く、商品の重量や厚さに応じた選択肢が豊富なのが特徴です。
クリックポスト
オンラインでラベルを作成・決済してポスト投函でき、薄手の物を安く送るときに向きます。信書は送付不可。ただし、内容物に関する無封の添え状・送り状は送付可能です。
ゆうパケット
追跡があり一定の厚さまで対応するため、補償が不要でコストを抑えつつ追跡を付けたいケースで使いやすいです。クリックポスト同様、内容物に関する無封の添え状・送り状は送付可能です。
レターパック
定額で重量のある小物まで対応できる点が強みで、書類や多少重めの商品を確実に送りたいときに便利です。
一方で、信書の扱いや補償範囲、地域による配達日数の差など運用上の注意点もあるため、発送量や顧客対応方針に合わせてサービスを選ぶ必要があります。大量発送の際は窓口差出しやオンラインラベルの一括作成などの運用フロー整備が有効です。
ゆうメール
1kgまでの荷物を送ることができます。※外装の見やすいところに「ゆうメール」またはこれに相当する文字を表示します。
あわせて読みたい!ゆうメールで「信書」は送れない!?プロが教える信書のコツを解説
ヤマト運輸
ヤマト運輸はクロネコDMサービスを終了し、ネコポスやクロネコゆうパケットといった薄型・小物向けのサービスを展開しています。
ネコポス
2025年11月10日から規格をリニューアル。長辺34cm以内、厚さ3cmまでの三辺(縦+横+厚さ)60cm以内、新しい取扱サイズに拡大します。クロネコメンバーズ会員になると受け取り場所を選択でき、置き配にも対応。最短翌日のお届けが可能です。
クロネコゆうパケット
ヤマト運輸が集荷した荷物を日本郵便の配送網で郵便受けに配達するサービスで、長辺34cm以内、厚さ3cmまでの三辺(縦+横+厚さ)60cm以内、重さ1kg以内で1cm、2cm、3cmの厚みに応じた全国一律料金が特徴です。※数量などの諸条件に応じてお客さまごとに設定あり、ネコポスと変わりません。
お届け日数がネコポスと違って3日〜1週間ほどを要し、郵便受けに投函します。
佐川急便
メール便系サービスは法人向けのDMや定期発送に強みがあり、飛脚メール便などは企業の大量発送に適した取り扱いフローを提供しています。
飛脚メール便
飛脚メール便は、三辺合計70cm以内・重量1kg以内の規格で、主に企業やEC事業者向けに設計されたサービスです。大量のDMやカタログ、会報誌などの一斉発送に強みがあります。全国エリアにわたる発送が可能で、発送フローも一括管理しやすく、法人の大量発送や定期的な案内物の配送に最適です。
飛脚ゆうメール
佐川急便に依頼した荷物のうち、ゆうメールの要件を満たすもの(縦34cm・横25cm・高さ3cm・重量3kg以内のお荷物)を日本郵便と連携して届けるサービスです。ゆうメールの特徴である全国一律の配送料や、郵便局を活用した安定した配送網を利用できるのが強みです。
※「追跡」「補償」「土日配送」はサービスごと・地域ごとに違いがあり、上表は一般的な傾向です。補償の有無はECでのクレーム対応に直結するため、特に重要です。補償が無い場合は梱包や代替対応(返金・再送)方針を事前に決めておきましょう。
※記載の料金は公表されている一般料金や目安であり、法人契約や発送ロット数、システム連携によって、実際の単価は大幅に引き下げられる場合があります。
メール便の送り方
梱包材・専用資材(推奨資材例、パッキング手順)
梱包は「商品保護」と「厚さ・重さの最適化」を両立させることが重要です。薄手で壊れにくい商品はクッション封筒や軽量のプチプチ封筒で十分ですが、本やプレート状の商品のように曲がりやすいものは段ボール芯や硬い紙で芯材を入れて補強します。液漏れや粉末類は個別密封し、外装が汚れないよう二重包装にすることが望ましいです。
厚さ制限のあるサービスを使う場合、詰め方次第で厚さが変わるため、梱包手順を現場で標準化し、実際にメジャーで測って基準を定めておくと余計な追加料金や差し戻しを防げます。大量出荷なら専用サイズの封筒や箱を予め定番化し、資材発注のロットを大きくすることでコストを下げられます。
参考に:EC事業者必見!梱包材の見直しで叶える経費削減とサステナビリティ
ラベル・宛名の書き方
宛名は読みやすさとバーコードの可読性が最優先です。手書きは少量なら問題ありませんが、EC運用ではプリンタで印字したラベルを使うほうが誤読やミスが減り、スピードも上がります。ラベルには送り先の郵便番号・住所・氏名・電話番号を明確に記載し、注文番号や顧客管理用の内部コードを追記しておくと問い合わせ対応が迅速になります。
バーコードや追跡番号はテープで隠したり歪ませないように配置し、ラベルの角がめくれないように四隅の一部を固定するのがコツです。大量発送向けには、配送会社指定のテンプレートを使ってCSVから一括印字するフローを整備すると業務効率が飛躍的に高まります。
ポスト投函と 集荷、どっち?
ポスト投函は手軽でコストも低く、夜間や人手が足りない時間帯でも発送できる点が魅力です。ただし、トラブル発生時に受領証のような証拠が残らない可能性があります。
その点、集荷はピッキング完了後にそのまま発送でき、受領書や配送伝票の控えが得られるため大量出荷や記録が必要な運用に向いています。ただし、集荷にすると集荷時間の制約や最低出荷数、場合によっては集荷料金が発生することがあるため、自社の出荷量と業務フローを照らし合わせて選びます。
最適な運用は「日常の標準ルート=ポスト投函で小ロット」「繁忙日や補償・追跡が重要なものは集荷による窓口差出票の取得」といった使い分けをすると良いでしょう。
メール便配送がおすすめの商品カテゴリ

メール便が最も効果を発揮するのは、「薄くて壊れにくく、返品リスクが比較的低い」商品群です。実際に、メール便配送でおすすめの商品カテゴリをご紹介します。
日用品/化粧品
日用品や化粧品は、重さの割にかさばらないものが多く、メール便と相性が良いカテゴリです。ただし液体物やエアゾールなどは包装や規制の観点で制約が出るため、容器の密閉、二重包装、吸収材の使用などの対策が必須です。また化粧品は返品や開封後のクレームにつながりやすいため、商品の状態確認や出荷前検品を強化すること、配送方法の選択基準を明文化しておくことがリスク低減につながります。定期購入でコストを抑えたい商品には、月次発送ルールを設けてメール便を標準運用に組み込むのも有効です。
衣類/ファッショングッズ
薄手の衣類、下着、靴下、アクセサリー等はメール便で送ることが可能です。折りたたみや圧縮でサイズを抑えられるため、送料を下げられる利点があります。ただしシワやにおい、型崩れには気を配る必要があり、適切な畳み方やシワ防止の芯材、香り除去の注意など梱包設計が重要です。返品率が高い商品カテゴリでもあるため、返品ポリシーを明確にしておくこと、そして検品基準を設けてから出荷することが、顧客満足度(CS)を維持するポイントです。
あわせて読みたい!顧客満足度(CS)を企業成長につなげる実践的アプローチ
本・書籍/カタログ
書籍や雑誌は、ゆうメールなど媒体に適したサービスで安く送れる代表的な商品です。紙製品は形状が安定しているため梱包の工夫で破損リスクをかなり下げられます。薄さや重量の規定に合う限りコストパフォーマンスは高く、複数冊をまとめて送ることで単価をさらに下げられる場合があります。発送時には曲がり防止のための芯材や二重包装を行い、ISBNや注文番号をラベルに明記しておくと流通上のトラブルや問い合わせ対応がスムーズになります。
メール便で送る際の注意点
メール便と宅配便は『送れるもの』と『届け方』が大きく異なります。メール便運用で重要なのは、禁止物・禁止行為の確認と顧客への明確な情報を提示することです。商品ページや購入フローで「この商品はメール便で送れます/送れません」を見やすく表示し、注文時の顧客期待を管理することで誤配送やクレームを防ぎます。また追跡の有無や補償の有無は購入前に明示し、万が一の紛失時の補償方針や代替対応(返金・再送の基準)を社内で決めておくことが必須です。さらに、現場側では重量・厚さの計測方法を統一し、梱包手順をマニュアル化しておくと運賃差や差戻しを減らせます。
メール便で送れるもの
薄手の衣類・書籍・CD・化粧品サンプル・クッション封筒に入るサイズのアクセサリーや小物類・販促物・カタログ類など
いずれも「壊れにくい」「厚さや重量が基準内である」ことが共通条件になります。商品に液体や粉末が含まれる場合は、規定に沿った密閉・緩衝措置を取れば送付可能な場合もありますので、個別に確認してください。
メール便で送れないもの
信書(契約書や請求書など)・高価な貴金属類・現金・危険物(可燃性・引火性のあるもの)・生き物や生鮮食品・配送会社の規約で明示的に禁止されている品目
また補償がないサービスで高額品を送ることは避けるべきで、代替の宅配便や保険付きサービスの利用を検討する必要があります。具体的な判断に迷う場合は、商品ごとに配送会社に確認を取ります。
まとめ
メール便は「薄くて小さく、壊れにくく、急ぎでない」商品に最適な低コスト配送手段です。本記事は、メール便の基礎から主要サービス比較、梱包・宛名の実務、配送リスクまで初心者向けに解説しました。メール便の活用はコスト削減だけでなく、顧客体験を高める点も大きな魅力です。貴社の通信販売やECサイト事業に取り入れてみてはいかがでしょうか。