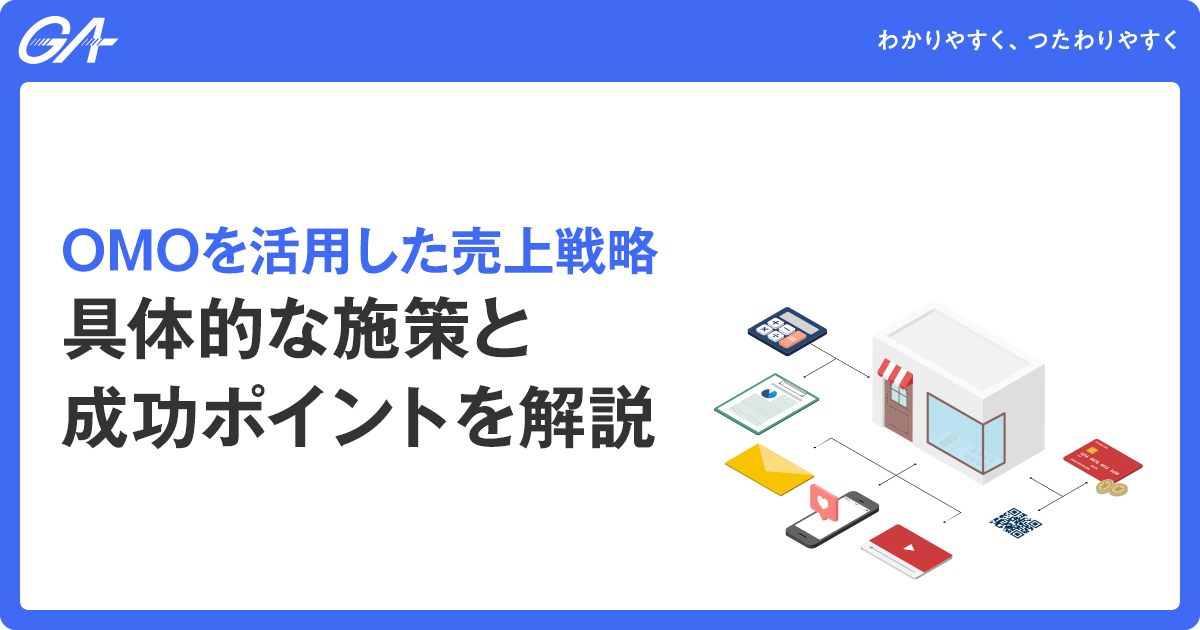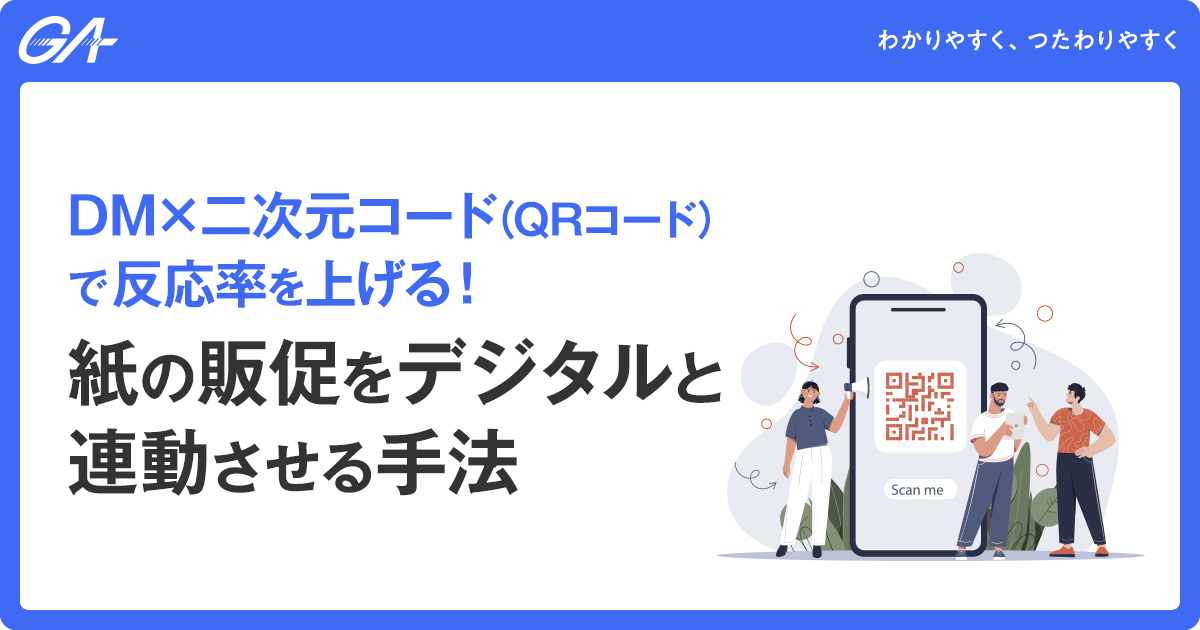近年、デジタルテクノロジーの急速な発展により、私たちの生活は大きく変化しています。デジタル化が加速する現代において、オンラインとオフラインの境界線はますます曖昧になっています。消費者は店舗で商品を見てからオンラインで購入したり、ECサイトで調べてから実店舗で買い物をしたりと、シームレスな購買体験を求めています。その代表的な概念が「OMO(Online Merges with Offline)」です。OMOは単なるマーケティング手法ではなく、顧客体験を根本から変革するビジネス戦略として、小売業界からサービス業まで幅広い分野で導入が進んでいます。
本コラムでは、OMOの本質を理解し、それを実現するための具体的な施策、そして成功のポイントついても詳しく解説します。
OMOとは

OMOとは「Online Merges with Offline」の略称で、オンラインとオフラインを融合させ、顧客にシームレスな購買体験を提供するマーケティング戦略です。
この概念は、中国の著名なベンチャーキャピタリストである李開復(リー・カイフー)氏によって2017年に提唱されました。OMOの核心にあるのは、オンラインとオフラインを区別せず、顧客にとって最適な体験を提供するという考え方です。
消費者が、ネットで商品を検索したり、レビューをチェックしたり、実店舗で商品に触れてみたり、購入場所を柔軟に選択できるようになることで、企業はより多くの購買機会を創出できます。OMOの最大の狙いは、オンラインとオフラインそれぞれの利点を最大化し、ユーザーの満足度やロイヤルティを高めることにあります。
O2Oとの違い
O2Oは「Online to Offline」の略で、その名の通り、「オンラインからオフラインへ」顧客を誘導することを主眼に置いた戦略です。
例えば、ウェブサイトやSNS上でクーポンを配布し、実店舗への来店を促進するようなケースで、最終的なゴールは店舗での購買という構造です。情報の流れも基本的には一方向で、オンラインからオフラインへという流れになります。
参考にしたい!O2Oマーケティングとは?特徴と最新事例を解説
一方、OMOではオンラインとオフラインの境界自体が存在しません。顧客はオンラインとオフラインを自由に行き来し、企業側もその行動に合わせてシームレスな体験を提供します。情報の流れも双方向で、実店舗での行動データがオンラインの推奨商品に反映されたり、オンラインでの閲覧履歴が店舗での接客に活用されたりします。
また、O2Oが主に集客や送客という「手段」にフォーカスしているのに対し、OMOは顧客体験全体の最適化という「目的」にフォーカスしています。どちらのチャネルで購入しても同じように便利で快適な体験ができることが重要であり、企業側の都合でチャネルを誘導するのではなく、顧客が自由に選択できる環境を整えることがOMOの本質といえるでしょう。
オムニチャネルとの違い
オムニチャネルは「すべてのチャネル」を意味する言葉で、実店舗・ECサイト・モバイルアプリ・SNS・電話など、あらゆる顧客接点を統合し、どこからでも同じように購買できる環境を提供する戦略です。在庫情報の統合、購買履歴の共有、ポイントの統一など、複数のチャネルをシームレスに連携させることに重点が置かれています。
オムニチャネルとOMOは非常に近い概念であり、実際には重なる部分も多くあります。しかし、微妙な違いがあります。オムニチャネルは「複数のチャネルを統合する」ことに焦点を当てており、それぞれのチャネルの存在を前提としています。つまり、実店舗もECサイトもアプリも存在するが、それらを連携させて顧客にとって便利にするという考え方です。
対してOMOでは、もはや「チャネル」という区分自体を意識しません。顧客にとっては、店舗で商品を手に取りながらスマートフォンで情報を見ることも、自宅でオンライン購入することも、すべてが一つの連続した購買体験の一部です。企業側も、オンラインとオフラインを別々のチャネルとして管理するのではなく、統合された一つのビジネスとして捉えます。
また、オムニチャネルが主にシステムやオペレーションの統合という「仕組み」に重点を置いているのに対し、OMOはより顧客視点での「体験価値」に重点を置いています。デジタル技術を活用して実店舗での体験を豊かにしたり、オンラインでしか得られない情報を店舗でも活用できるようにしたりと、単なるチャネル統合を超えた新しい価値創造を目指すのがOMOの特徴です。
参考に!オムニチャネルとは?メリットと導入の成功ポイントを事例で解説
OMOのメリット
OMO導入により、企業と顧客双方にさまざまなメリットがあります。
顧客体験の価値が上がる
OMOの最大のメリットは、顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)の向上です。OMOを実現することで、顧客は場所や時間を問わず自由に情報収集・購入ができます。例として、実店舗で商品を試した後、スマホで最適なサイズや色を探してオンラインで購入することも可能です。また、購入履歴や好みに基づくパーソナライズされたレコメンド、実店舗のリアルな体験とデジタルの便利さが融合し、顧客満足度が高まります。結果として、ブランドへの信頼度向上やリピート購入にもつながります。
LTVを最大化できる
顧客一人ひとりの顧客満足度を高めながら、効率的なマーケティング活動を実現できるのも大きなメリットです。つまり、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を最大化することができます。
OMO導入は、顧客の行動データや購入履歴を一元管理し、長期的な関係性を築くことが可能になります。CRM(顧客管理システム)やCDP(カスタマーデータプラットフォーム)を活用することで、個々の顧客に最適化したサービスを提供できます。
例)
・顧客の購買履歴や閲覧履歴を総合的に分析することで、次に購入する可能性が高い商品を予測し、適切なタイミングで提案
・購買頻度の低下や閲覧履歴の変化などから顧客の興味関心の変化を読み取り、特別なオファーや新商品の案内を送る施策を展開
OMOを実現するための具体的な施策

OMO戦略を実際に展開するには、具体的な施策の実施が必要です。ここでは代表的な施策を紹介します。
施策1:モバイルオーダー・店舗受け取り
スマホやECサイトで商品を注文し、実店舗で受け取る「BOPIS(Buy Online, Pick-up In Store)[店頭受け取りサービス]」は、コロナ禍を契機に急速に普及しました。特に飲食・小売業では、モバイルオーダーの利便性にオフラインのスピードや安心をプラスでき、ピックアップ専用カウンターを設置するだけで店舗運営効率もアップします。また、店舗での商品体験やカスタマイズサービスとのシナジーも期待できます。
BOPIS導入企業例⋯ユニクロ、スターバックス
施策2:CRM/CDPによるデータ活用
実店舗とECサイト、それぞれの顧客情報や購買履歴をCRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)システムやCDP(カスタマーデータプラットフォーム)で一元管理することで、顧客ごとに最適なキャンペーンやレコメンド配信、会員限定サービスを展開できます。例えば、店舗で購入した商品をもとにWEB広告を出し分けたり、SNSメッセージに個別対応するなど、よりパーソナライズドなマーケティングが実現します。
CDP導入企業例⋯パルコ、ナイキ
施策3:ポイントやクーポンの共通化
OMO施策の代表格が、実店舗・ECサイトどちらのチャネルでも「同じポイント」「同じクーポン」が使える仕組みです。これにより、「どこで買うのがお得か」を迷うことなく、好きなチャネルで購入ができる自由度が高まります。さらに、顧客のロイヤリティ向上や、継続的な来店・利用のきっかけ創出にも有効です。
ポイント共通化企業例⋯ユナイテッドアローズ、ベイクルーズ
施策4:デジタル会員証
紙やプラスチックの会員証からデジタル会員証への移行は、OMO時代のマストともいえます。スマートフォン一つで会員証の表示・ポイント付与・情報更新・限定クーポン取得が可能となり、前述した顧客の体験価値を大きく高めます。また、顔認証やQRコードを活用した新しい会員証も登場しており、非接触・衛生的なデータ連携も進んでいます。
施策5:チャットボット
店舗での顧客体験を向上させるために、デジタル技術を活用した施策も重要です。チャットボットは、顧客からの問い合わせに24時間365日対応でき、商品の在庫確認や店舗案内、よくある質問への回答などを自動化できます。オンラインだけでなく、店舗内にタブレット端末を設置することで、店員が忙しい時でも顧客が自分で情報を得られる環境を整えられます。
施策6:デジタルサイネージ
デジタルサイネージは、店舗内に設置された大型ディスプレイで、商品情報、プロモーション映像、コーディネート提案などを表示します。従来の紙のポスターと異なり、時間帯や季節、在庫状況に応じて表示内容を柔軟に変更できます。さらに、顧客の属性や行動に応じてコンテンツを出し分けるインタラクティブなデジタルサイネージも登場しています。
あわせて読みたい!デジタルサイネージ動画とは?メリットや活用場面・制作のコツを解説
OMO成功のポイント

OMO戦略を成功させるためには、単に技術を導入するだけでなく、包括的なアプローチが必要です。ここでは4つの重要なポイントを解説します。
ICT導入
OMOの実現には、クラウドベースの統合システムが欠かせません。実店舗とオンラインのデータをリアルタイムで同期できる基盤が、OMO戦略の骨組みとなります。
さらに、AI・機械学習技術により、顧客データから有益なインサイトを抽出し、パーソナライズされたレコメンデーションを実現できます。IoTデバイスを活用した在庫管理やビーコンによる店舗ナビゲーションなども、リアル店舗をデジタル化する重要な技術です。
同時に、顧客データを扱う以上、強固なセキュリティ体制の構築とプライバシー保護への対応も必須となります。
販売チャネルのマルチ化
OMOを実現するには、実店舗とECサイトだけでなく、複数のチャネルを統合的に運用することが重要です。
モバイルアプリやSNS(Instagram Shopping、Facebook Shopsなど)は、顧客との継続的な接点になります。ポップアップストア、ライブコマース、オンライン接客など、新しいチャネルも活用できます。
重要なのは、顧客がどのチャネルを選択しても、一貫した体験を提供することです。
顧客体験を高める店舗環境
OMO時代の実店舗は、単なる販売の場から「体験の提供場所」へと進化する必要があります。オンラインでは実現できない価値を提供することが、差別化につながります。
商品を手に取り、試着・試用できる五感に訴える体験、専門知識を持つスタッフによるコンサルティング、ワークショップなどのイベント開催が効果的です。
さらに、AR試着やVR体験、タッチパネルでのカスタマイズなど、デジタル技術と実店舗を融合させた体験は、顧客の関心を大きく引きます。
施策知識やスキルをもった人材の育成
OMO戦略の成功は、最終的に「人材」にかかっています。店舗スタッフには、タブレットやPOSシステムを使いこなし、顧客データを活用した接客ができるデジタルリテラシーが求められます。
また、データ分析スキルを持つ人材や、部門間の壁を越えて協力できるコミュニケーション能力も重要です。テクノロジーや消費者行動は常に変化するため、継続的な学習姿勢も不可欠です。定期的な研修プログラムの実施、外部セミナーへの参加支援、社内での知識共有の仕組み作りなど、組織的な取り組みが必要です。
まとめ
OMO(Online Merges with Offline)は、オンラインとオフラインの境界線をなくし、顧客にシームレスな体験を提供する戦略です。O2Oやオムニチャネルと違い、「チャネルという概念そのものをなくす」ことが特徴です。
OMO導入のメリットとして、顧客体験が大幅に向上し、顧客生涯価値(LTV)の最大化が実現できます。さらに、成功のポイントは、ICT導入による基盤整備、複数チャネルの統合運用、体験価値の提供、そして人材育成の4点に集約されます。特に、デジタルとリアルを融合させた顧客体験の設計と、その実現を支える人材の確保が最も重要です。
OMO戦略は一朝一夕には成しえませんが、これからの小売業やサービス業にとって避けては通れないテーマです。今から段階的に取り組むことが、中長期的な企業競争力を左右します。顧客視点での改善を継続することで、OMOは安定した売上とロイヤル顧客の獲得につながります。