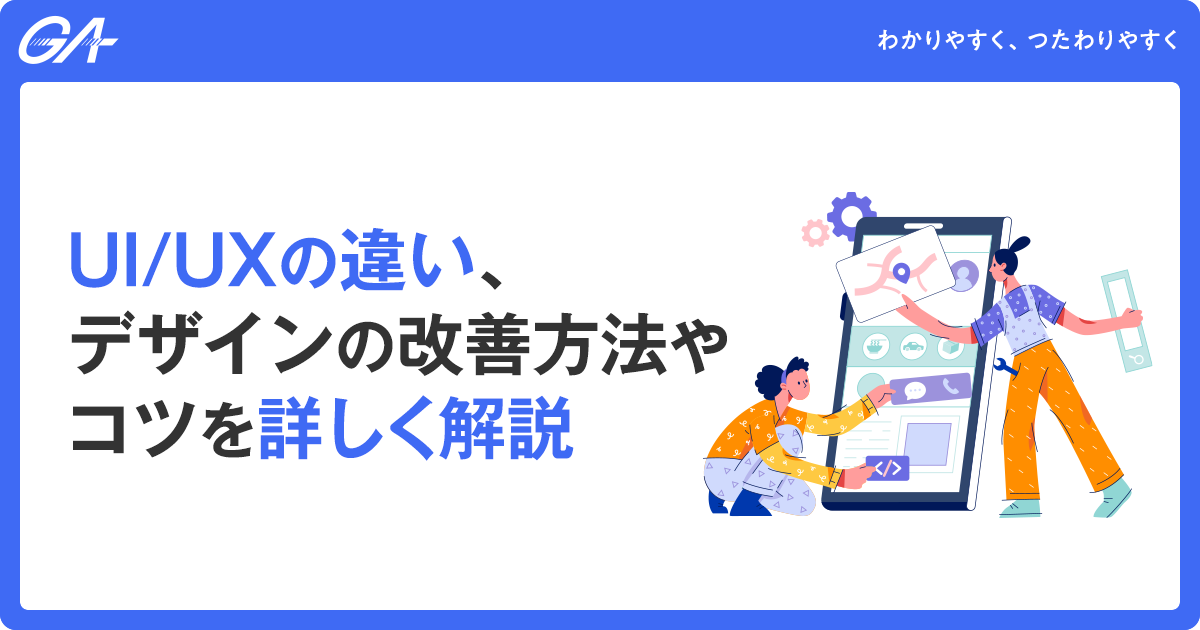ECサイトの成果を左右するのは、商品だけではありません。使いやすく、わかりやすく、心地よいと感じられる「UI/UX」こそが、売上やリピート率を左右するカギとなります。しかし、ただ見た目を整えるだけでは意味がなく、ユーザー目線に立った設計が不可欠です。ここでは、優れたUI/UXをデザインするために押さえておきたいポイントを解説します。
UIとUXって何が違うの?

ECサイト運用において、頻繁に登場する「UI」と「UX」という言葉。どちらも顧客満足やCVR改善に直結する重要な概念ですが、混同されやすく、本質を正確に理解できていないケースも少なくありません。ここでは、UIとUXの違いと関係性について、EC担当者の視点から具体的に解説していきます。
UI=ユーザーインターフェース|操作画面そのもの
UI(User Interface)とは、ユーザーとサービスの接点、つまり「画面上で直接目に見える部分」を指します。ECサイトでいえば、商品一覧ページのレイアウト、カートボタンの配置、グローバルナビゲーションの構成、検索窓の位置やデザインなどが該当します。
例えば、商品画像が統一されていて見やすかったり、サイズやカラーの選択肢が迷わず操作できたりすることで、ユーザーは「使いやすい」と感じます。この「見た目の整合性」や「情報設計のわかりやすさ」が、UIの良し悪しを左右します。
しかし、UIはあくまで“入り口”。ボタンが大きくて押しやすい、文字が読みやすい、カテゴリが明確に分かれている──といった目に見える部分を整えることで、ユーザーが快適にサイトを「操作」できる状態を作ります。
UX=ユーザーエクスペリエンス|使って感じる「体験」
一方のUX(User Experience)は、ユーザーがサービスを通じて得る「体験」全体を指します。UIのように具体的なパーツではなく、感覚や印象、満足度といった“目に見えない価値”が中心です。
次のような場面がUXに大きく影響します。
- 商品ページに必要な情報が揃っていて、購入の意思決定がスムーズだった
- サイト表示が速く、ストレスを感じずに閲覧できた
- 欲しい商品を簡単に検索できた
- カートから購入完了までが短く、途中で離脱しなかった
こうした一連の流れにおける「使いやすさ」や「心地よさ」が、UXの中心です。仮にUIが洗練されていても、「商品がなかなか見つからない」「ログインがうまくいかない」といった不便さがあれば、UXは損なわれます。
つまり、UIが良くてもUXが悪ければ、ユーザーは「使いにくいサイト」と感じて離脱してしまう可能性が高くなります。
UIとUXはどう関係している?
UIとUXは別物のように思われがちですが、完全に切り離された概念ではありません。
むしろ、UIはUXという「家」の一部である「家具」のようなものと考えるとわかりやすいでしょう。例えば、センスのいい家具があり、その配置が整っていれば、家の居心地(UX)はよく感じられるはずです。しかし、いくら家具のデザインが洗練されていても、間取りが悪かったり、導線が不便だったりすると、家全体の快適さ(UX)は損なわれてしまいます。
要は、UIだけを改善しても、UXが保証されるわけではないのです。
ECサイトでのUXを高めるには、以下のような総合的な設計が求められます。
- 購入までの導線設計(ファネルの短縮)
- カスタマーサポートへの導線やFAQの整備
- サイトスピードやモバイル対応
- 顧客ニーズに沿ったコンテンツ配置やレコメンド設計
これらすべてが組み合わさって、最終的に「快適だった」「また使いたい」と思える体験(UX)へとつながります。したがって、UI改善はUX改善の第一歩であり、全体設計の中でUIをどう配置するかがUXの成功のカギを握っています。
ECサイトで「買い物途中の離脱」が起きる原因とは?

「UIが悪い」と言われるケースの具体例
ユーザーがECサイトを訪れ、商品に興味を持っても、実際に購入に至らないケースは少なくありません。その大きな理由のひとつが「UI(ユーザーインターフェース)の不備」です。ここでは、UIが原因で離脱が起きやすい典型的な例をいくつか紹介します。
ボタンが見つからない/目立たない
ユーザーが次に進むために必要な「カートに入れる」や「購入手続きへ進む」などのボタンがページ上で見つけにくい、あるいは他の要素に埋もれて目立っていない場合、ユーザーは一瞬でストレスを感じます。特に、アクションの導線が曖昧だと、「ここでいいのかな?」という不安が生まれ、そのまま離脱する可能性が高まります。
商品画像が小さい・拡大できない
ECにおける「写真」は、実店舗での「現物確認」に相当する非常に重要な要素です。にもかかわらず、商品の写真が小さく、拡大機能もない場合、ユーザーは商品の質感やディテールを想像しにくくなります。とくにファッションや家具・雑貨など、見た目が購入判断に直結するカテゴリでは致命的です。
スマホでの表示が崩れている
スマートフォンユーザーが大多数を占める今、モバイル対応の品質はユーザー体験に直結します。PC用のデザインをそのまま流用して文字が読みにくかったり、ボタンが押しづらかったりすると、購入どころかページ閲覧すら難しくなります。リンクの押し間違いや、スクロールしすぎによる迷子状態など、些細な不便が離脱のトリガーとなります。
UI以外にもある!UX視点での離脱要因
UI(ユーザーインターフェース)だけでなく、UX(ユーザー体験)の観点からも離脱要因を見直すことが重要です。ユーザーが途中で購入をあきらめる背景には、UIだけでは測れない心理的・機能的なストレスが潜んでいます。
配送料や決済方法の提示が遅い
購入直前で「思っていたより送料が高い」と判明したり、希望する決済方法が使えないことがわかると、ユーザーは一気に離脱してしまいます。これらの情報は、商品詳細ページやカート画面の前に明示するのが理想です。
商品情報が不十分・比較できない
サイズ・素材・スペックなどの情報が不足していたり、類似商品との比較がしづらいと、ユーザーは不安を感じて離脱します。特に高単価商品では、信頼性や納得感を与える情報設計が欠かせません。
会員登録の手間が面倒
購入前に必須となる会員登録が長すぎたり、入力項目が多すぎると、購入意欲があっても途中で離脱されるケースが多くなります。ゲスト購入の導入や、SNSアカウント連携などによる簡略化が有効です。
データで見る離脱のサイン|注目すべきKPIとは
UX上の課題は、定性的なユーザーの声だけでなく、定量データからも読み取ることができます。以下のKPIを継続的に観測することで、UX改善のヒントが得られます。
カート投入率(CVRの一歩手前)
訪問ユーザーが商品をカートに入れる率は、CVR(コンバージョン率)よりも前の段階での興味関心を示す重要な指標です。この数値が低い場合、商品情報の不足や、価格・在庫・送料の不明確さが原因かもしれません。
離脱率(LP・商品ページ・購入フロー)
ページ単位での離脱率を把握することで、どの時点でユーザーが離れているのかが可視化されます。特に商品ページやカートステップでの急激な離脱が見られる場合は、説明の分かりにくさやフリクション(心理的負荷)が疑われます。
スクロール到達率(ヒートマップで可視化)
ヒートマップツールを活用すれば、ユーザーがどこまでスクロールしたか、どこで興味を失ったかが明確になります。重要な情報が下部に偏っている場合、レイアウトの再設計や情報の再配置を検討しましょう。
UI/UX改善の進め方|初心者でもできる3ステップ

STEP1|Googleアナリティクス・ヒートマップで現状把握
ユーザー行動を「見える化」して、どこで詰まっているかを特定する
まずは、Googleアナリティクスやヒートマップを活用して、ユーザーがどのページで離脱しているのか、どこまでスクロールしているのかなど、実際の行動を「見える化」しましょう。ファネル分析やクリック率、スクロール率などのデータを通じて、課題となっているページや要素を把握することが改善の第一歩です。
STEP2|ボトルネックを1つに絞って改善施策を試す
例:ファーストビューの変更、商品画像の最適化、ボタン配置の修正
すべてを一度に改善しようとすると、何が効果的だったのかが見えなくなります。まずは最も影響が大きそうなボトルネックを1つに絞り込み、ピンポイントで改善施策を実行します。たとえば、「ファーストビューで商品特徴が伝わっていない」「カートボタンが目立たない」といった問題に対して、レイアウトやデザインの修正を行いましょう。
STEP3|改善前後でKPIを比較して判断する
離脱率/CVR/ページ滞在時間/スクロール率などで効果検証
改善施策を行ったあとは、必ず数値で効果を検証します。改善前と後で、CVR(コンバージョン率)、離脱率、ページ滞在時間、スクロール率などのKPIを比較し、どのような変化があったのかを確認しましょう。小さな改善でも、ユーザー体験の積み重ねによってUI/UX全体の底上げにつながります。
優れたUI / UXの4つのコツ

優れたUI/UXを設計するには、単に見た目を整えるだけでは不十分です。ユーザーが直感的に使いやすいと感じる導線設計や、行動を自然に促す仕掛けを設けることが重要です。そのためには、いくつかの基本原則を押さえた上で、ユーザーの視点に立ったデザイン思考が求められます。
1.ユーザーの目的を最短距離で達成させる設計
UI/UXの基本は、ユーザーが迷わず目的を果たせるように設計することです。例えば、ECサイトであれば「商品を探してカートに入れる」「情報を確認して購入に進む」といった一連の流れがスムーズに行えることが求められます。ナビゲーションやボタンの配置、視線誘導の工夫を通じて、ユーザーが思考停止せずに操作できる導線をつくりましょう。
2.UI(インターフェース)は「直感的な操作性」を重視
文字情報だけでなく、視覚的な要素を使って操作を直感的に伝える工夫も重要です。ボタンの色や大きさ、アニメーション、アイコンなどは、ユーザーの視線や行動をナビゲートする手段として有効です。また、余白やコントラストの使い方次第で、ページ全体の印象や読みやすさも大きく変わります。
3.UX(体験価値)は「ストレスの少なさ」で差がつく
ユーザーが安心して操作できるようにするには、入力やクリックに対する即時のフィードバックも欠かせません。フォーム入力後の確認メッセージやエラー時の具体的な説明、ボタンを押したあとの遷移表示など、小さなリアクションがUX向上に大きく貢献します。ユーザーに「今どの状態にいるか」「次に何が起こるか」を丁寧に示すことが大切です。
4.デザインの一貫性とシンプルさを保つ
さらに、ページ全体を通して一貫したデザインルールを守ることで、ユーザーは迷いにくくなります。フォントや色、ボタンの形状などが統一されていることで、自然と使い方を理解しやすくなり、初めて訪れたユーザーにも安心感を与えることができます。また、情報を詰め込みすぎず、目的ごとに必要な要素を絞り込む「引き算のデザイン」もポイントです。
まとめ
優れたUI/UXのデザインには、ユーザーの視点に立った情報設計と、課題を発見・改善するプロセスが欠かせません。見た目の美しさだけでなく、迷いなく操作できる動線設計や、感情的な満足感を提供することが求められます。継続的な改善こそが、ECサイトの成長につながるUI/UXの本質です。
私たち株式会社ゼネラルアサヒは、EC事業社様100社以上のお取引実績があります。お客様の課題を丁寧にヒアリングし、さまざまなご提案をさせていただきます。ECサイトのお悩みはどんなことでもご相談ください。