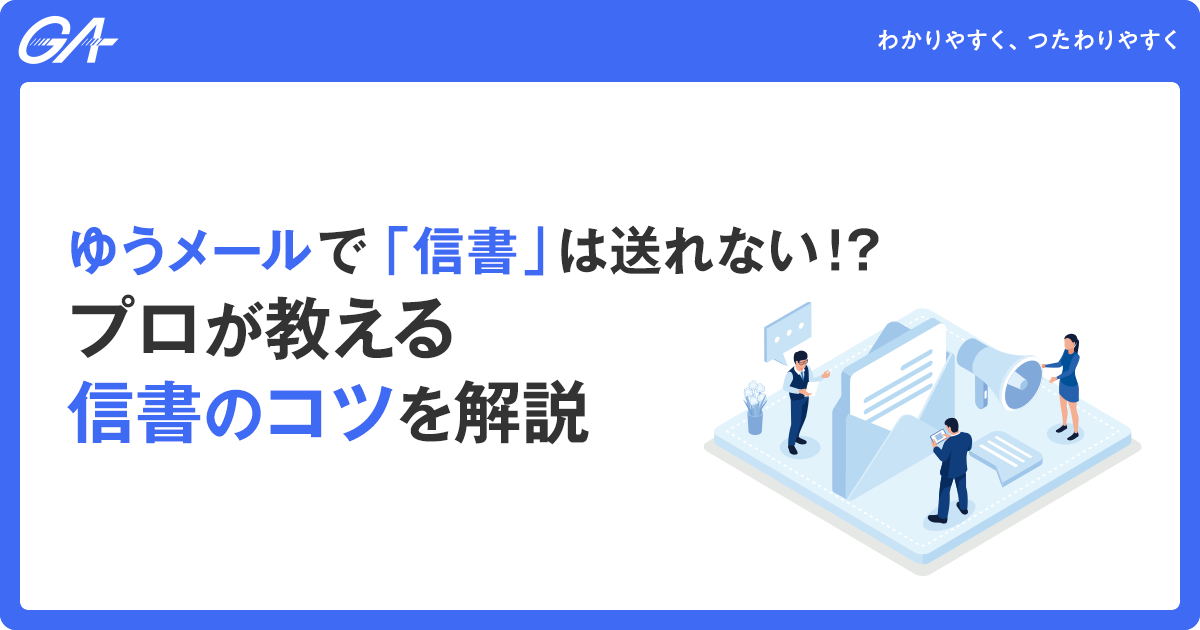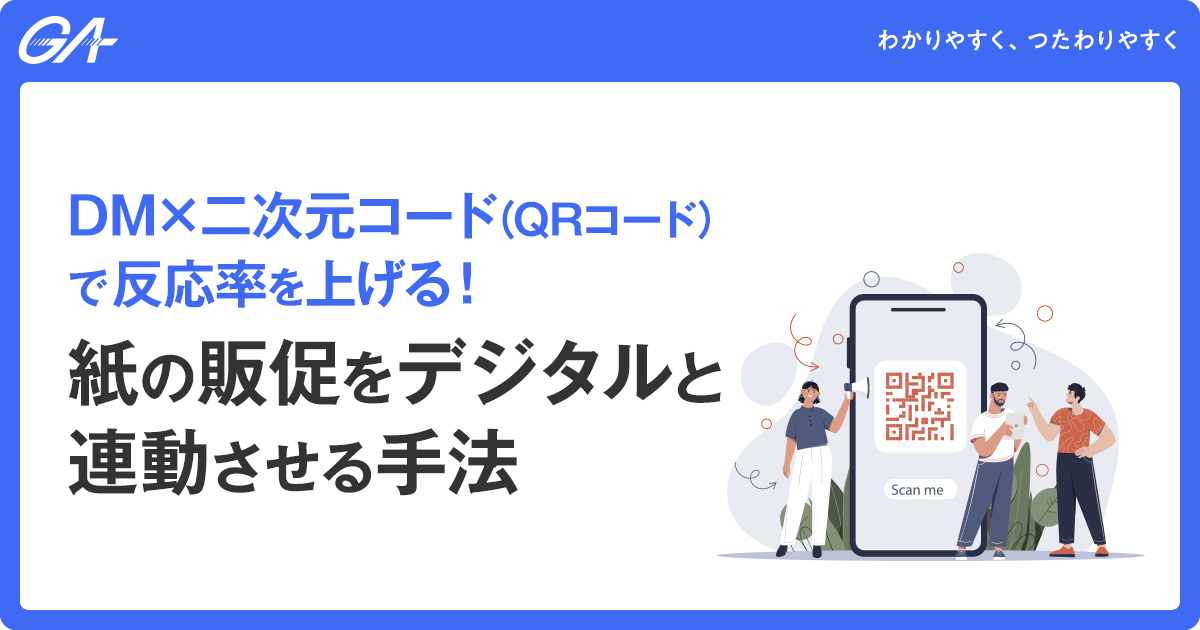ゆうメールと信書の違いを知らずに発送すると、差し止めやトラブルにつながる可能性があります。特にDM(ダイレクトメール)や挨拶文は、文言によって信書と判断されるケースが少なくありません。
DMやカタログをゆうメールで送る企業は多いですが、信書は法律で厳格に定義されているため正しい知識を持つことが重要です。本記事では、信書の定義やゆうメールとの違いを理解した上で、注意すべき文言や対応策をわかりやすく解説します。
信書とは(法律的定義と目的)
まず理解しておきたいのが、「信書」の定義です。
郵便法および信書便法において、信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」と定められています。
参照:総務省の「信書のガイドライン」
この定義には大きく3つの要素があります。
- 特定の受取人:誰宛てかが明確に特定されていること(「お客様各位」ではなく、「○○様」など)。
- 意思表示または事実通知:差出人の考えや依頼、感謝、取引内容の通知などが含まれること。
- 文書であること:手紙や書面といった「形ある文章」であること。
つまり、「特定の方にあてた手紙や通知文」はすべて信書にあたります。例えば、契約内容の確認書、請求書、受領書、個別のお礼状などが典型的な信書です。
信書の取り扱いは法律で厳格に制限されています。その目的は、通信の秘密を保護し、文書の安全かつ確実な送達を担保することにあります。したがって、信書を送付できるのは「郵便局(日本郵便)」や、国から認可を受けた信書便事業者に限られているのです。
ゆうメール vs 信書:なぜ送れないのか?

ここで疑問になるのが、「なぜゆうメールでは信書を送れないのか?」という点です。
ゆうメールが対象としているもの
ゆうメールは、日本郵便が提供するサービスのひとつで、冊子や印刷物、カタログ、パンフレット、商品サンプルなど、不特定多数に向けた広告物の送付を主な目的としています。料金が安く設定されているのも、「大量に、同じ内容のものをまとめて送る」用途を想定しているからです。
信書送付におけるゆうメールの法的制限
一方で、信書は「特定の相手に向けた意思表示や通知文」であるため、性質がまったく異なります。ゆうメールは広告用としての利用を前提にしているため、信書を同封することは郵便法違反になります。もし誤って信書を入れてしまった場合、郵便局で差し止められるだけでなく、悪質な場合は処罰の対象になる可能性もあります。
信書を送れる他のサービス
では、信書を送りたい場合はどうすれば良いのでしょうか。日本郵便では、以下のサービスを利用することが認められています。
- 普通郵便(定形・定形外):最も一般的な信書の送付方法。
- レターパック(ライト/プラス):全国一律料金で追跡機能つき。ビジネス文書の送付にも便利。
- スマートレター:180円の専用封筒で、簡易的に信書を送れる低価格サービス。
このように、送付物の性質とサービスの目的を正しく理解して選ぶことが重要です。コストだけを重視してゆうメールを利用しようとすると、法律違反につながりかねません。
ゆうメールで「信書」と判定される注意表現

ゆうメールは広告物やサンプルを送るのに便利ですが、ちょっとした文言の書き方次第で「これは信書にあたります」と判断されてしまうことがあります。特にDM(ダイレクトメール)を送る際には注意が必要です。ここでは、実際に信書とみなされやすい表現を整理します。
受取人を特定する表現
- 「〇〇様」や「△△ご担当者様」など、特定の個人・企業宛を明示する言葉。
- 「会員の皆様」「ご購読者様」など、一見不特定多数に見えても、条件を限定しているため信書とみなされやすい。
👉 ポイントは、「特定の誰かに向けたものではなく、不特定多数向けの案内である」ことを文面で示すことです。
サービスや商品の利用を通知する表現
- 「このたびはご購入ありがとうございます」
- 「先日はご利用いただき…」
- 「ご契約更新のお知らせ」
これらは差出人から受取人に対して「事実を通知」していると解釈され、信書に該当する可能性が高いです。
送付状や挨拶文の扱い
- 「ご挨拶申し上げます」や「お願い申し上げます」といった手紙風の文章。
- 「お世話になっております」「今後ともよろしくお願いいたします」など、取引関係を前提とした表現。
これらは単なる広告の添え状ではなく、「意思表示」と判断されることがあります。
「受取人を特定する表現」のビフォー・アフター例を対比表
| NG表現(信書とみなされやすい) | OK表現(ゆうメールで安全) | ポイント |
| 〇〇様 日頃より当店をご利用いただきありがとうございます。新商品をご案内いたします。 | お客様各位 平素よりご愛顧を賜り、ありがとうございます。新商品のご案内を同封いたしましたのでご覧ください。 | 宛先を特定せず、不特定多数向けの案内に変更。利用実績に言及せず抽象的表現に置き換える。 |
| △△ご担当者様 先日はサービスをご利用いただきありがとうございました。 | みなさまへ 平素よりご愛顧を賜り、ありがとうございます。サービスに関するお知らせを同封いたしました。 | 個人名を避け、全体向けの表現に変更。 |
| 会員の皆様 ご購入ありがとうございました。 | ご案内 日頃よりご支援いただきありがとうございます。新商品のお知らせを同封しました。 | 条件や購入履歴に基づく呼称を避け、一般的な呼称に変更。 |
| ご購読者様 前回お届けした商品はいかがでしたか? | お知らせ この度、新商品のご案内を同封いたしました。 | 「購入・利用実績」を前提にしない表現に変更。 |
このように、ちょっとした文言の違いで信書とみなされてしまうリスクがあるため、DMの文面を作成する際には細心の注意が必要です。
信書とみなされないための具体的対応策
「これは信書ではない」と説明できるように、文面の工夫をすることが非常に重要です。ここでは、DMやゆうメールで広告を送る際に使える具体的な対応策を紹介します。
宛名は「各位」や「ご案内先」など一般表現に
特定の人を名指しするような「○○様」「△△ご担当者様」は信書と判断されやすい表現です。代わりに、「ご担当者各位」「お客様各位」「ご案内先」といった、不特定多数を対象とする表現に切り替えましょう。
利用や購入を示す文言は避ける
「ご購入ありがとうございます」「ご利用いただき〜」といった表現は事実通知に該当し、信書扱いになるリスクがあります。そこで代替表現として、「ご愛顧いただき」「日頃のご支援に感謝申し上げます」「お知らせ」など、受取人の利用実績を前提としない言葉を選ぶのが安全です。
送付状はあくまで「添え状」に
送付物に同封する文書は、長々とした手紙調ではなく、「カタログを同封いたしましたのでご高覧ください」程度の簡潔な添え状にとどめるのがポイントです。挨拶文を控えめにし、送付内容の説明や案内に徹することで、信書と判断されにくくなります。
このように、文言を工夫するだけで「広告物」か「信書」かの線引きが変わるため、DM制作の段階から注意を払うことが不可欠です。
実例紹介(ケーススタディ)

ここでは、実際に「ゆうメールで信書とみなされた例」と「工夫でクリアできた例」を紹介します。具体的な修正例を知ることで、実務にすぐ活かせます。
ケース1:信書とみなされた例
送付内容:DM + 挨拶状
ビフォー文面:
「○○様 日頃より当店をご利用いただき誠にありがとうございます。今回は新商品のご案内をお送りします。」
問題点:
- 「○○様」で受取人を特定
- 「ご利用いただき」という表現が事実通知に該当
結果:郵便局で「信書」と判断され、ゆうメールでは送付不可に。
ケース2:修正して通った例
修正後の文面:
「お客様各位 平素よりご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。新商品のお知らせを同封いたしましたので、ぜひご覧ください。」
修正ポイント:
- 宛名を「各位」に変更し、不特定多数を対象に。
- 「ご利用」→「ご愛顧」という抽象表現に変更。
- 挨拶文は簡潔にし、案内の目的を明確化。
結果:郵便局の確認で「広告物」と判断され、ゆうメールで送付可能に。
ケース3:添え状でクリアできた例
送付内容:カタログ + 添え状
添え状文面:
「商品カタログをお送りいたします。ご参考にしていただければ幸いです。」
ポイント:
- 手紙風ではなく、送付物の説明にとどめる。
- 感謝や要望の表現を避ける。
結果:ゆうメールで問題なく送付できた。
このように、ちょっとした表現の違いで「信書」か「広告物」かの判断が変わってしまいます。DM制作時には、必ず表現をチェックし、必要なら郵便局に確認をとることが一番の近道でしょう。
審査の現場事情と送付前のリスク管理
実際にゆうメールを利用する際、最大の難しさは「現場での判断のばらつき」です。郵便局の担当者によっては、同じ内容のDMでも「これは信書です」と判断される場合があります。年々審査が厳格になっていることもあり、差し止められるリスクは無視できません。
さらに、差し止められた場合は発送が遅れるだけでなく、印刷や封入作業にかかったコストも無駄になってしまいます。特に販促キャンペーンやセール告知のように「送付タイミングが命」というケースでは、事前の確認が非常に重要です。
リスクを避けるための対応策
- 差出前に郵便局で確認:封筒見本や添付文書を持ち込み、事前に局員へ相談する。
- 内容のグレーゾーンを避ける:少しでも信書に近い表現は削除し、安全寄りに調整する。
- 発送前の社内チェックリストを作成し、宛名表現・添え状文言などを必ず確認する。
このひと手間で、差し止めや発送遅延といったリスクを大幅に軽減できます。
ゼネラルアサヒのDM成功事例

当社は、DM生産工場を持つ強みと、個別配送費に関する深い知識を活かし、企画からデザイン、そして郵送コストを考慮した最適な仕様まで、一貫してご提案します。他社にはない、お客様の事業に寄り添った本質的な提案力こそが、私たちの最大の強みです。
1.DM施策の常識を覆した成功事例:接触頻度より「質」で成果を出す
「DMは毎月送らなければ、顧客は離れていく」そう考えていませんか? この事例は、DMの常識を覆し、コストを抑えながらも売上を向上させた当社の成功事例です。
毎月A4×4ページのキャンペーンDMを送付していた健康食品A社様の事例です。昨今の郵送費高騰を受け、DMの仕様と発送頻度の見直しをご提案しました。
DMのページ数を増やし、より多くの商品やサービスを掲載することで、顧客に対してより深くメリットを伝えられるようになりました。また、発送頻度を減らしコストを抑えることにもつながりました。
結果:
- エンドユーザーのクロスセルが向上し、客単価がアップ
- クライアントの郵送代が1/2に削減
この事例は、単に接触頻度を減らすのではなく、「接触時のメリットを最大限に打ち出す」ことの重要性を示しています。コストを抑えつつ、顧客の購買意欲を高めるDM施策は十分に可能です。
2.休眠顧客を掘り起こし、コスト削減も実現したDM改善事例
DMの反応率低下にお悩みではありませんか? この事例は、DMの紙面内容と仕様を見直すことで、休眠顧客の掘り起こしと大幅なコスト削減を同時に実現した成功事例です。
DMを送付していた健康食品B社様から、コンバージョン率(CVR)が低下しているとのご相談をいただきました。そこで私たちは、現状の紙面を徹底的に分析。重複している内容を整理し、訴求の中心を「価格」から「お客様の声」や「成分のメカニズム」へと切り替えることをご提案しました。
さらに仕様を見直すことで郵送費も大幅に削減。紙面の訴求力向上とコスト削減の両面から改善を図った結果、CVRは1.4%向上しました。
結果:
- 売上や申込数など目標達成に直結
- 単なる安さではなく、商品の信頼性を高めた
- 重複をなくし、DMの情報設計が明確化。読みやすさアップ
「短期的な成果改善」と「長期的なブランド価値向上」を両立できる良事例といえます。
まとめ
ゆうメールはコスト面で魅力的ですが、信書は送れないという明確な制限があります。違いを正しく理解し、文面を工夫することで、DMを安全に発送することが可能です。宛名や表現を少し変えるだけで、信書か否かの判断が分かれるため注意が必要です。どうしても信書を送りたい場合は、普通郵便やレターパック、スマートレターなど代替手段を検討しましょう。発送前には必ず郵便局で確認し、リスクを未然に防ぐことが、コスト効率と確実性を両立する最適な方法です。
私たちは、印刷会社を母体とする強みを活かし、DMをはじめ、ウェブや動画を組み合わせた最適なプロモーションをご提案します。企画から効果検証まで一気通貫で行うことで、お客様の成果を最大化します。
まずはお気軽にご相談ください。