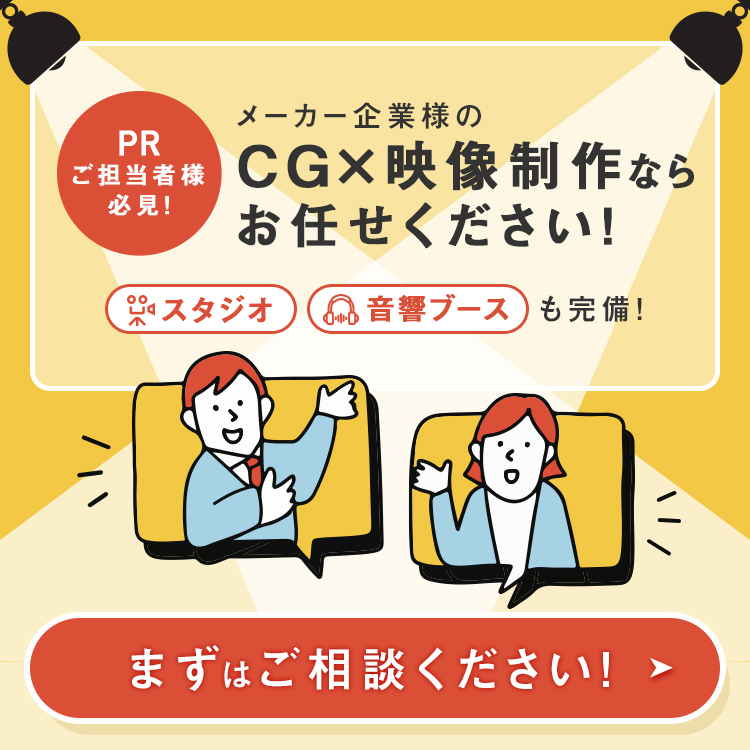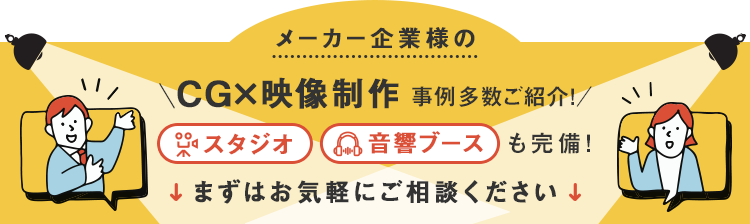動画制作における「撮影」に関する専門用語をピックアップし、解説するシリーズPart2です。プロの撮影現場で使われる専門用語は、さらっと言われても何のことだろうと分からず、ついついそのままやり過ごしていませんか?
これらの用語を知っていれば、制作会社とのやりとりでスマートな進行ができるようになります。これから動画の制作・編集を始める方にとって心強い味方になってくれるはずです。
ぜひこの記事を事前に読み込んで、動画制作に臨むことをおすすめします。
■目次
動画撮影で押さえておきたい基本用語
今回は「動画撮影で押さえておきたい用語20選」の「Part2」として、20の専門用語をご紹介します。用語への理解が深まることで、どういった撮影が効果的か、スムーズな撮影のために準備しておくこと、また撮影のイメージなどが掴みやすくなるものです。
ここでは、撮影時のカメラの設定や注意点などに関する専門用語を詳しく解説します。
こちらもチェック!
今さら聞けない!動画制作・編集の基本用語集 Part1はこちら
今さら聞けない!動画制作・編集の基本用語集 Part2はこちら
動画撮影で押さえておきたい用語20選 Part1はこちら
ホワイトバランス
「ホワイトバランス」とは、白いものが白く映るように被写体の色を正確に再現するための機能です。夕日に照らされた被写体が赤く見えるように、被写体の色は光の色によって見え方が変わります。これは光源ごとに固有の色温度があり、青っぽく見えたり赤っぽく見えたりするためです。
デジタルカメラやビデオカメラには、カメラがホワイトバランスを自動で調整してくれる「オート」と、「晴天(太陽光)」「曇天」「日陰」「蛍光灯」「電球」といったプリセット(あらかじめ設定されたモード)があります。オートで補正が不十分な場合は、撮影時の光源に合わせてプリセットから選択するか、カラーチャートやグレーカード、純白の紙を使ってホワイトバランスをマニュアルで設定します。
シャープネス
「シャープネス」とは画像編集ソフトにおける調整項目のひとつで、輪郭部分のコントラストを強調したり、ソフトに見せたりする機能です。
シャープネスを強くすると、くっきりとしたシャープな画像になります。立体感が出て、細部の描写も鮮明になり、解像度が高くなったような印象になります。
逆にソフトで柔らかな雰囲気に仕上げたいときは、シャープネスを低く設定します。デジタルカメラでは撮影時にシャープネスを設定できるものもあります。
RAW、RAWモード
「RAW」とは英語で「生の」「未加工の」という意味があり、デジタルカメラ内で画像処理せずに未加工の状態で記録するモードを「RAWモード」、そしてそのファイル形式のことを「RAW」といいます。
通常の撮影ではカメラ内で画像処理が行われ、圧縮、各種動画形式へ記録されるため、そのまま再生することができますが、RAW画像はそのままでは見ることができません。RAWモードで撮影した場合は、現像が必要です。
RAWファイルの現像とは画像処理ソフトを使い画像調整や各種動画形式へ変換することで、RAWファイルの大きな特徴は高画質のまま、より細かな画像調整ができることです。さまざまな調整や加工をしてもデータの劣化を最小限に抑えることができ、またイメージ通りの映像に仕上げることができます。
一方でデータ容量が大きいため、パソコンに負荷がかかったり、データの取り扱いに手間がかかったりなどのデメリットもあります。
TIFF
カメラ側で保存する基本のフォーマットで、RAW画像を高画質のまま保存するファイル形式を「TIFF」といいます。可逆圧縮なのでオリジナル画像の品質を損なわず再現性が高いため、高い解像度が必要な場合など、主に印刷業界で使用される形式です。高画質で保存するためファイル容量が大きく、WEBでの利用には適していません。拡張子は「.tif」または「.tiff」です。
TIFF形式は、バックアップしておくオリジナルの元画像のファイルに適しています。用途やメディアに応じて加工・圧縮し、JPGやPNGなどのファイル形式に変換して利用します。

アングル
「アングル」とは英語で「角度」という意味で、被写体に対して構えるカメラの角度のことをいいます。アングルには3種類あり、被写体が同じでもアングルを変えることで見え方が異なります。アングルによって視聴者が受ける印象も変わるため、使い分けることで効果的な演出ができます。
・ハイアングル
被写体を見下ろすようにカメラを下に向けた角度。「俯瞰」ともいいます。被写体を小さく見せるため、寂しさや弱さを表現する効果もあります。ヘリコプターやドローンなど空からの撮影では、状況説明や景観の広がりを表現できます。
・水平アングル
被写体に対して水平にカメラを向けた角度。安定した基本のアングルで、視聴者が違和感を持たずに落ち着いて見ることができます。一方で映像に変化がなく退屈に感じられる場合もあります。
・ローアングル
被写体を見上げるようにカメラを上に向けた角度。「あおり」ともいい、被写体を大きく見せるため、尊大や威厳なども表現できます。インタビューや高層ビルなどの撮影で用いられます。
ケラレ
写真や映像の隅に黒い影が出てしまうことを「ケラレる」といいます。ケラレの原因は、レンズフードやレンズに取り付けたフィルターの映り込みです。特に広角レンズ装着時に発生しやすく、レンズフードをきちんと取り付ける、フィルターを重ね付けしない、薄枠のフィルターを使用する、などで防止できます。
順光/逆光
「順光」とは、被写体の正面から当たる光のことをいいます。被写体にどの方向から光が当たっているかで、被写体の見え方や映像の雰囲気が変わります。順光で撮影をすると発色が良く、被写体の色や形を綺麗に見せることができますが、立体感に欠け、のっぺりとした映像になりがちです。
横から当たる光のことを、「斜光」または「サイド光」といいます。立体感や陰影が出て、ドラマチックな表現ができます。
被写体の後ろから当たる光を「逆光」といいます。逆光で撮影すると被写体が暗くなるため、逆光での撮影はNGと思われがちですが、実はポートレートや花、料理の撮影に向いています。ふんわりとした柔らかい雰囲気を表現でき、料理の場合はみずみずしく美味しそうに撮影できます。花びらや葉が透けて見えるので、キラキラとした透明感のある映像になります。逆光で被写体が暗くなってしまう時は、露出を調整したり、レフ板やストロボなどの補助光を追加して明るく映るようにします。
白飛び/黒つぶれ
「白飛び」とは、肉眼では見えていても実際に撮影をすると、ハイライト部分(明るい部分)の階調がなくなり白くなってしまうことをいいます。光源が強すぎたり、露出設定が上がりすぎると、ハイライトの強い部分で起こりやすくなります。
白飛びは編集ソフトで補正はできますが、程度によっては相応の編集技術が必要なため、特にメインの被写体は白飛びしないように注意して撮影しましょう。
また逆に、光量が足りなかったり、露出設定を下げすぎてしまい、暗い部分が真っ黒になってしまうことを「黒つぶれ」といいます。
■色かぶり
「色かぶり」とは、撮影時の光源や近くの物体からの反射光によって画像全体が特定の色に偏ってしまうことをいいます。例えば蛍光灯の下で撮影すると全体的に青っぽく写ったり、電球の下ではオレンジがかった画像になったりします。
本来の色よりも青くなってしまうことを「青かぶり」、赤くなってしまうことを「赤かぶり」などということもあります。
色かぶりを防ぐには、撮影時のホワイトバランスの設定が重要です。「オート」にする、光源に応じてプリセットから選択する、またはマニュアルで調整するなどして、ホワイトバランスを適切に設定します。
色かぶりしてしまった場合は、RAWデータであればRAW現像時に補正したり、編集ソフトで補正したりすることもできます。
シズル感
「シズル感」とは主に広告撮影の現場で使われる、おいしさやみずみずしさを表現する言葉です。肉が鉄板でジュージューと焼けて肉汁が滴り落ちる状態を表す英語「sizzle」に由来し、冷えたビールジョッキの表面についている水滴やステーキの切り口から滴る肉汁や焼ける音など、視聴者の五感を刺激し、食欲や購買意欲をそそる様子をいいます。
「シズルの撮影」や「シズル感をもっと出して」といったように使われます。元々は料理の撮影現場で使われる言葉でしたが、最近では食べ物以外の商品撮影においても臨場感やリアルな使用感を表すような演出を行う際に用いられることがあります。

テクスチャ
被写体の質感のことを「テクスチャ」といいます。金属や木材、織物など被写体ならではのテクスチャを表現できれば、視聴者はその被写体を触った時の触感、「滑らか」や「でこぼこ」「ツルツル」「ふんわり」などをよりリアルにイメージすることができます。
テクスチャは、被写体の表面の凹凸が伝わるように細部まで鮮明に映すことで表現できます。絞りを絞り込んで撮影したり、マクロレンズを使ってマクロ撮影したりするほか、編集ソフトなどでも調整できます。
ねむい
明暗の差が少なくメリハリがない画像や映像は「ねむい」と評価されます。コントラストや彩度、シャープネスが低くなっていたり、曇りの日や空気が淀んでいるような時間帯に撮影をすると、色が全体的に淡く霧がかかったような印象になりやすいです。
これらは、曇りや日陰など光量が不足している状況での撮影や被写体に光が当たりすぎて白飛びしている状態、ホワイトバランスが適切に設定されていない、レンズによってはコントラストやシャープネスが低い特性がある、などが原因で発生すると考えられます。
「ねむい」画像や映像は、編集ソフトを使ってコントラストやシャープネスを調整することで改善できる場合があります。 一方で、コントラストや彩度が高く、クリアで鮮明な印象を与える画像や映像は、「抜けが良い」「抜け感がある」と評価されます。
ハイライト
画像の最も明るい部分のことを「ハイライト」といいます。光源からの光を反射し白く光っている部分などです。ハイライトと陰影があることで、コントラストの効いた印象的な画像に仕上がるため、撮影時にはハイライトと陰影を意識します。
ライティングによってハイライトを入れることで、被写体の立体感を表現することもできます。例えば、無機質で平面的な家電製品もハイライトが入ると立体的になり質感も表現できます。料理ではソースの照りや食材のみずみずしさ、時計やジュエリーでは輝くような高級感などを表現でき、ハイライトは商品を魅力的に見せる技法でもあります。
ハレーション
「ハレーション」とは逆光などでレンズに強い光が入り込み、画像の一部が白っぽくぼやけてしまうことをいいます。ハレーションは本来、フィルムの内面で光が反射して起こる現象のため、フィルムのないデジタルカメラでは起こりません。しかし、デジタルカメラであってもハレーションによく似た「フレア」という現象が起きるため、カメラの種類に関わらず、強い光で被写体がにじんだり、白っぽくなったりする現象のことを「ハレーション」と呼び、混同して使われることも多いです。
また、「ハレ切り」とは「ハレーション切り」の略で、ハレーションが起こらないように黒いパネルや紙などで光を遮り、レンズ面に直接光が当たるのを防ぐことをいいます。
ハレーションを起こさないようにするためには、始めから強い光が入り込まないアングルで撮影をする、レンズフードをつけるなどの対策があります。
逆に、眩しさや幻想的な雰囲気を演出するために、あえて画面に太陽や光源を入れてハレーションやフレアを起こすこともあります。

フレア/ゴースト
「フレア」とは、太陽光など強い光にレンズを向けたときに起こる現象で、レンズやカメラボディの中に入り込んだ光が反射してカブリやムラが出たり、画像の一部または全部が白っぽくなったりすることをいいます。ハレーションとよく似ていますが、発生の仕組みが異なり、フィルムではなくレンズ、またはボディで起こる現象のため、デジタルカメラでも発生します。
フレアの一種に「ゴースト」という現象もあります。ゴーストは、本来存在しない光がはっきりとした形で画像に映り込むことを指します。
デジタルカメラにおいても、強い光が入り込まないアングルで撮影する、レンズフードをつけるなど、フレアやゴーストを防ぐことが大切です。
モアレ
規則正しく繰り返す細かな網模様や縞模様が複数重なると、本来ないはずのまだら模様が発生します。これを「モアレ」、または「干渉縞」といいます。
撮影においては細かい線が多数ある被写体や、人物の場合にストライプやチェックの衣装を着ていると、映像にモアレが目立って現れることがあります。
これは、カメラのセンサーが本来一定の間隔で整列している網模様や縞模様の網点を正確に再現できず、角度のズレなどによってお互いが干渉し合うことで起こります。
モアレを防ぐにはわずかにピントをずらして撮影をするほか、動画編集ソフトで設定することでモアレを除去することができます。人物撮影の場合は、細かな模様の衣装は避けましょう。
レタッチ
撮影した画像や映像の色補正やコントラストの調整、また映り込んでしまった不要なものの消去や合成などの修整作業のことを「レタッチ」といいます。レタッチは「Adobe Photoshop」など専用の画像編集ソフトや、動画であれば動画編集ソフトの「Adobe premiere Pro」や「Adobe After Effect」などを使って行います。
レタッチを過度に行うと不自然な画像や映像になってしまいますが、広告や映像作品においてレタッチは必要不可欠な技術であり、撮影した映像をそのまま使うことはほとんどありません。レタッチによって表現の幅が広がったり、より魅力的な映像に仕上げたり、またある程度不要なものが映り込んでしまっても撮り直さずに修整することができます。

露出/露出補正
「露出」とはカメラの撮影素子に取り込まれる光の量のことをいい、画像の明るさのことです。同じ画像でも露出(明るさ)によって印象は大きく変わります。
露出は絞り、シャッタースピード、ISO感度(業務用ビデオカメラではゲイン)の3つの要素で決まりますが、動画の場合、シャッタースピードはほぼ固定されるので、絞りとISO感度で露出を調整します。ただし、ISO感度は高ければ高いほどたくさんの光を取り入れることができますが、上げすぎると映像がどんどん粗くなってしまうので注意しましょう。
画像が暗くなってしまうことを「露出アンダー」、逆に明るくなってしまうことを「露出オーバー」といい、明るすぎたり、また暗くなりすぎたりしないように露出を調整することを「露出補正」といいます。
露出補正は、決して適正露出にするためだけに行うものではありません。意図的にアンダーやオーバーに設定することも、イメージに合わせた映像づくりの方法のひとつです。
一般的には、プラス補正する(明るくする)と爽やかさや柔らかさ、透明感などを表現でき、マイナス補正(暗くする)すると引き締まった感じや落ち着いた雰囲気、重厚感などを表現できます。
色温度
色温度とは、光源の色を表す尺度で、単位はケルビン(K)を使います。数値が低いほど赤みがかった温かみのある光になり、数値が高いほど青みがかった冷たい光になります。
- 低い色温度(約2700K):ろうそくの炎、白熱電球など、橙色が強い温かみのある光
- 中間色温度(約5000K):太陽光(昼光色)など、自然の爽やかな白色光
- 高い色温度(約6500K):曇り空、蛍光灯など、青みが強いクールでクリアな光
カメラで撮影する際に色温度は非常に重要な要素です。人間の目は異なる光源の下でも自動的に色を補正して認識することができますが、カメラは自動的に補正できないため、色温度が合っていないと色の再現性が悪くなり、被写体の本来の色になりません。
色温度による問題を解決するには、ホワイトバランスをカスタム設定する、RAW撮影して画像処理ソフトで色温度を調整する、色温度変換フィルターで光の色を調整する、などのやり方があります。
色温度は写真や映像の印象を大きく左右するため、色温度について理解し、適切な設定や調整を行うことで、より自然な色合いの映像を撮影することができます。
被写界深度
被写界深度とは、写真や映像においてピントが合っているように見える奥行きのことです。レンズを通してシャープに写るピント面から比較的シャープに見える範囲を被写界深度と呼び、被写界深度外の範囲はピントが合っていない状態でボケが生じます。被写界深度を理解することは、写真の表現を大きく左右する重要な要素となります。
被写界深度は、絞り値(F値)、レンズの焦点距離、被写体との距離の3つの要素によって決まります。絞り値を小さくする(絞りを開く)ほど、被写界深度は浅くなり、背景ボケが大きくなり、絞り値を大きくする(絞りを絞る)ほど、被写界深度は深くなり、パンフォーカスに近づきます。焦点距離が長い望遠レンズでは、被写界深度は浅くなり背景ボケが大きくなり、広角レンズでは、被写界深度が深くなり広い範囲にピントが合います。被写体に近づくと被写界深度は浅くなり、被写体から離れると被写界深度は深くなります。
被写界深度を活かした表現では、被写界深度を浅くすることで、主題以外をぼかし、主題を際立たせることができるため、ポートレートやマクロ撮影でよく用いられます。被写界深度を深くすることで、風景全体にピントを合わせ、雄大さを表現できるため、風景写真などでよく用いられます。

まとめ
今回は、動画撮影で押さえておきたい20の専門用語について解説しました。カメラの機能を知り適正に設定すること、撮り方をちょっと工夫すること、撮影した動画を修整・加工しイメージに近づけることで、仕上がりは段違いに変わります。「Part1」とともに、これから動画撮影を始めようと考えている初心者の方、企業担当者の方はぜひ参考にしてください。
いま、動画はスマートフォンや小型カメラでも気軽に撮影できますが、より高いクオリティを求める場合は専門のカメラや機材、ライティングの知識・技術、高度なカメラワークが必要です。
当社は、大型スタジオからキッチンスタジオまで全国に8つの撮影スタジオを完備し、最新の撮影機器や撮影セット、小道具を備えています。スタジオ撮影から国内ロケ、海外ロケ、ドローン撮影などあらゆる撮影に対応し、リモートでの撮影立ち合いやディレクションも可能です。
動画撮影をご検討の方は、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせください。
https://www.generalasahi.co.jp/cd/movie/contactform/
また、当社のホームページでは用語だけでなく、動画制作に関する最新動向や制作のポイントなど、企業の担当者の方に役立つ情報をコラム配信しています。動画に関する気になることやお探しの情報があれば、ぜひチェックしてみてください。
https://www.generalasahi.co.jp/cd/movie/topics/