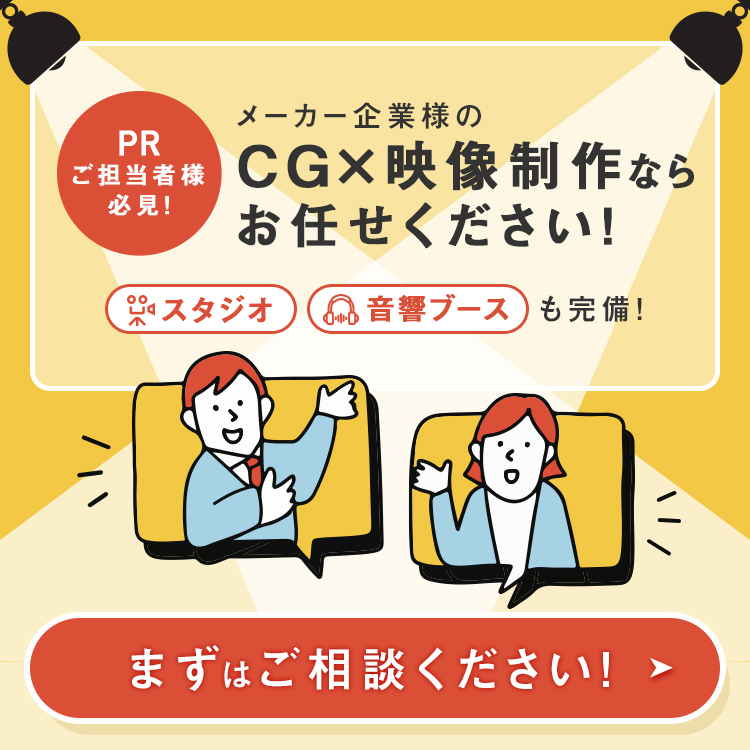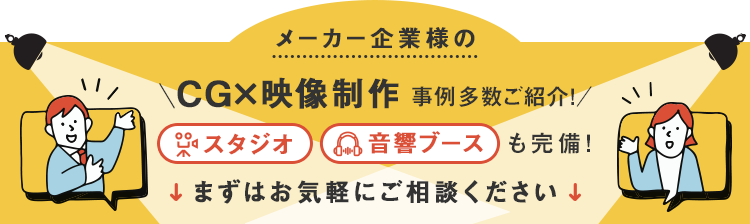今や、スマートフォンやタブレットの普及により、動画を通じた情報伝達が身近になってきました。そんな中で、企業や組織が従来の紙のマニュアルに代わって採用し始めているのが、動画マニュアルです。
では、動画マニュアルとは何か、どのように活用できるのか、そして効果的な動画マニュアルを作るコツは何か。これらの疑問に答えながら、動画マニュアルの魅力に迫っていきましょう。
■目次
動画マニュアルとは

動画マニュアルとは、文字や静止画像だけでなく、動画を使って手順や情報を伝える新しいタイプのマニュアルです。従来の紙のマニュアルと比べて、以下のような特徴があります:
- 視覚的に分かりやすい
- 音声による説明が可能
- 複雑な手順も理解しやすい
- 何度も繰り返し視聴できる
- スマートフォンやタブレットで手軽に見られる
例えば、新しい機械の使い方を説明する場合、文字だけの説明では理解しづらい部分も、実際の操作の様子を動画で見せることで、誰でも簡単に理解できるようになります。
特に企業向けの場合には、教育のたびに準備しなければならなかった大量の紙のマニュアルや教育にかかる人件費、時間を削減でき、場所の確保も必要なくなります。動画マニュアルを導入することでコスト削減と業務の効率化を目指せることが、導入する企業が増えている理由です。
当社のマニュアル動画の事例はこちら そのほかの実績はここをクリックしてください。
動画マニュアルの主な種類

動画マニュアルを用いることで、より効率的で効果的な作業手順や製品の説明が実現します。
ここでは、さまざまな場面で活用されている動画マニュアルの種類について解説していきます。
製品のチュートリアル
動画マニュアルは、製品やサービスについて、より具体的かつ視覚的に実践する指導書として活用されています。新しく購入した製品の使い方は誰もが習得するまでに時間を要します。
そこで、例えば機械など製品やソフトウェアの基本的な操作方法を、ステップバイステップで解説します。ユーザーは、実際の製品を目の前にしながら動画を見ることで、スムーズに使い始めることができます。
特に、ソフトウェアなどに多く用いられます。製品やサービスを提供する企業のホームページなどで、公開されているのを見たことがあるかもしれません。複雑で専門的な内容でも、視覚的・聴覚的に伝えられ、消費者の理解につながるでしょう。
研修マニュアル
企業では、新入社員教育や、既存社員のスキルアップのための研修用動画として動画マニュアルが積極的に使われています。特に、新人向けの研修を行う際に、基本的なビジネスマナーや名刺交換、電話応対、社内ルールなど研修のテーマ別に作成しておくと便利です。講師が不在でも統一された内容の研修を行うことができます。
先輩社員や店長などへ向けた、指導者用マニュアルもあります。例えば、フランチャイズ店舗向けの運営マニュアルです。接客から商品、サービスの説明の仕方に加え、接客態度や考え方までが網羅されています。
業務手順マニュアル
業務手順マニュアルは、多くの企業で作成され、活用されています。主な目的は、新入社員や派遣社員、アルバイトの方に向けて、仕事の全体像や業務フロー、作業手順などを説明することです。
動画マニュアルを作成しておけば、指導者による資料作成の準備や教育のための時間を削減でき、社内教育の負担の軽減が可能です。業務手順などは文章では説明しづらい部分があるでしょう。動画で作成することで視覚的に説明できるため、より効率的に社員の理解を深められます。
教わる側にとっても、短時間でポイントをおさえやすく、すばやく担当業務に従事できるでしょう。通常業務の一般的な手順だけでなく、イレギュラーなトラブル発生時の対応や、変動的な業務など、テーマごとに動画を用意しておくと便利です。
動画に網羅されないケースなどについては口頭で説明するなどし、業務手順マニュアルと併用して活用するとよいでしょう。
営業マニュアル
営業マニュアルは、主に企業の営業担当向けに作成され、営業職の基本的な業務フローやノウハウが網羅されています。具体的にどのように営業活動をするか、視覚的にまとめたものです。営業ならではのルールなどがわかりやすく文章化されています。
接客業であれば、接客の手順やサービス、考え方などを学べるでしょう。営業マニュアルには、組織で働くにあたって必要とされる実践的なノウハウが盛り込まれています。
動画マニュアルのメリット

動画マニュアルは、企業や組織が抱える様々な課題を解決する可能性を秘めています。ここでは、動画マニュアルがもたらす主なメリットを見ていきましょう。
コスト削減ができる
企業は、遠隔地の社員も同じ品質の研修を受けられるため、出張費を大幅に削減できます。全国の支店社員に新商品の説明をする際、各地への出張を動画マニュアルで代替できれば、交通費、宿泊費、日当などの経費が不要になります。
更新コストの削減も見逃せません。内容の更新が必要な場合、動画の一部だけを差し替えることで対応できます。例えば、製品マニュアルの一部仕様が変更になった場合、該当部分の動画だけを再撮影・編集することで紙と違って修正が簡単ともいえます。
会社の資産になる
動画マニュアルは、会社の貴重な知的資産となります。ベテラン社員の技術やノウハウを動画で記録することで、次世代への技術伝承がスムーズに行えます。また、会社独自の業務プロセスや顧客対応方法などを動画で残すことで、一貫性のあるサービス提供につながります。
初期費用はある程度かかるとしても、一度制作すれば繰り返し使用でき、費用対効果はかなり高いところがポイントです。
動画で理解度がアップ
さらに大きな利点は、学習者の理解度を大幅に向上させることです。従来の文字や静止画像だけのマニュアルと比べ、動画マニュアルは複数の感覚を同時に刺激することで、情報の吸収と記憶を促進します。
例えば、製品の組み立て方を説明する場合、実際の組み立ての様子を見ながら音声解説を聞くことで、手順をより直感的に理解できます。これは、文字だけの説明では伝えきれない微妙な動きや力加減など細かな動きを視覚的に把握でき、紙との大きな違いといえるでしょう。
また、テロップや図解、アニメーションなどの視覚効果を効果的に使い、複雑な情報も分かりやすくします。そのことでより理解度を上げ、学習効果を高めます。
自動翻訳
最近の技術の進歩により、動画マニュアルの音声や字幕を自動で他言語に翻訳することが可能になっています。これにより下記のようなことが想定されます。
- グローバル展開している企業で、各国の社員が同じ内容を学べます。
- 海外の顧客向けに、製品説明を多言語で提供できます。
- 言語の壁を越えて、社内のコミュニケーションを活性化できます。
このように、動画マニュアルは単なる情報伝達ツールではなく、企業の効率化や国際化を促進する強力なツールとなり得るのです。
企業の規模や動画マニュアルの活用範囲によって変わりますが、長期的に見れば大きな経済的メリットをもたらす可能性があります。また、単なるコスト削減だけでなく、情報伝達の質や効率も向上させることができるのが動画マニュアルの強みです。企業は、これらの多面的なメリットを考慮しながら、動画マニュアルの導入を検討することが重要です。
効果的な動画マニュアルのコツ

良い動画マニュアルを作るには、いくつかのポイントがあります。ここでは、準備から完成までの流れに沿って、そのコツを紹介します。
事前準備のコツ
- 目的を明確にする:何を、誰に、どのように伝えたいのかを明確にしましょう。
- ターゲットを理解する:視聴者の知識レベルや背景を考慮し、適切な内容と表現を選びます。
- 全体の流れを決める:伝えたい内容を整理し、論理的な順序で並べます。
- 必要な機材を用意する:カメラ、マイク、照明など、品質の良い動画を撮影するための機材を準備します。
構成のコツ
- 導入部分を工夫する:動画の冒頭で、内容の概要や目的を簡潔に説明します。
- セクションに分ける:内容を小さなセクションに分け、理解しやすくします。
- 重要ポイントを強調する:キーワードや重要な手順は、視覚的に目立たせます。
- まとめを入れる:各セクションの最後に簡単なまとめを入れ、理解を深めます。
撮影のコツ
- 明るい場所で撮影する:十分な光量があることを確認し、必要に応じて照明を使用します。
- 安定した画面を維持する:三脚を使用するなど、カメラがぶれないよう注意します。
- クリアな音声を収録する:外部マイクを使用するなど、聞き取りやすい音声を心がけます。
- 複数のアングルを使う:全体像と細部の両方が分かるよう、適切にアングルを変えます。
編集のコツ
- 不要な部分をカットする:冗長な部分や失敗したテイクは思い切ってカットします。
- テロップを効果的に使う:重要な情報や補足説明をテロップで表示します。
- BGMや効果音を適度に入れる:集中力を維持するため、適切な音楽や効果音を入れます。
- トランジションを工夫する:場面の切り替わりをスムーズにするため、適切なトランジション効果を使います。
これらのコツを押さえることで、より効果的な動画マニュアルを作ることができます。次に、さらに詳しく、効果的な動画マニュアルを作るためのポイントを見ていきましょう。
動画マニュアル作成時の3つのポイント
プロの視点で、動画マニュアルを作る際に押さえておきたいポイントをまとめました。
マニュアル動画といっても、日常でもよく使うような商品から工場など目の触れない場所で使う製品のマニュアルまで多岐にわたりますが、ここでは一部を紹介しています。最近では、医療機器メーカーの医療系マニュアル動画の実績もあります。
まずは、実績をご覧ください。(一例)
https://www.generalasahi.co.jp/cd/movie/works_type/manual/
POINT1:テーマを基本に短くまとめる
動画マニュアルは、1つの動画につき1つのテーマに絞ることが大切です。例えば、「コピー機の使い方」という大きなテーマがあれば、「用紙のセット方法」「両面コピーの取り方」「拡大・縮小コピーの方法」など、より具体的なテーマに分けて、それぞれ別の動画を作成します。
また、1つの動画は5分以内を目安に作るのがよいでしょう。長すぎる動画は視聴者の集中力が途切れてしまいます。必要な情報を簡潔にまとめることで、効果的な学習につながります。
また、製品やサービスのチュートリアルなど、消費者向けの動画マニュアルをYouTubeなどの動画投稿サイトや自社ホームページで一般公開している企業もあります。消費者は自分のタイミングでマニュアルを確認でき、文章ベースのマニュアルよりも多くの情報を短時間で得られるでしょう。
POINT2:カメラワークや展開スピードに配慮する
動画マニュアルでは、カメラワークや情報の展開スピードも重要です。例えば、製品の全体像を示す時は広角で撮影し、細かい操作を説明する時はクローズアップするなど、適切なカメラワークを心がけましょう。
また、情報の展開スピードは、視聴者が理解しやすいペースを保つことが大切です。早すぎると理解が追いつかず、遅すぎると退屈してしまいます。適度な間を取りながら、重要なポイントではゆっくり説明するなど、メリハリをつけることが効果的です。
POINT3:テロップやハイライトなどを活用する
動画マニュアルでは、視覚的な要素を積極的に活用することで、より分かりやすい説明が可能になります。
例えば:
- テロップ:重要なキーワードや補足説明を画面に表示します。
- ハイライト:注目してほしい部分を光らせたり、色を変えたりして強調します。
- アイコンや図解:複雑な情報を簡潔に表現するために、アイコンや図解を使います。
- ズームイン・アウト:細かい部分を強調したり、全体像を示したりする時に使います。
これらの要素を適切に組み合わせることで、視聴者の理解を助け、情報の記憶を促進することができます。
動画マニュアルの作り方5ステップ

ここまで動画マニュアルのコツや作成時のポイントについて述べてきました。では、実際にどのように動画マニュアルを作ればよいのでしょうか。ここでは、動画マニュアル作成の5つのステップを詳しく解説します。
ステップ1.マニュアルの目的とターゲットを設定する
動画マニュアルを作成する前に、まずは課題を分析しましょう。動画マニュアルの目的やターゲットを明確にするのが大切です。誰に何を伝え、どのような状態になるのが理想かを明確にします。ターゲットを決める際には、ターゲットのレベル感を想定しておくとよいでしょう。
例えば、製品の使い方や作業工程が複雑な場合には、テキストや画像では伝えにくいかもしれません。指導者によって教え方や指導内容、レベルが統一できないこともあるでしょう。
マニュアルで伝えるべき情報や伝え方の課題を洗い出すことで、動画の方向性や盛り込むべき内容が見えてきます。内容によっては、動画マニュアルだけでなく、紙のマニュアルと併用するなど、課題解決の方法も見えてくるでしょう。
ステップ2.構成案をもとに台本を作成する
解決すべき課題や盛り込みたい内容が見えてきたら、業務内容と伝えたいポイントを整理し、動画のテーマを設定しましょう。研修や商品の使用手順、作業内容などを伝える動画マニュアルは、より「わかりやすさ」が求められます。
わかりやすい動画マニュアルを作成するためには、1動画1テーマが基本です。一旦作業フローや使用手順を時系列で整理し、重要なパートを箇条書きで洗い出してみましょう。「テキストや写真では伝わりにくい部分を動画で解説する」という動画マニュアルだからこそ伝えやすい部分を意識するのが大切です。
テーマを設定し、伝えたいポイントを洗い出したら、構成案と台本を作成します。構成案を決める際には、撮影すべき内容やその順番、各カットの時間、テロップの入れ方も想定しておきましょう。
また、動画の方向性を決める際には、視聴者の利用シーンやデバイスを想定しておくのも大切です。企業の研修マニュアルであれば、会社のPCで集中して視聴することが想定できます。製品の使用手順など顧客向けである場合には、別のことをしながらスマートフォンで視聴することが考えられるでしょう。
PCに向かって視聴していれば、長時間の動画で手順ごとに解説する動画でも理解してもらいやすいです。片手間で視聴している場合には、短時間でポイントをおさえた動画のほうが理解されやすくなります。
伝えたい情報だけでなく、視聴者の属性なども考慮することで、より質の高い動画マニュアルの構成や台本、絵コンテが作成できるでしょう。
あわせて読みたい「プロが伝授!初心者でもできる絵コンテの作り方を解説」
ステップ3.動画を撮影する
撮影をスムーズに行うためには、準備と段取りが大切です。構成案や台本に沿って撮影しますが、実写で撮影する場合、編集段階になってもう一度撮影したいと思っても、難しいことがあります。撮影するカットの秒数やアングルを構成段階でしっかり決めておくのはもちろん、アングルを変えて数パターン撮影しておくと安心です。
撮影現場の担当者と一緒に内容が適しているか、都度映像チェックもしておきましょう。撮り直しを防ぎ、的確なカットを撮影するためにも重要です。カット数が多ければ、編集段階でも動画をつなぎやすくなります。

ステップ4.ナレーションを収録する
動画の撮影が終わったら、ナレーションを収録します。適度にナレーションを入れることで、より動画の内容がわかりやすくなり、メリハリができます。ナレーションは、動画全体の流れを補足し、図表や画像などの資料の解説として入れることが多いです。
ナレーションの内容も台本に落とし込んでおき、話すスピードや抑揚に気をつけて録音しましょう。回りくどい言い方を避け、活舌よくシンプルにポイントを伝えることが大切です。
ステップ5.動画を編集する
最後は、いよいよ動画の仕上げの段階です。撮影した動画や音声をもとに、編集アプリやソフトなど用いてテロップ・ナレーション・音楽などを挿入し、編集作業を行います。
マニュアル動画は単調になりがちなため、ナレーションのほかにもBGM・効果音・テロップを入れることでメリハリが出て効果的です。
ナレーションを入れる場合でも、テロップがあるとより理解を深められます。ただし、視聴者が文字だけに気を取られることがないよう、テロップは最小限に留めましょう。動画マニュアルは、動画とナレーションだけで理解できるのが理想です。
編集段階では、タイトルも入れます。動画をポイントごとに切り分け、何を解説しているかわかりやすいタイトルを適宜入れると理解が深まるでしょう。
編集で動画マニュアルに盛り込む全ての要素を入れ込んだら、全体の流れと内容を客観的に確認します。
動画マニュアル作成ソフトを選ぶ

動画マニュアルを社内で制作する際には、動画作成ソフトが必要です。動画作成の経験がない場合には、ソフトの操作性のよさや扱いやすさで選んでみましょう。使いやすいソフトを選ぶためのチェックポイントを3つ解説します。
機能や操作性
ソフトを選ぶ上で、使い勝手のよさは重要なポイントです。必要な機能が搭載されているか、スムーズに操作できるかなどを確認しましょう。専門的な知識やスキルがない場合には、誰でも簡単に操作できるシンプルなものを選ぶと安心です。
マニュアル化すべき内容が多い場合には、作成の手順が少なく、時間がかからないものを選びましょう。例えば、テロップを自動生成できるソフトなどを使用すれば、テロップ作成の手間が省けます。動画マニュアルをいかに効率的に作成できるかがポイントです。
外国人スタッフがいる場合は、多言語対応ソフトの活用も検討しましょう。多言語対応しているものや、日本語の音声を翻訳してテロップを生成してくれるものなど、多種多様なソフトがあります。
動画作成ソフトはさまざまなものがあり、どれを選べばよいのか迷うこともあるでしょう。トライアル期間を設けているサービスも多いため、操作性を試して比較してみるとよいでしょう。どのような動画マニュアルを作成したいかを考慮し、求める機能や操作性を確認するのが大切です。
サポート体制
動画作成ソフトを選ぶ上で忘れてはならないのが、サポート体制です。ソフト使用時に不明点が見つかった場合やトラブルシューティングなど、電話やチャットですぐに質問できるサポート体制が整っているかを確認しましょう。
また、動画マニュアルには企業の運営に関する重要な情報が含まれるため、セキュリティ対策も大切です。作成した動画マニュアルはクラウド上で管理することが多いため、セキュリティ面やデータ損失に対する対策がされているかなどもチェックポイントとしておさえておきましょう。
サポート体制の充実度はもちろん、サポート対応の曜日や時間もあわせてチェックしておくと安心です。深夜や休日に稼働する業種であれば、24時間365日対応のソフトを検討してみましょう。
利用料金
多くの企業にとって、動画作成ソフト導入で発生するコストは重要なポイントでしょう。無料のトライアル期間を設けているソフトがほとんどですが、期間が終了すればコストが発生します。また、トライアル期間中は一部機能が制限されているものも多いため、本格的な制作には有料版がおすすめです。
料金体系はソフトによって異なりますが、高額なものも少なくありません。導入費用や月額料金または買い切り料金など、利用する際に発生するコストを比較してみましょう。予算やソフトの使用頻度、活用方法などを考慮しながら自社に適したものを選ぶのが大切です。
【目的別】動画マニュアル活用事例

動画マニュアルを導入している企業がどのように活用しているのかは、気になるところです。ここでは、他社が作成した動画マニュアルの活用事例を3社ご紹介します。業種や職種によって、求められる要素は異なります。これから動画マニュアルの作成を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
【製品紹介】本田技研工業
消費者向けに作られた、発電機の使用方法を解説する動画マニュアルです。ナレーションとテロップを使用したシンプルな構成で、わかりやすくポイントがおさえられています。
発電機は、使用方法を誤ると危険です。そのため使用上の環境や使用前の確認事項など、注意すべき点を冒頭で解説しています。重要な内容を冒頭にもってくることで視聴者の注意を引くのも、動画マニュアル作成のコツです。
最終的に、エンジンオイルの確認方法は、取扱説明書を確認するようナレーションで誘導しているのがポイントです。
参考:https://youtu.be/Zt_E3JeXHmM?si=Ckpjo9uyGoY8bD51
【作業解説】岡本工作機械製作所
株式会社岡本工作機械製作所の社内向け動画マニュアルは、BGMやナレーションは使用せず、作業の流れを見せる映像とテロップのみのシンプルな構成です。一見するとシンプルすぎるようにも見えますが、機械の動作音が強調され、一連の作業の流れがわかりやすく作られています。
伝えるべき情報に絞り複雑な編集をしないことで、紙ベースのマニュアルよりもわかりやすい動画マニュアルになっているのがポイントです。
参考:https://youtu.be/JlbA7YKjlqg
【新入社員教育】ホーム株式会社
オフィス空間の企画提案をするホーム株式会社では、新入社員向けの動画マニュアルを活用しています。新入社員向けということで、従業員以外にマナー講師を起用している点がポイントです。プロの講師により、業務上の注意点がわかりやすく作られています。
シンプルな構成で、前半では商品を納品する際の流れを説明し、後半では新入社員が直面しやすい事例を解説しています。自社内で新入社員向けの動画マニュアルを作成する上で、参考になる動画です。
参考:https://www.youtube.com/watch?v=DdMhOFQCYEo
まとめ
動画マニュアルは、文字や静止画像だけでは伝えにくい手順や情報を、視覚的・聴覚的に分かりやすく伝えることができる効果的なツールです。導入により、教育コストの削減や、統一された研修の実現、技術やノウハウの確実な伝承が可能になります。
また、作成時は1動画/1テーマを基本とし、5分程度の長さに抑えると視聴者の集中力を保ち、必要な情報への誘導が期待できます。さらにはカメラワークや展開スピード、テロップやハイライトの活用など、視聴者目線での工夫を取り入れることで、より効果的な動画マニュアルに仕上がるでしょう。自動翻訳機能を組み合わせると、グローバルな活用の可能性も広がるでしょう。
当社では、動画マニュアルの企画から動画制作・編集まで行っています。お見積り等、下記URLよりお気軽にお問い合わせください。