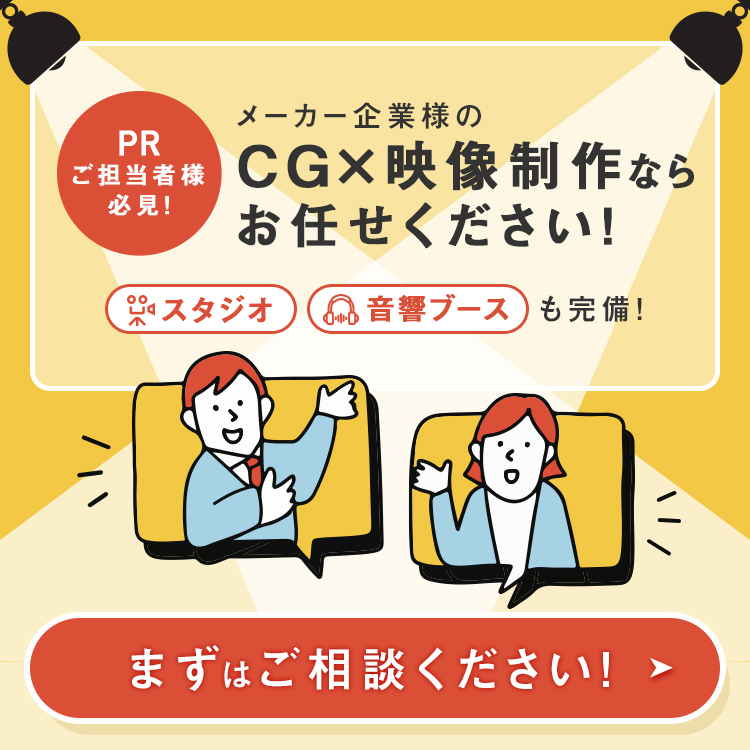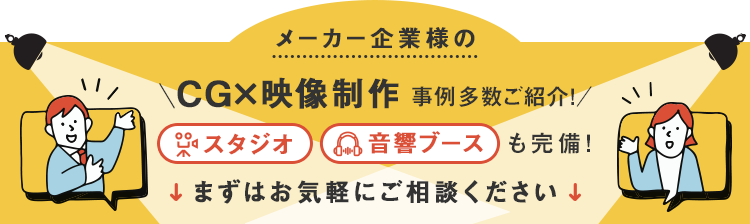コロナ禍を経て、ようやく気軽に移動できるようになり、インバウンドの需要も盛り上がりを見せています。そこで、さまざまな地域の魅力を伝えるコンテンツとして、動画を活用したPR方法に注目が集まっています。
モバイル端末の普及によりYouTubeやSNSを利用して手軽に動画を見る機会が増え、紙のパンフレットとは違った地域PRが可能になりました。しかも、企画次第では大きな反響が得られることも魅力です。
地方自治体においても、この機会に動画制作を検討してみてはいかがでしょうか。
この記事では、地域PRを動画で行うメリットや、地域を盛り上げた成功例を具体的に挙げると共に注意しなければならないポイントもご紹介します。
■目次
地域をPRする方法

地域を活性化させるために、各地ではさまざまな方法で地域PR(地方PR)が行われています。地域PRの主な方法は、PR動画の制作・配信やイベントの開催、SNSや雑誌での発信などです。返礼品を受け取れるふるさと納税も近年注目されるようになり、地域PRへの活用が広がっています。それぞれの方法の特徴を詳しく見ていきましょう。
動画
その地域ならではの風景やグルメを映した動画では、魅力を視覚的によりダイレクトにPRできます。短時間でも多くの情報を伝えられる方法で、臨場感のある演出やストーリーを持たせることが可能です。動画配信プラットフォームを用いることで多くの人にアプローチでき、SNSでの拡散力にも優れています。一気に知名度を上げられる可能性のある、効果の高いPR方法です。
イベント
訪問客が体験できるイベントの開催も、地域のPRに効果的です。イベントと一口にいってもさまざまなパターンがあります。例えば、ご当地ラーメンのイベントやバレンタインフェアなど、各地の店舗が集まってテーマに沿った商品を販売するイベントがその一つです。「北海道物産展」「沖縄フェア」といった、ある地域を特集するイベントもあります。音楽フェスなどの大きなイベントをある地域で開催して、地域に訪れる人を増やすイベントもその一つに挙げられるでしょう。
SNS
若年層への周知に効果的な方法がSNSを使ったPRです。自然やグルメなどをはじめとするインパクトのある写真や動画を載せることで、効果的に訴求できるでしょう。共感を得られれば、投稿をシェアしてもらうことで拡散も狙えます。ご当地キャラが地域について発信する形式を取ることも方法のひとつで、より親しみやすさが増すでしょう。
ふるさと納税
ふるさと納税とは、応援したい自治体を個人が選んで寄付できる制度のことです。寄付を行う先の自治体を決めるために、多くの人が重視するのが返礼品です。自治体は、地域の特色を活かした魅力的な返礼品を用意することで多くの寄付を集められます。このようにふるさと納税は、返礼品を通して地域をPRできる機会となっているのです。
雑誌
雑誌への掲載もPR方法の一つです。広告を出す、地域への旅行プランやグルメなどを特集してもらうなどの方法があります。雑誌には、地域住民に向けた情報誌や観光客に向けた旅行雑誌などさまざまな種類があるため、どのような人にPRしたいかを考えて選ぶといいでしょう。ただし、掲載には費用がかかることを理解しておく必要があります。
地域PRに動画を使うメリットと効果

紹介した地域PRの方法の中でも、動画には特に多くのメリットがあります。具体的には、一度に多くの情報を伝えられるため視聴者の印象に残りやすいことや、SNSでの拡散も期待できることなどです。これらのメリットは、地域のブランディングに役立ち、地域の住民や事業の盛り上がり、観光客の集客にもつながるでしょう。
印象に残りやすい
動画は目や耳から瞬時に情報が入るため、印象に残りやすいという特長があります。風景やスポットについて文字で読むよりも、映像で見たほうが印象に残り、後からでも思い出しやすいものです。必要に応じて字幕やテロップ、図解などが使えます。視聴者に対して直感的に訴えられるため、「この地域=この映像」と認識してもらいやすくなるでしょう。
多くの情報を伝えられる
映像や音声で構成される動画には、多くの情報が詰まっています。文字のみの場合は、読者に読んで想像してもらわなければなりません。読者の解釈によって、思い浮かべるものが異なる場合もあるでしょう。
しかし動画では映像や音声を使うことで、説明することなく伝えたい情景を理解してもらえます。映像と音声に文字などをうまく盛り込むことで、短時間でも多くの情報を伝えられるでしょう。
拡散性が高い
SNSには投稿をほかの人とシェアしたり、自分の投稿に引用したりする機能があります。動画をSNSに投稿することで共感を集められれば、さらに多くの人への拡散が期待できるでしょう。YouTubeなどの動画サイトのコンテンツを共有することも可能です。
InstagramなどのSNSやYouTubeは世界中で利用されているため、日本のみならず海外の人にも見てもらえる可能性があります。多くの人に視聴してもらうことで、地域の情報や印象が広まるでしょう。
地域のブランディングに貢献する
動画で地場産業や観光スポット、歴史などの情報を伝えることで、多くの人に地域に対する共通のイメージを持ってもらえるでしょう。「行ってみたい憧れの地域」「○○の聖地、○○といえばここ」という魅力的なイメージは、地域のブランディングにつながるはずです。ブランディングによって、地元の住民が抱く地域への愛着や、観光客からの認知度アップが期待できます。
地域の観光(訪問)客が増える
その地域ならではの魅力を知ると、実際に訪れてみたいと思う人が増え、地域への観光客や訪問客の増加が期待できます。地域のことを知らなければ、観光や訪問の候補地に挙がることすらありません。動画によって良いイメージを持つことで、「どこかに旅行に行きたい」と思ったときに候補地の一つとなるでしょう。
観光や滞在の具体的なプランを発信することも効果的です。PRのしかたによっては、海外からの観光客やワーケーションをしたい人も呼び込めるでしょう。
地域の活性化になる
地域PRによって、住民や地元の企業は地域のよさを再発見し、誇りや愛着を持つようになる可能性もあります。「前より地元が好きになった」「他の地域にはない魅力がある」という気持ちは、地域の活性化につながるでしょう。
地域と関わりのない人へもPRすることで、観光や訪問に来てもらえる可能性もあります。
観光客や訪問客が増えることで、地元の産業や事業がさらに盛り上がるなど、地域に関わるあらゆる人による活性化が期待できます。
動画で地域PRをする際に注意すべき点

動画で地域PRを行うためには、まず視聴してもらわなければなりません。誰に何を伝えたいかを明確にした上で、動画を制作する必要があります。さらにストーリー性を加えることで視聴者により強く印象づけられ、離脱を防止できるでしょう。より多くの人に見てもらうために、外国語への対応やSNSでの拡散への考慮も大切です。
ペルソナ設定と動画制作の目的を明確化する
まずは動画を制作する目的を明確にしましょう。目的によって、アプローチすべきターゲット層が変わります。理想的な視聴者像をより細かく想定するペルソナを作ることで、伝えるべきことが定まり、より多くの共感を集められるでしょう。
例えば、移住者を増やしたいのであれば、暮らしやすさやリアルな生活感が伝わるような内容にすることが大切です。観光客を増やしたいのであれば、その地域ならではの魅力を視覚的に伝えるといいでしょう。
幅広い層の人に見てもらえるのが理想ではありますが、一つの動画ですべての視聴者層に訴求することは困難です。逆に焦点を絞って訴求することで、伝えたいことが明確になります。ペルソナ以外の視聴者層にもなんらかの印象を残せるでしょう。
ストーリー性を組み合わせる
魅力を多く伝えたいからといって、情報の羅列になることは避けなければなりません。地域の魅力を効果的に伝え、視聴者に印象づけるには、ストーリー性を持たせることが大切です。「それは何?」「続きが気になる」と視聴者が興味を持って楽しめる動画を目指しましょう。
地域の魅力を存分に表現してインパクトを持たせて見ごたえのある動画にすれば、話題性が生まれ拡散される可能性が高まります。
外国語にも対応する
SNSや動画サイトを通じて、海外の人が動画を視聴する可能性も高くなっています。映像だけで伝わる魅力もありますが、英語などの字幕や副音声を付けることで、より多くの人に地域の魅力や動画の意図を理解してもらえるでしょう。日本国内だけではなく、世界中にファンを作るチャンスとなるため、外国語に対応した動画の制作をおすすめします。
SNSとの連携を強化する
SNSは拡散性が高いため、国内外を問わず動画を見てもらうために効果的です。より多くの人に視聴してもらえるよう、仕組みを最大限に活かしましょう。たとえばInstagramでは、投稿に「#(ハッシュタグ)」を付けられます。「京都」「温泉」といった地名や特色を表すワードを付けて投稿すれば、それらに興味のある人の検索結果に表示されるのです。オリジナルのハッシュタグを作って毎回の投稿に付けることで、視聴した人のファン化を狙えるでしょう。
無料で使えるものが多いことも、SNSを活用するメリットの一つです。
地域PRでよくある失敗

動画による地域PRにはさまざまなメリットや効果はありますが、失敗することも少なくありません。動画の存在を知らない人や、興味のない人に対するアプローチ方法を考える必要があります。また1本の動画が好評でも、その効果がいつまでも続くわけではありません。ほかの動画の安易な模倣ではなく、地域の魅力を伝えつつ視聴者を飽きさせない企画が必要です。
そもそも視聴してもらえない
動画を制作したからといって、視聴してもらえるとは限りません。多くの人に見てもらうためには、どのような人に見てもらいたいかを明確にして戦略を立てる必要があります。どうすれば動画を見つけてもらえるか、自社からどのようにアプローチするかを考えてください。
誰に見せたい動画なのかが明確でなければ、誰も見ようとしてくれないでしょう。動画の内容はもちろん、認知や視聴を集めるための仕組みづくりも大切です。
継続した取り組みをしていない
動画によって一度盛り上がっても、継続した取り組みを行わなければ盛り上がりは停滞してしまいます。ほかの魅力的な動画やコンテンツに埋もれて、徐々に忘れられてしまいかねません。一度の盛り上がりで満足せず、継続的にアプローチすることが大切です。
関連のある新しい動画を投稿したり、動画にちなんだキャンペーンを行ったりと、飽きさせずに興味を持ち続けてもらうためのアイデアを出しながら取り組みましょう。
他の地域PRの模倣になっている
他の地域の成功事例を参考にすることは大切ですが、ただ真似をするだけでは上手くいかないものです。地域によって特色や魅力、知名度、アクセスなどが異なるため、その地域ならではの企画を考える必要があります。
何をしていいのかわからない場合は、プロの手を借りることも一案です。弊社はマーケティングの観点から適切な提案を行い、動画コンテンツの企画から制作までを一貫してお手伝いしています。「地域独自の魅力を効果的に伝えたい」「多くの人にインパクトを与える企画を考えたい」という場合には、ぜひお気軽にご相談ください。
https://www.generalasahi.co.jp/cd/movie/contactform/
企業が地域貢献のためにPR動画を作るメリット

地域PRというと自治体の発信を思い浮かべるかもしれませんが、企業が地域PRを行うこともあります。企業が地域PRを行うメリットとして挙げられるのは、イメージ向上のほか顧客獲得や雇用機会の増大などです。地元の住民に企業の取り組みを知ってもらい、愛着や親しみを持ってもらえれば、地域密着の企業として好感度が高まるでしょう。
企業イメージが向上する
地域の人と同じように、企業も地域の一員です。地域とかかわりを持たない企業よりも、地域を大切にする企業の方が、周辺住民の持つ企業イメージが向上する傾向にあります。事業に対する理解を得たり、応援してもらえるようになるでしょう。
PR動画によって地域の魅力を伝えることや盛り上げることは、地域貢献活動の一つといえます。住民にとって、自分の地域のために行動を起こしてもらえることは嬉しいことでしょう。
集客への好影響が期待できる
地域のPRを通して住民とよい関係を築ければ、自社の商品やサービスを使ってくれる可能性も高まるでしょう。応援してくれる人が増えれば、企業にとって経営や事業をしやすい環境になります。
企業の取り組みによって地域が活性化すれば、住民だけではなく観光客からも好意的に受け取られる可能性が高くなります。地域に密着した企業として、知名度も上がるでしょう。
雇用機会が増える可能性がある
魅力が広く認知されて地域が活性化すれば住民の増加が期待でき、住民が増えると多くの人材が地域に集まることにもなります。その結果、雇用したくても近辺に人材がいないという悩みが軽減されるかもしれません。地域密着の企業として、地元で働きたい人に興味を持ってもらえるきっかけとなる可能性もあります。
地域への貢献が、このような間接的なメリットも生み出すのです。
地域PR動画の例

地域をPRする動画はたくさん配信されており、各地が個性豊かな動画を制作しています。強いインパクトを残すものや、つい見入ってしまうストーリーのもの、何度も見返したくなるものなどPR動画は地域によってさまざまです。ここでは、4つの地域のPR動画を紹介します。ぜひ視聴して、楽しみながら動画制作の参考にしてください。
※掲載の参考事例は弊社制作のものではありません
東北観光推進機構PR動画
「Autumn Colors in Tohoku 東北の秋」のPR動画は、東北観光推進機構と東北6県が共同で海外の人たちをターゲットに制作しています。
6Kシネマカメラや4Kドローンを駆使して、東北の壮大な自然美と伝統工芸の魅力を美しく撮影しています。見どころは夏から秋へと移り変わる力強くも美しい風景です。日が差し込む風景から始まり、活気に満ちた人々が鮮明に映し出されており、震災後の東北の歩みと前向きな暮らしぶりをリアルに表現しています。
再生数2700万回超という数字は自治体の地域PR動画としては最高の記録らしいです。東北の魅力を国内外にアピールして、地方活性化に寄与した名作と言えるでしょう。
北九州市と下関市の共同制作PR動画
「関門PRムービー「COME ON 関門!」」は福岡県と山口県の間にある関門海峡を舞台とした、映画さながらのクオリティの動画です。突如現れる「海峡怪獣」に動揺して逃げ惑う人々を映し出していますが、最後には意外な展開を迎えます。
観光地や解説などは一切登場せず、あえて「関門」の知名度アップだけを狙っています。2019年にはYouTubeでの再生回数が1億回を突破するという、地域PR動画としては異例の動画で、セリフは英語、字幕は中国語や韓国語、アラビア語のバージョンもあります。
参考事例:
宮崎県小林市PR動画
「ンダモシタン小林」は、宮崎県にある小林市が制作した移住促進PR動画です。穏やかで繊細なピアノ演奏をBGMに、フランスから来たという男性が小林市の日常の風景を巡ります。
フランス語のナレーションと思いきや、小林市で話される西諸弁(にしもろべん)であったことが話題になりました。西諸弁の字幕バージョンもあり、何度も視聴し直したくなる動画です。
参考事例:
大分県PR動画
大分県のPR動画【おんせん県】「シンフロ」篇は、シンクロと温泉がコラボレーションした動画です。入浴客が温泉を楽しむ中、プロのシンクロチームが現れて見事な演技が始まります。
大分県内各地の温泉にて撮影をしており、字幕をオンにすると撮影地が表示されるという観光客に嬉しいポイントもあり、息の合ったシンクロと多彩な温泉に見入ってしまう1本です。
参考事例:
まとめ
地域の魅力を伝えるために動画を活用するPR方法が注目されています。YouTubeやSNSで手軽に動画を視聴できる機会も増え、紙のパンフレットとは異なる効果的な地域PRが可能となりました。
地域PR動画のメリットは印象に残りやすく、多くの情報を視覚的に伝えられるため効果的であり、またSNSの拡散力を活用することで地域のブランディングや観光客誘致に寄与します。企業も地域PR動画に取り組むことで地域との関係強化や企業イメージ向上、顧客獲得、雇用機会の増加などのメリットがあります。
しかし、動画制作にはターゲット設定、ストーリー性、外国語対応、SNS連携などが重要となります。地域PR動画にお困りの場合は、ぜひ弊社にお気軽にご相談ください。企画から動画制作、またアフターフォローまで丁寧に対応させていただきます。